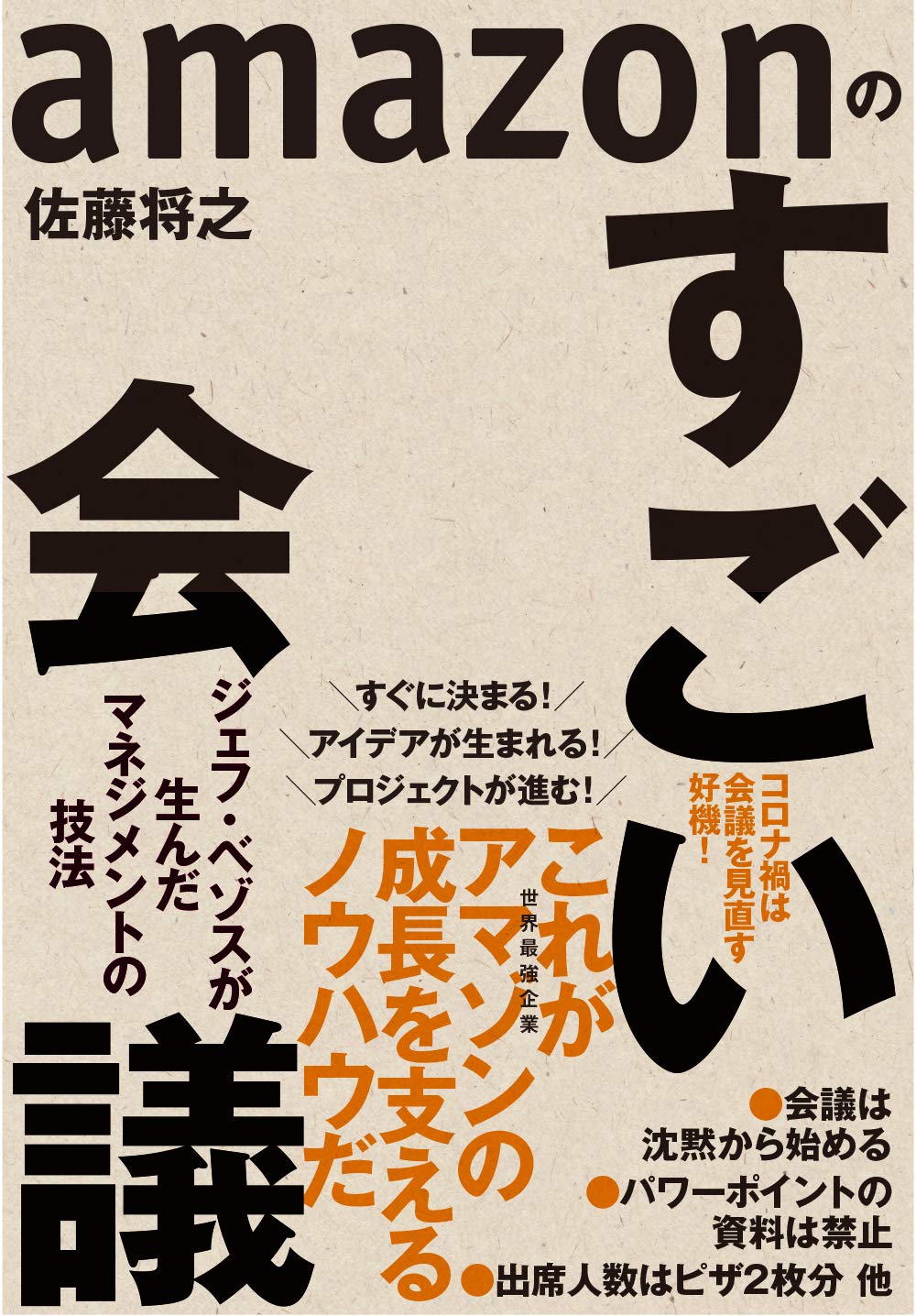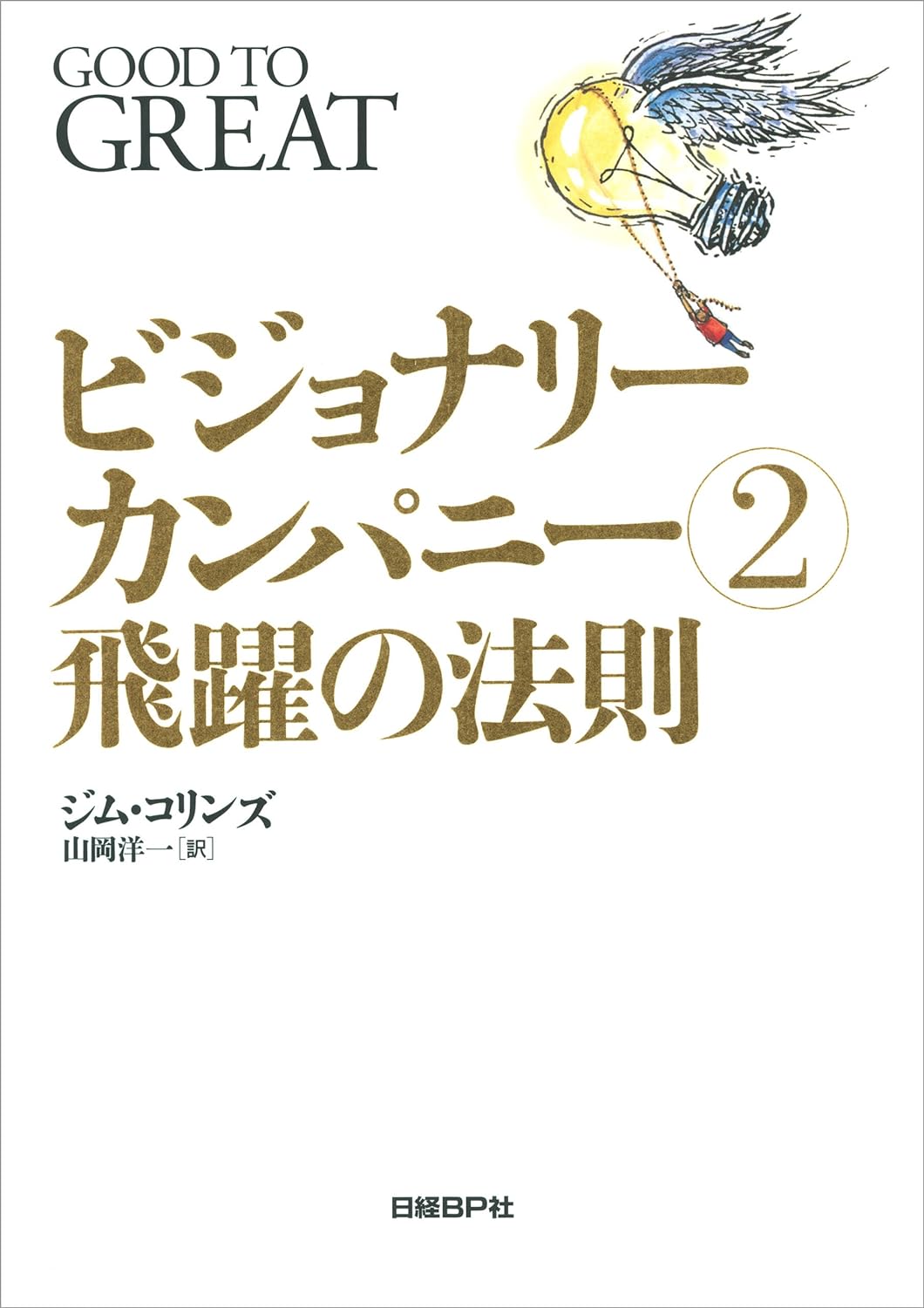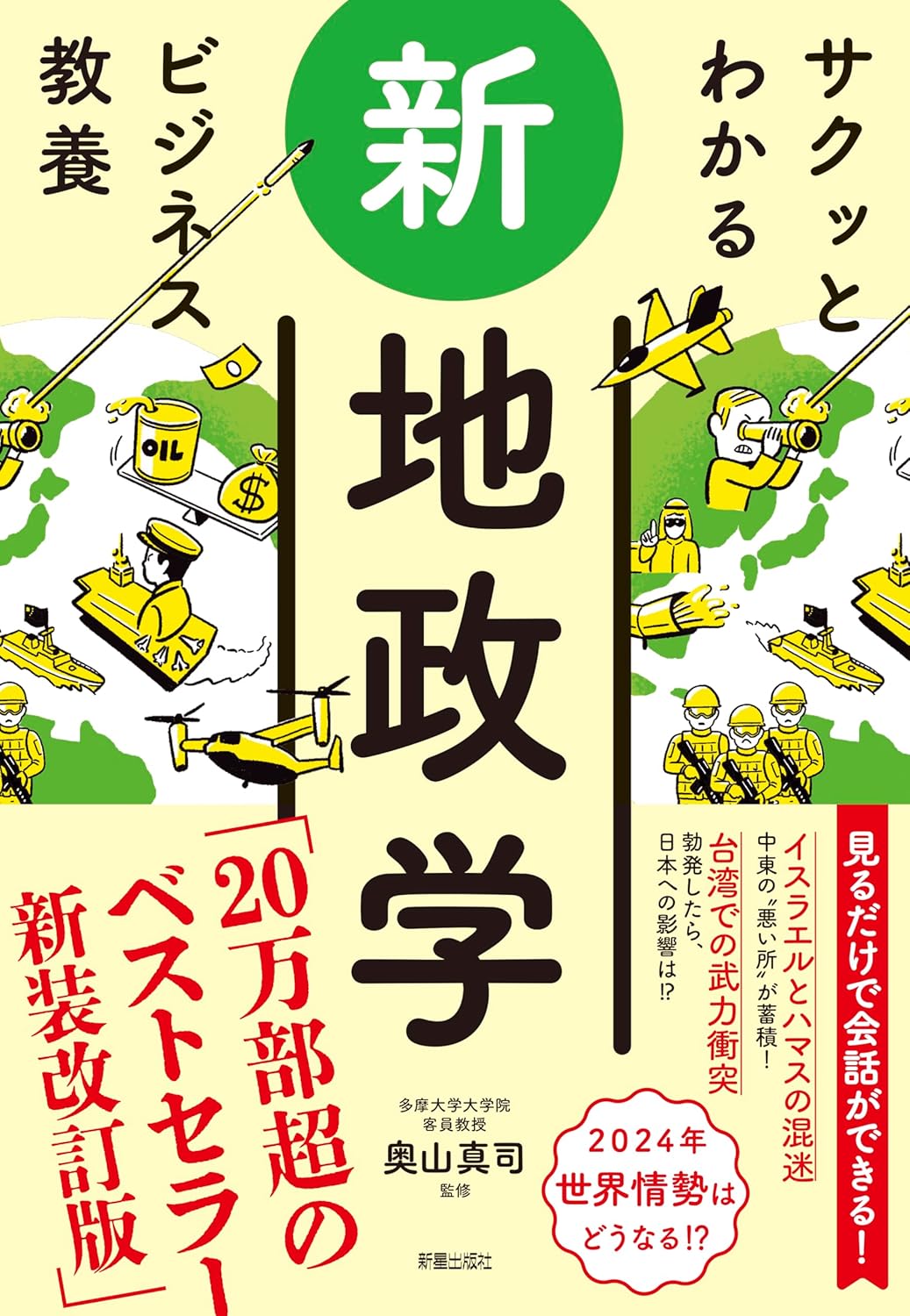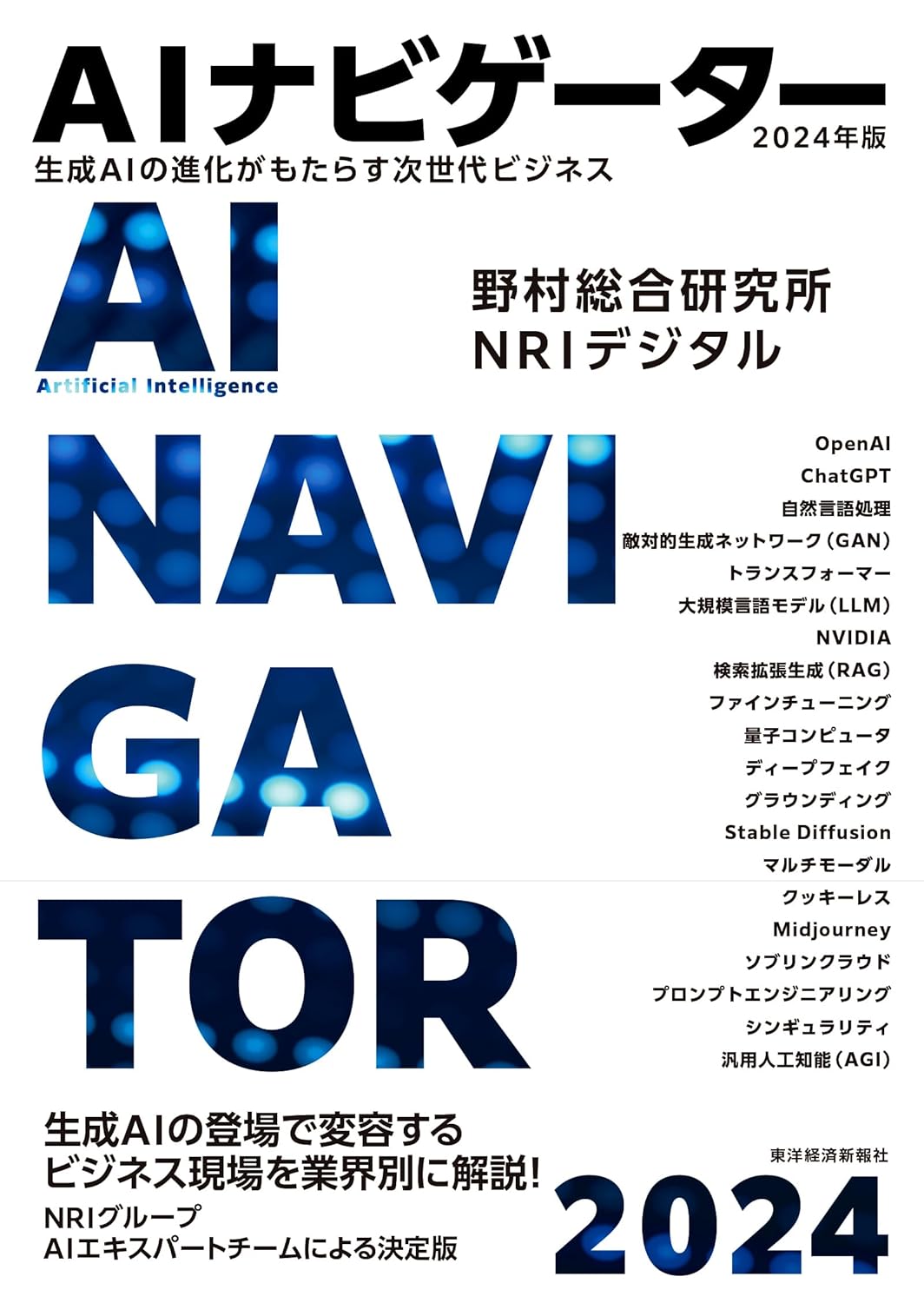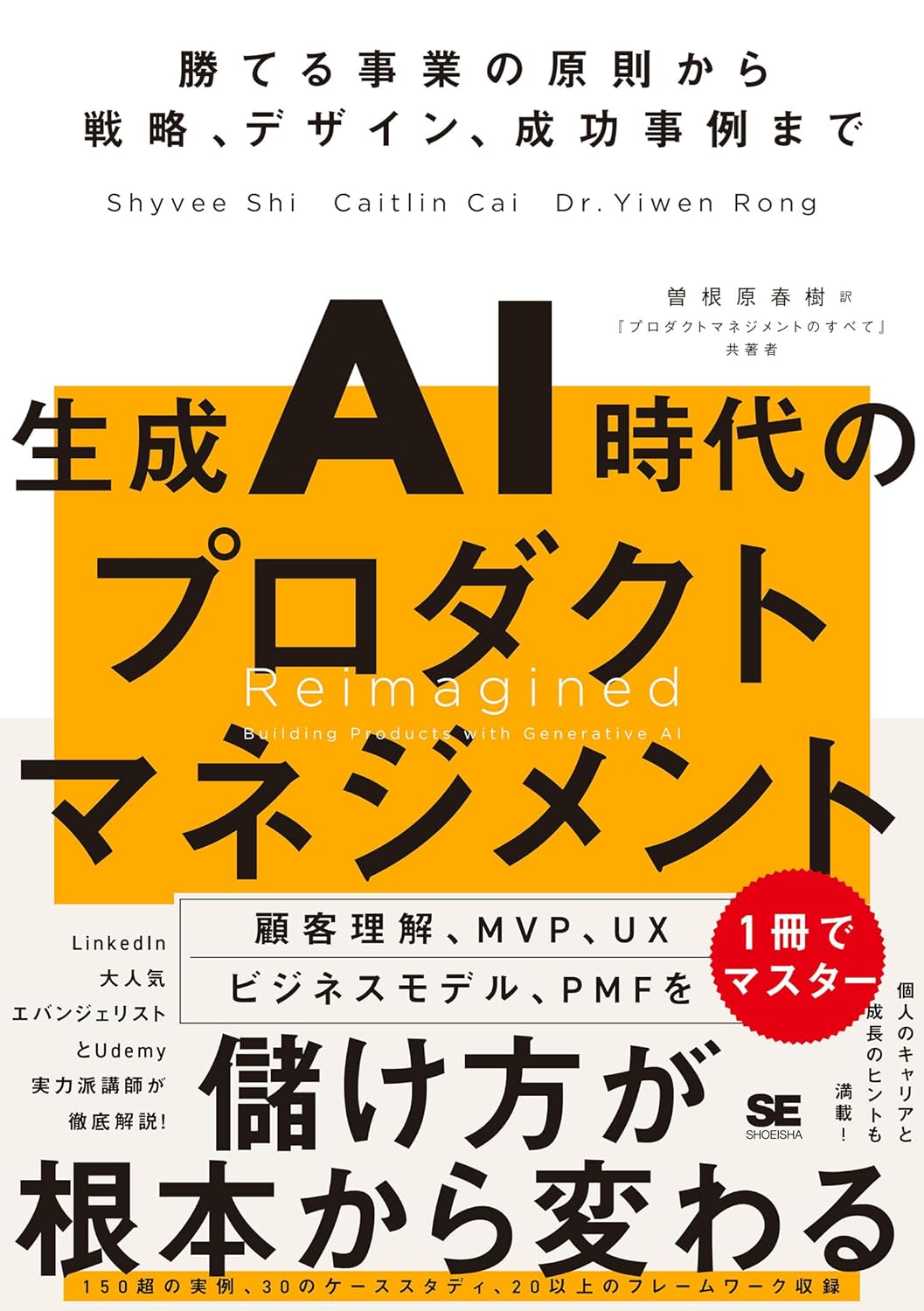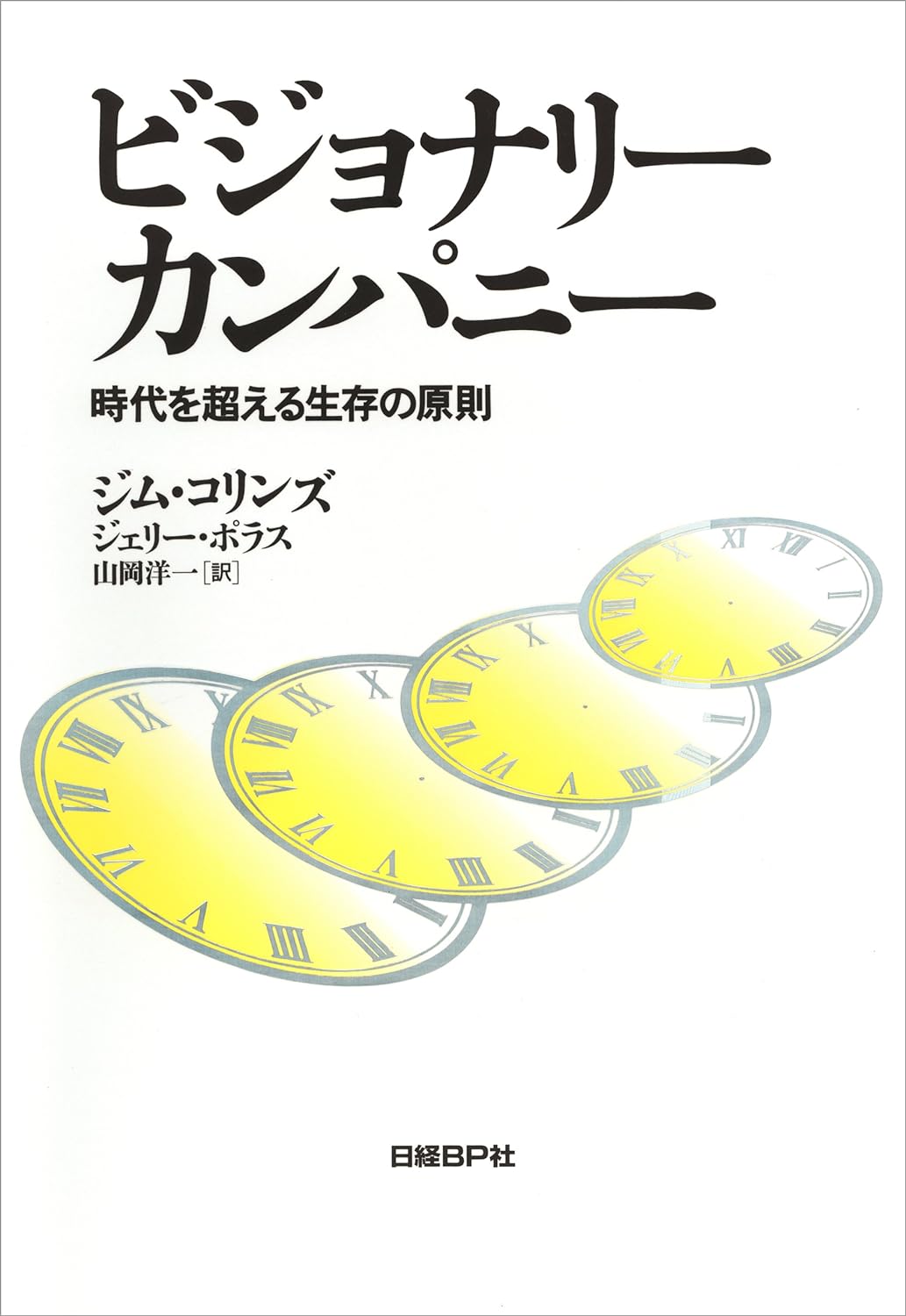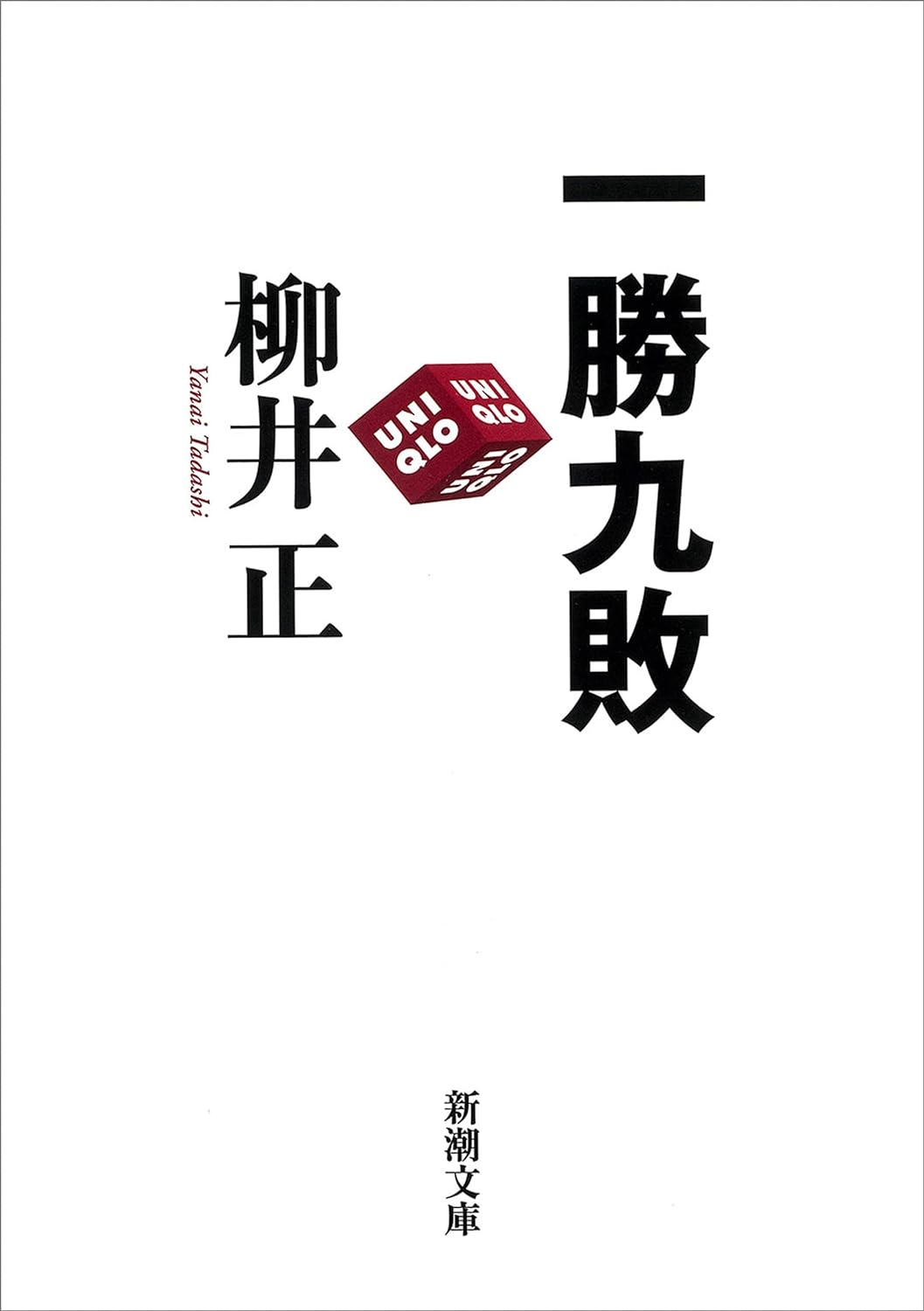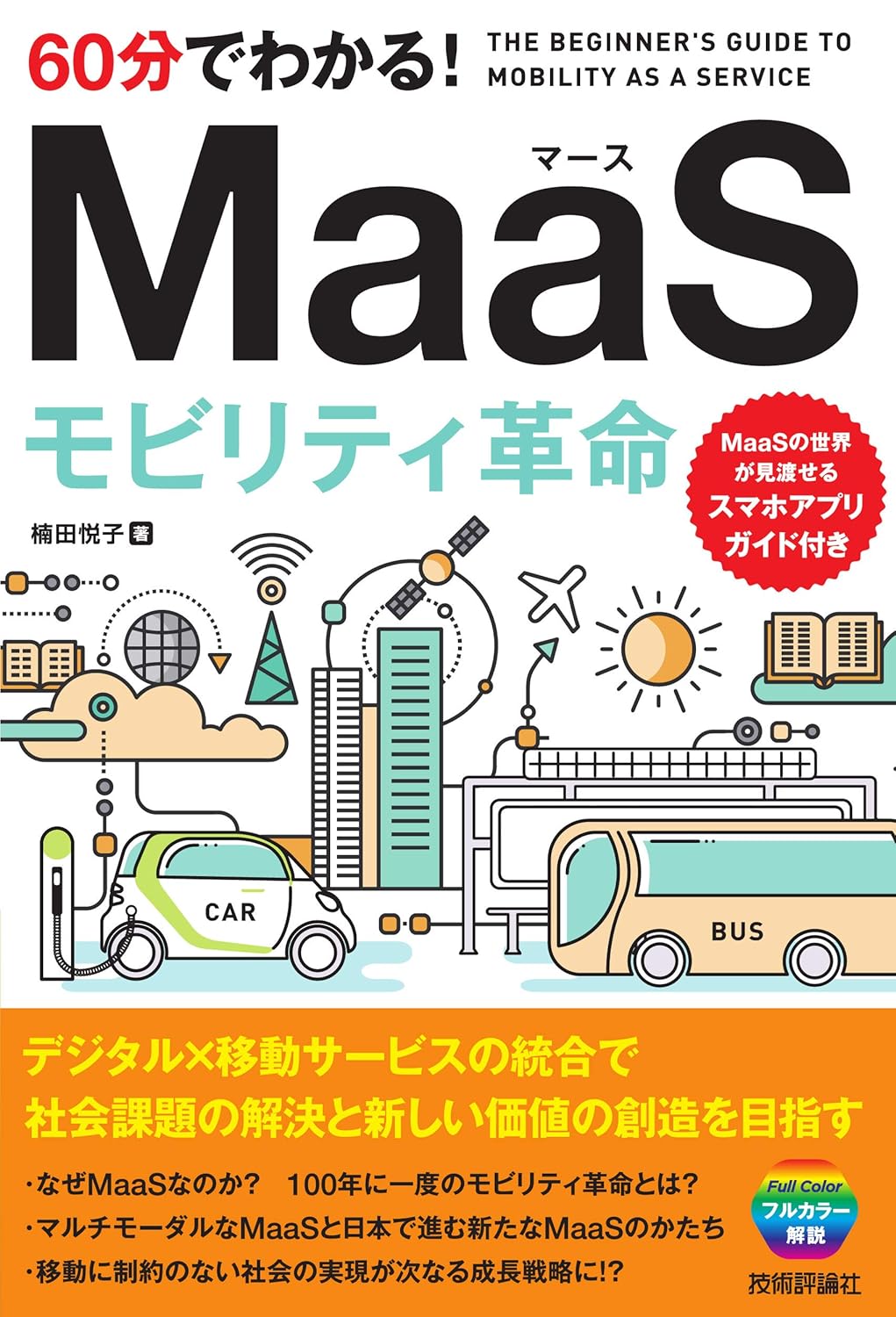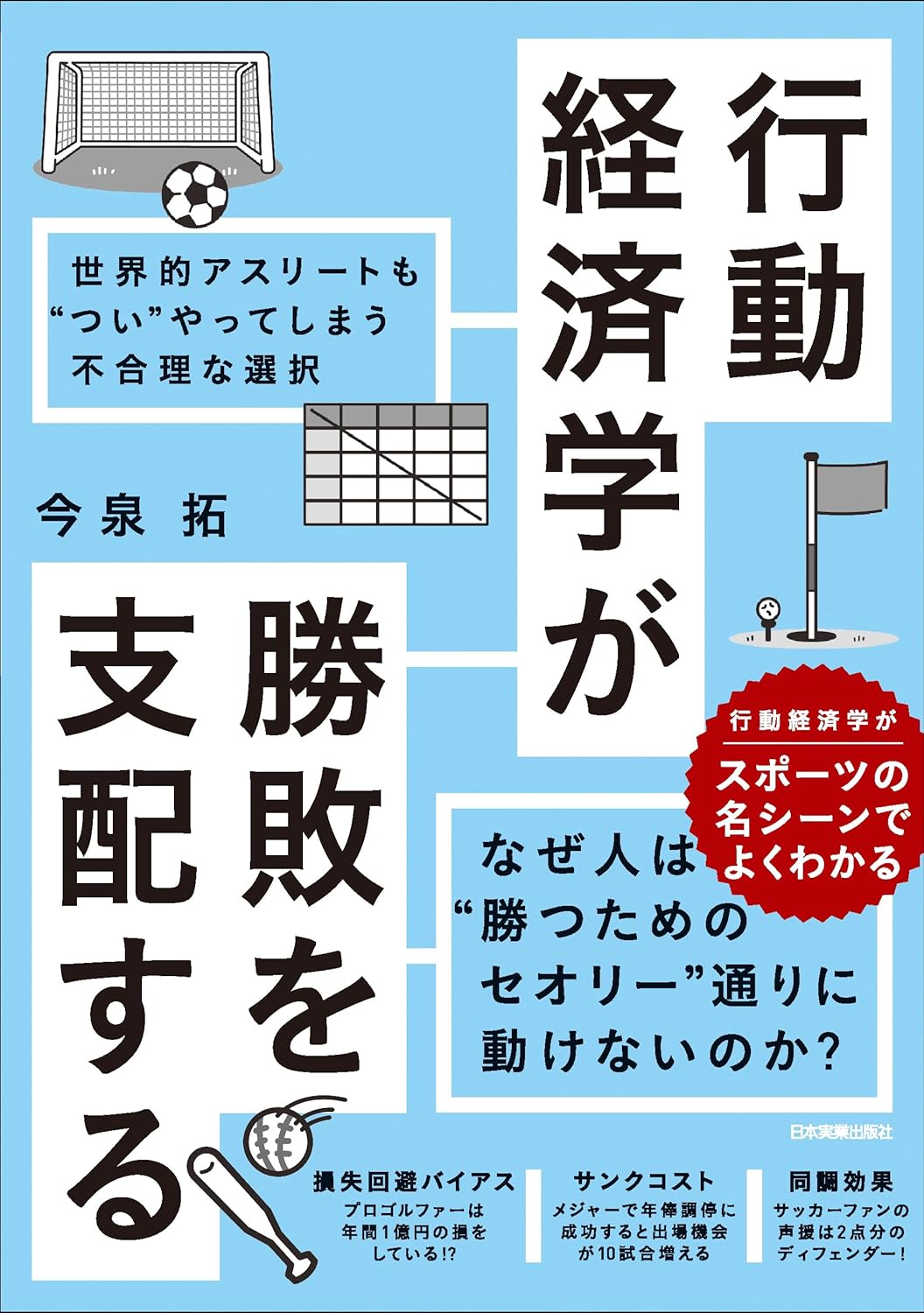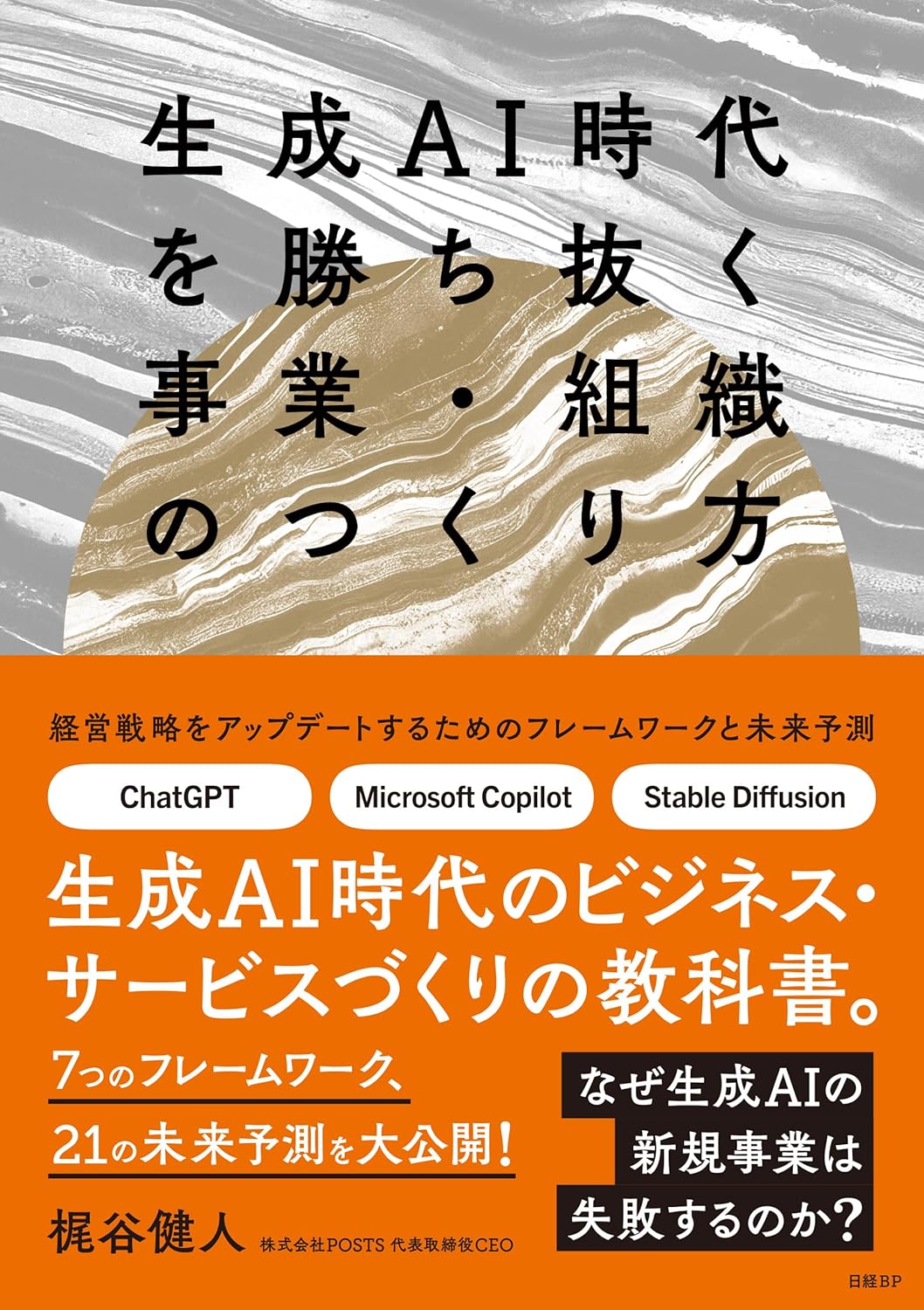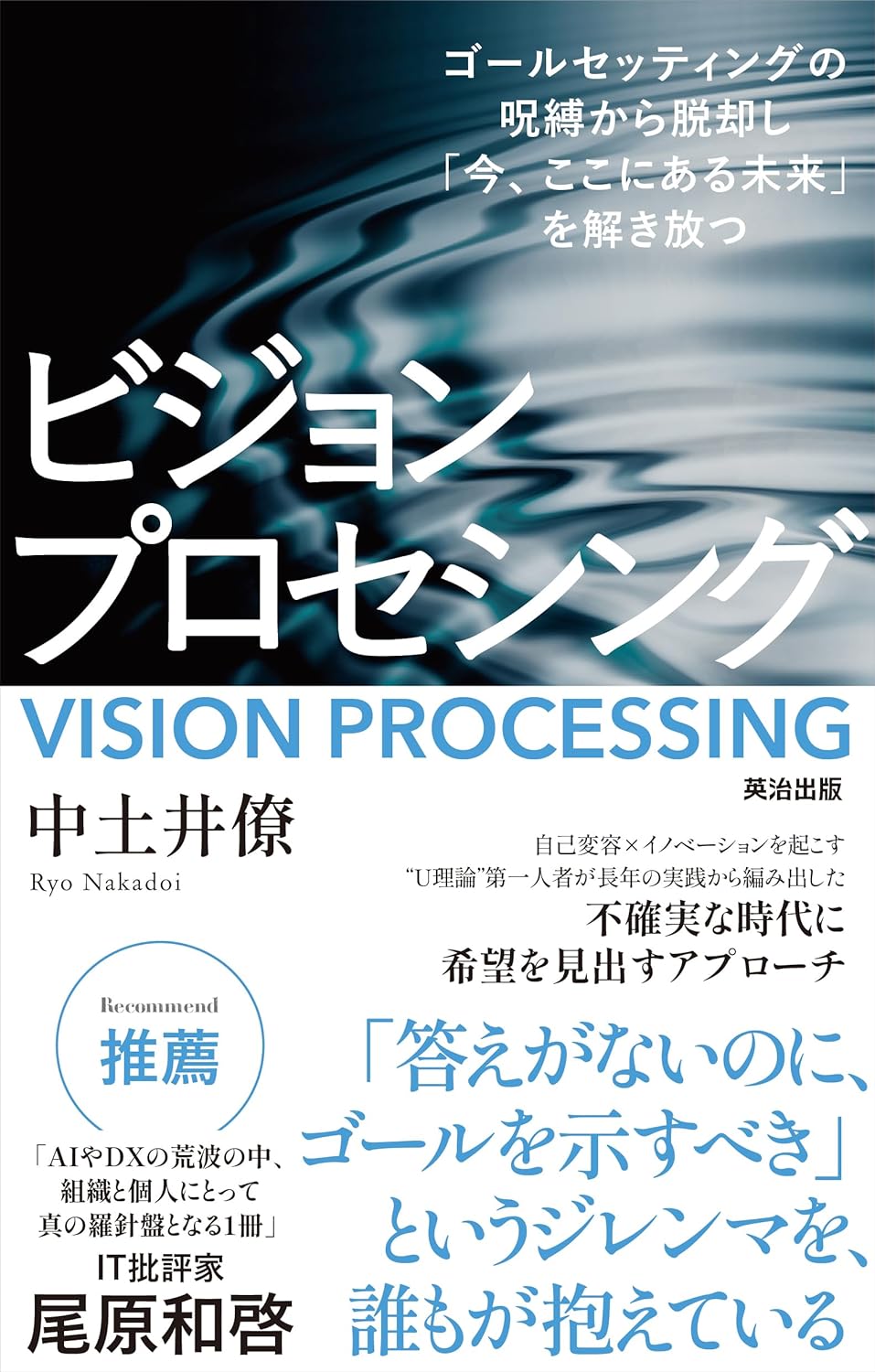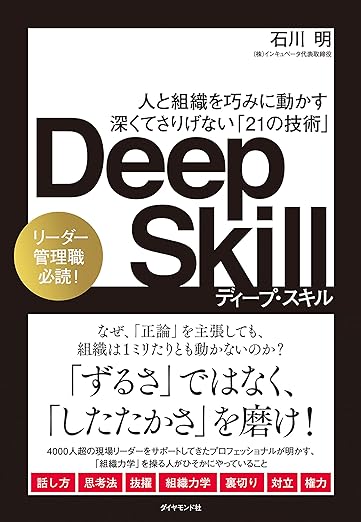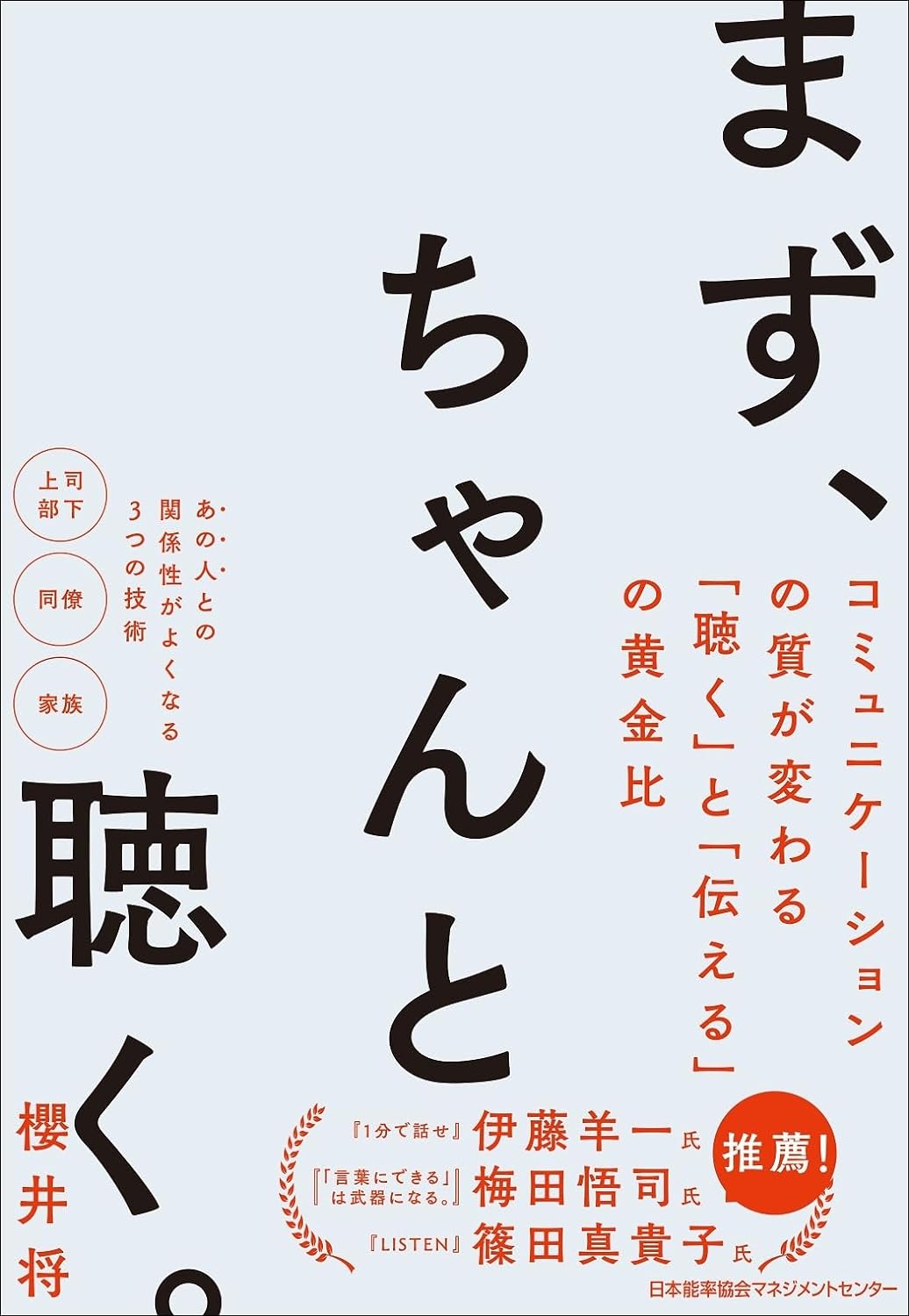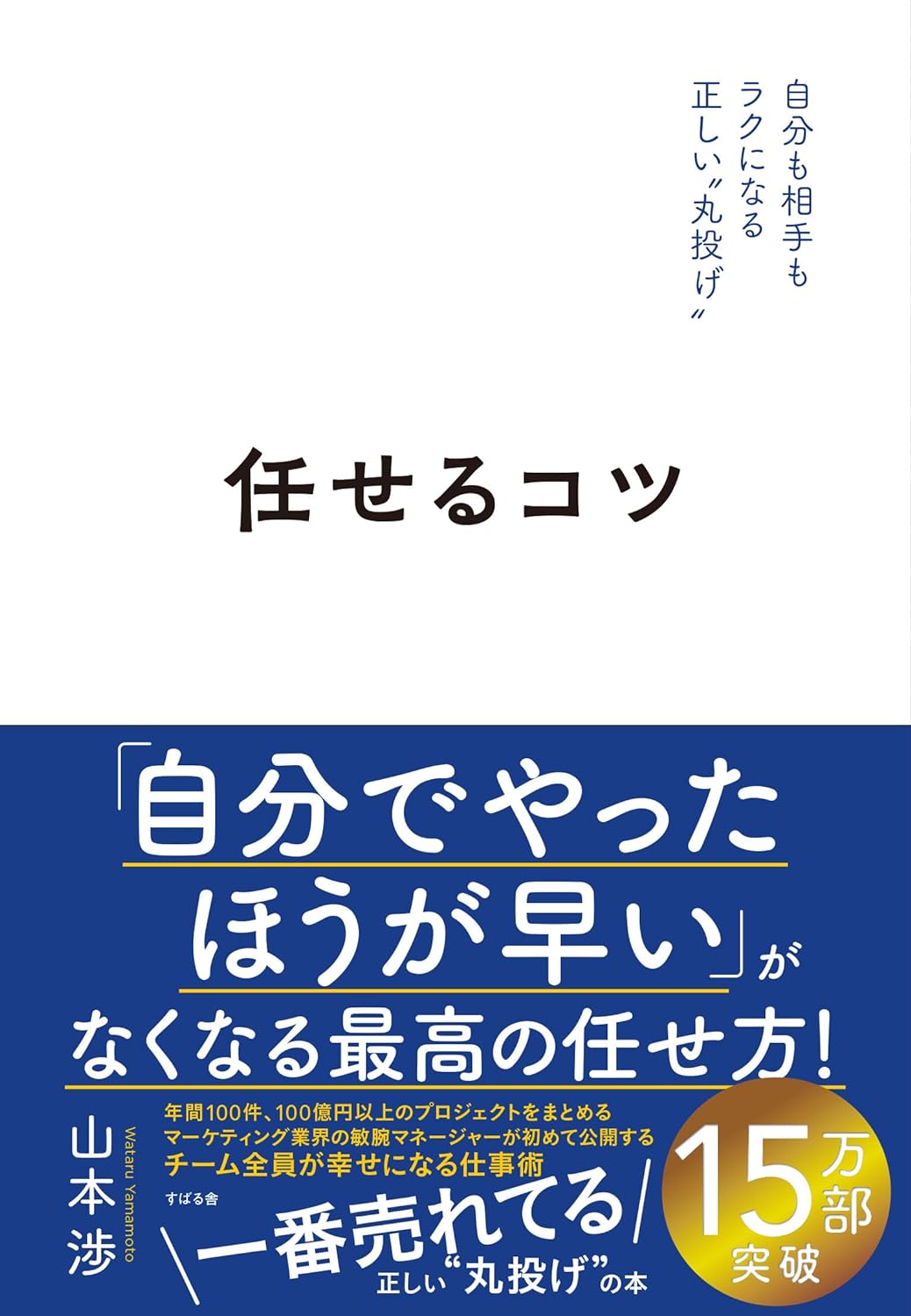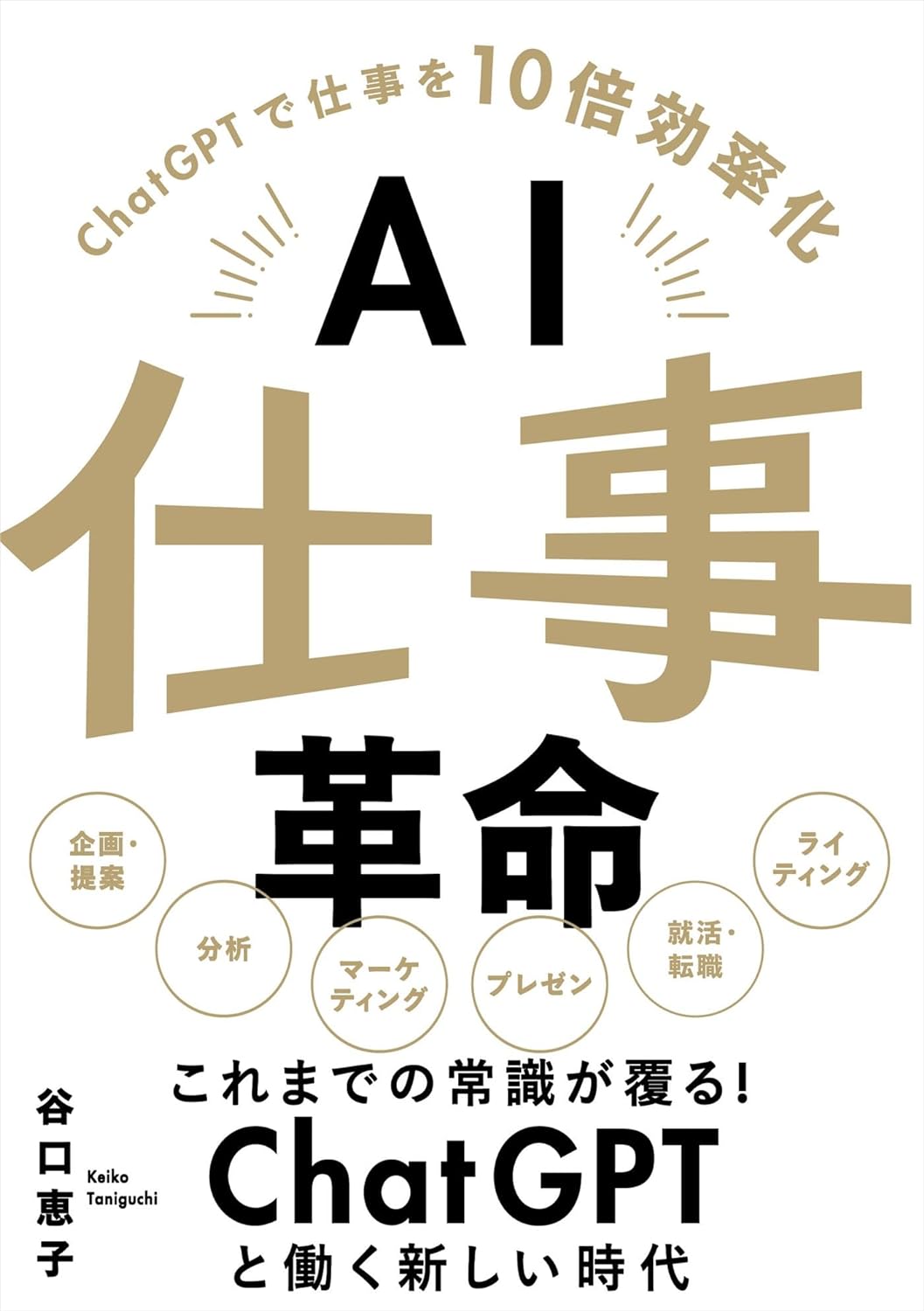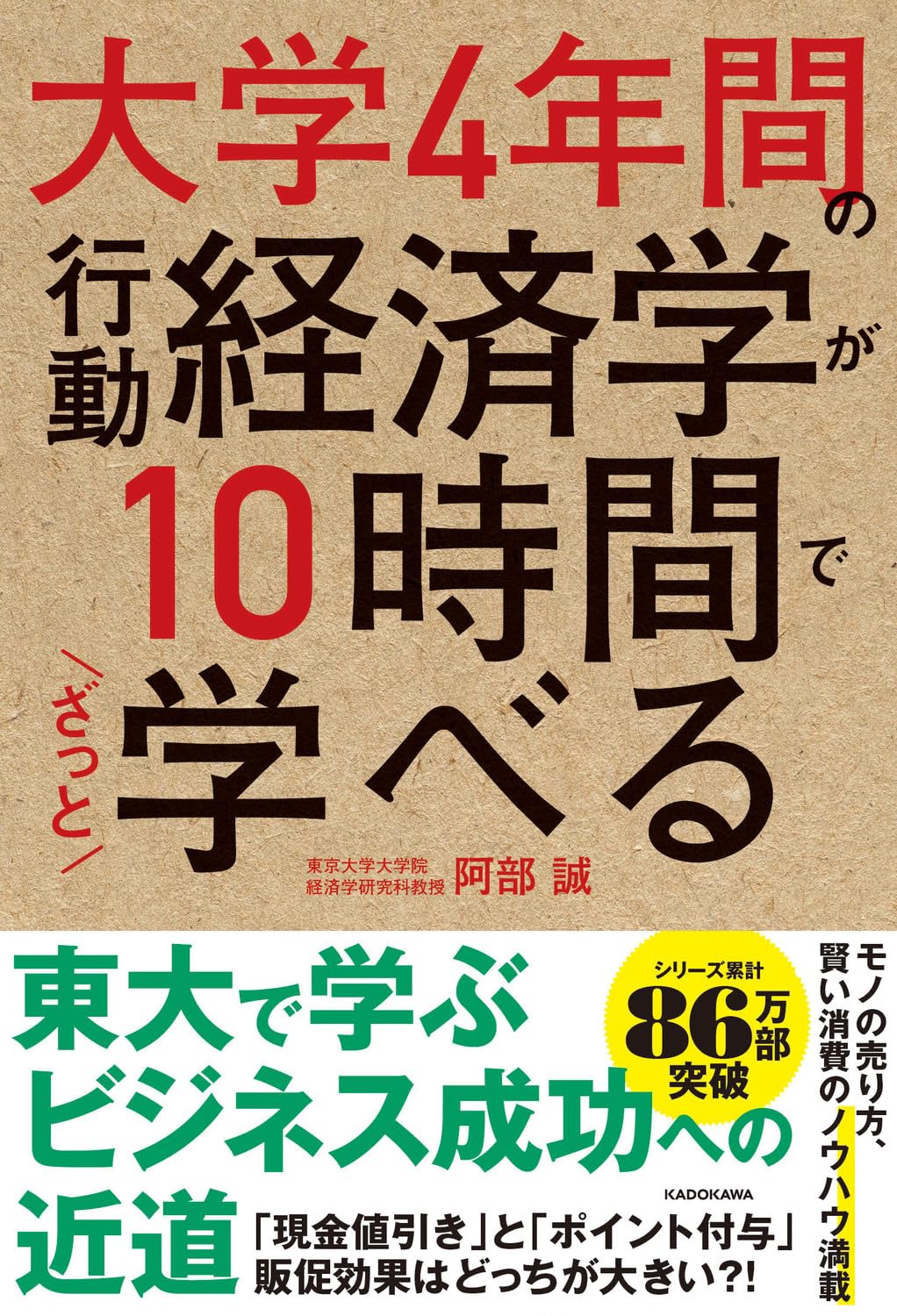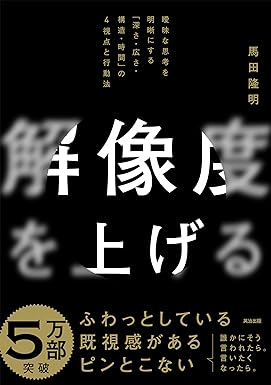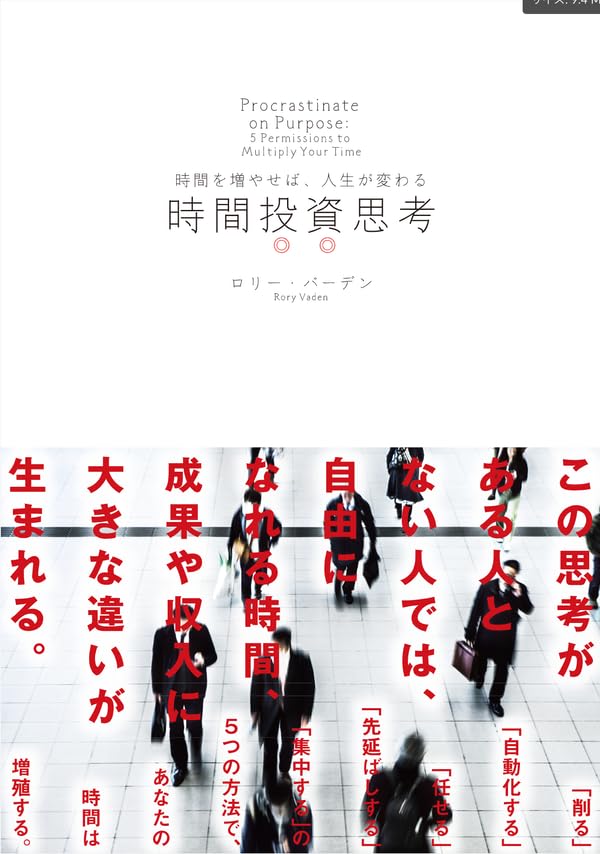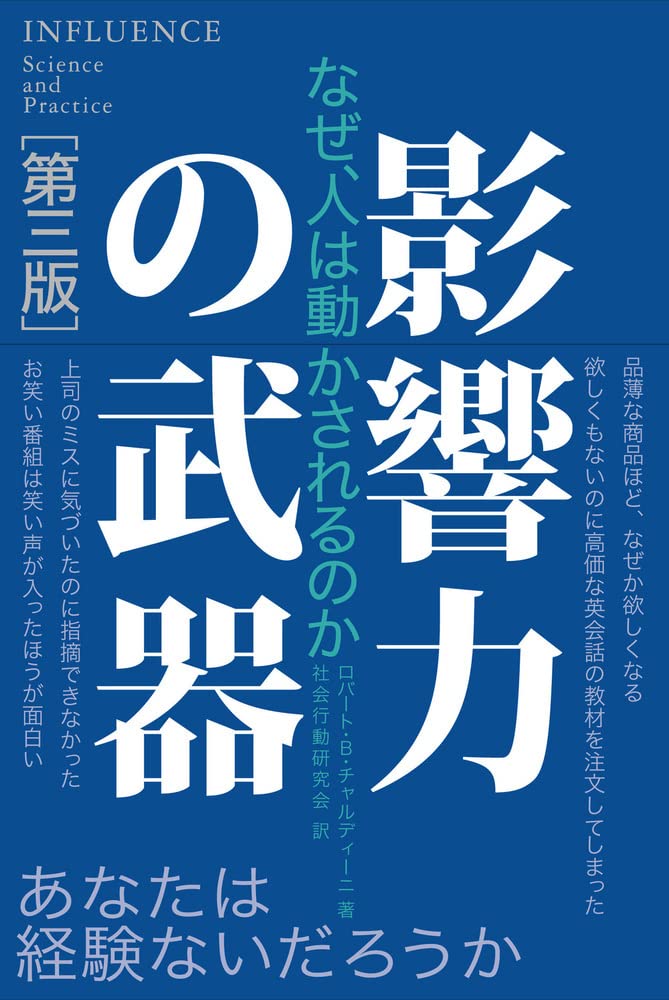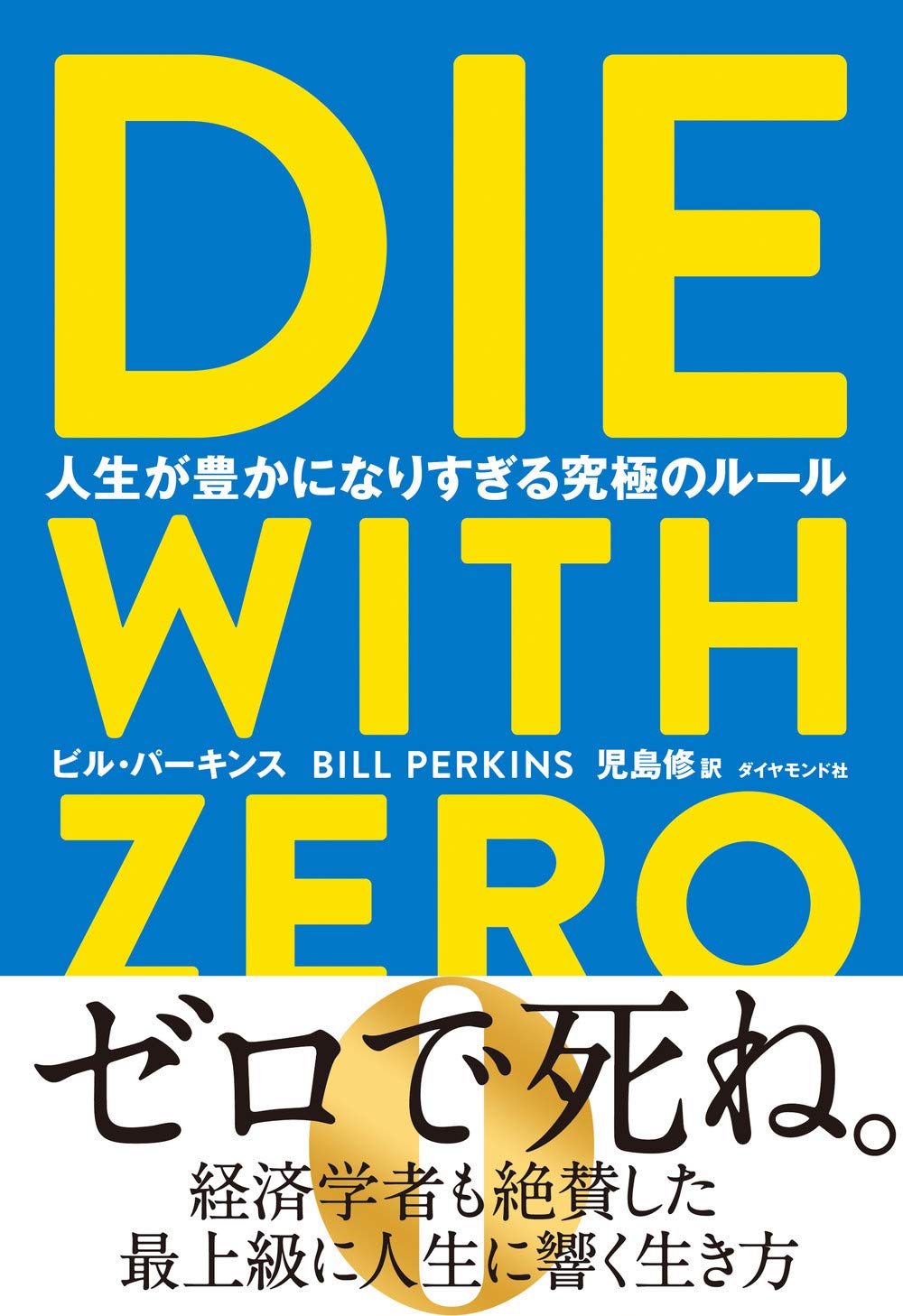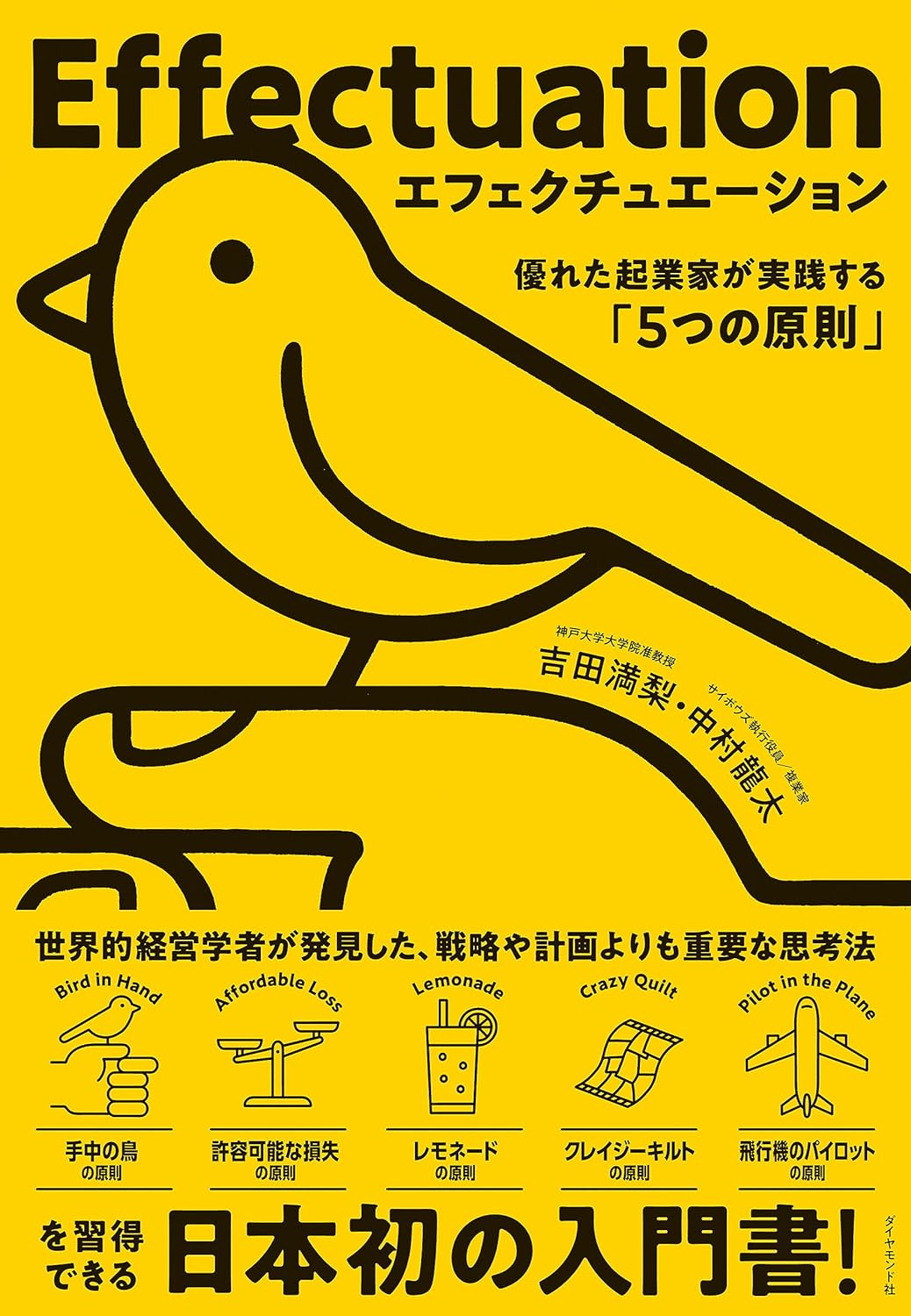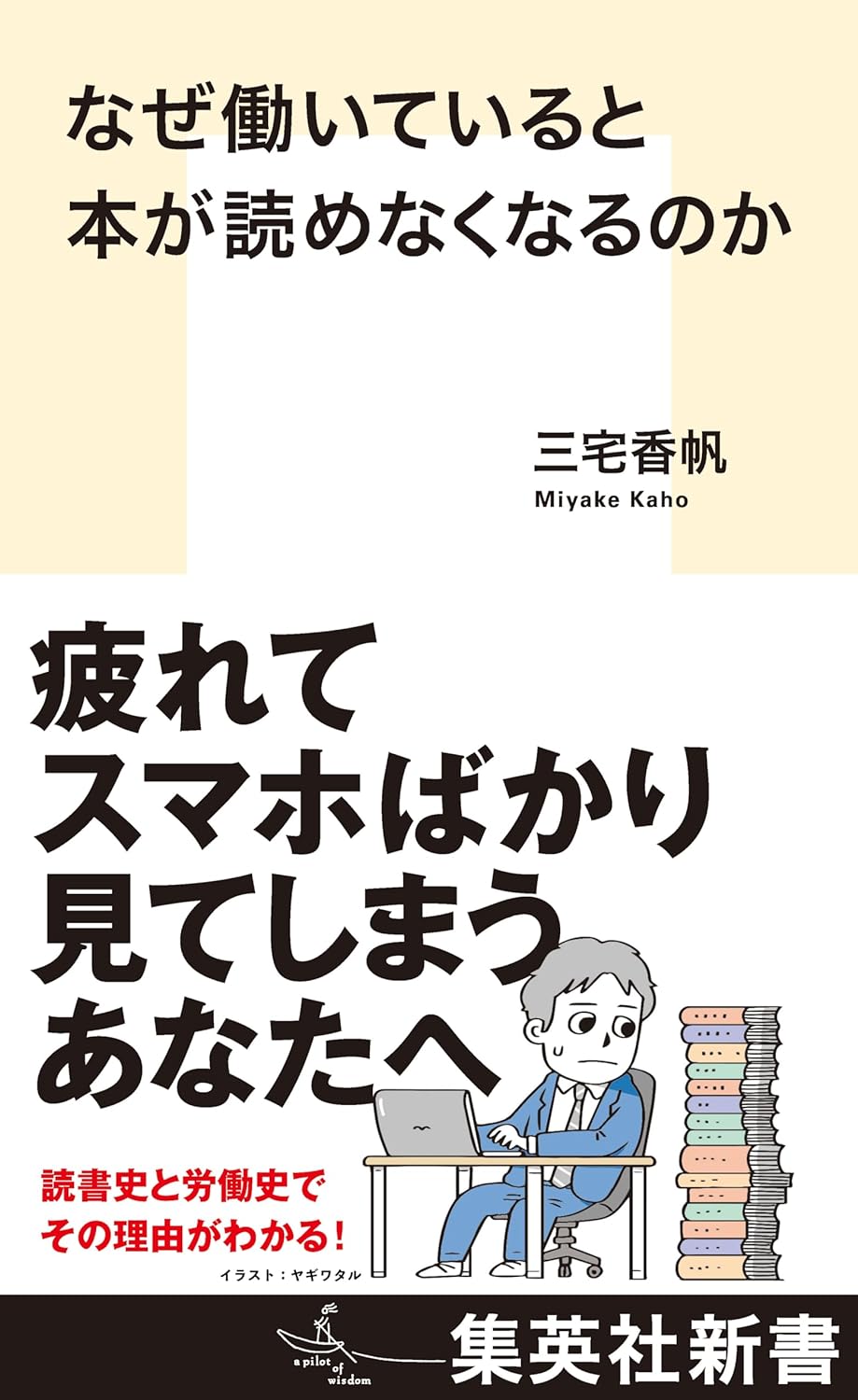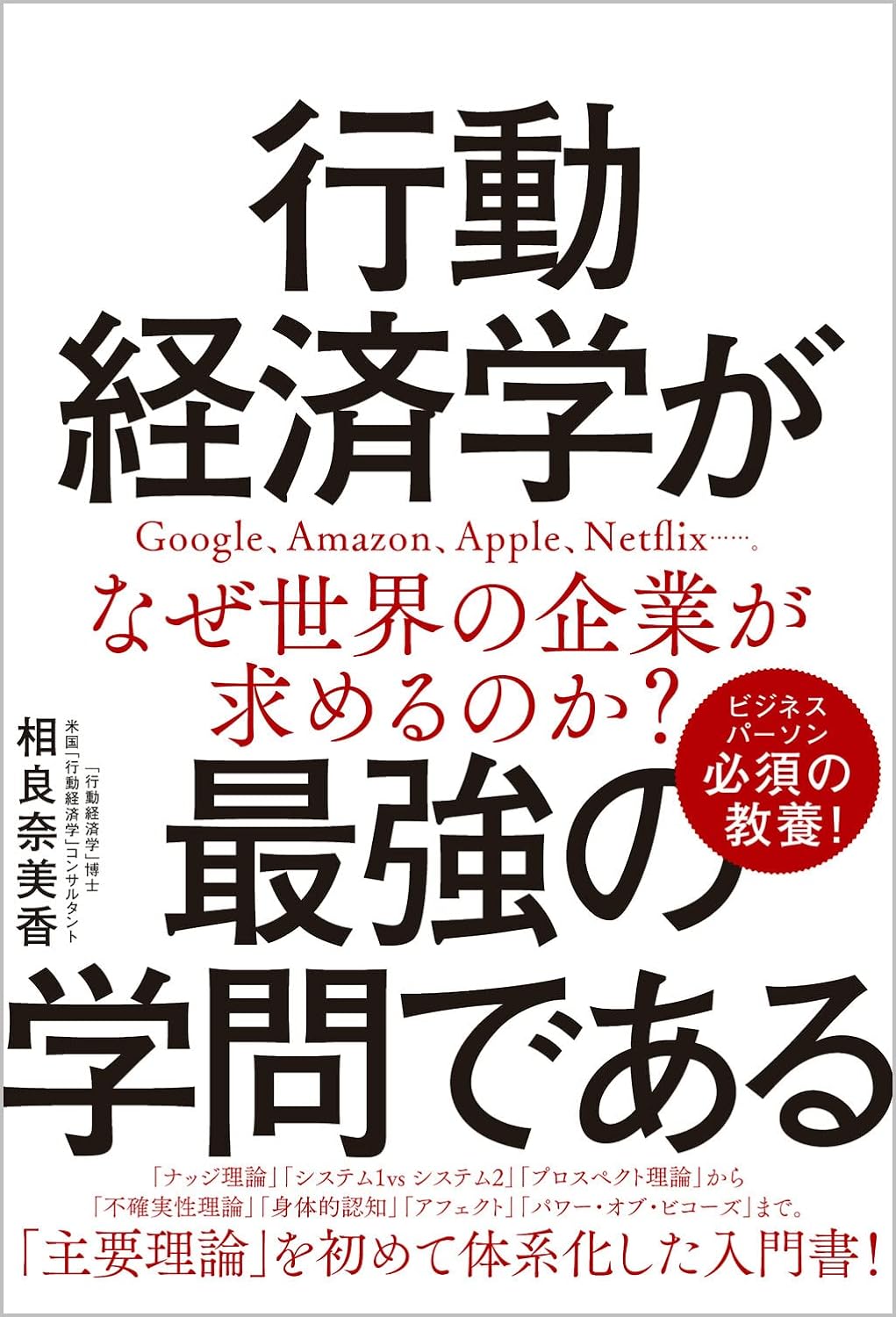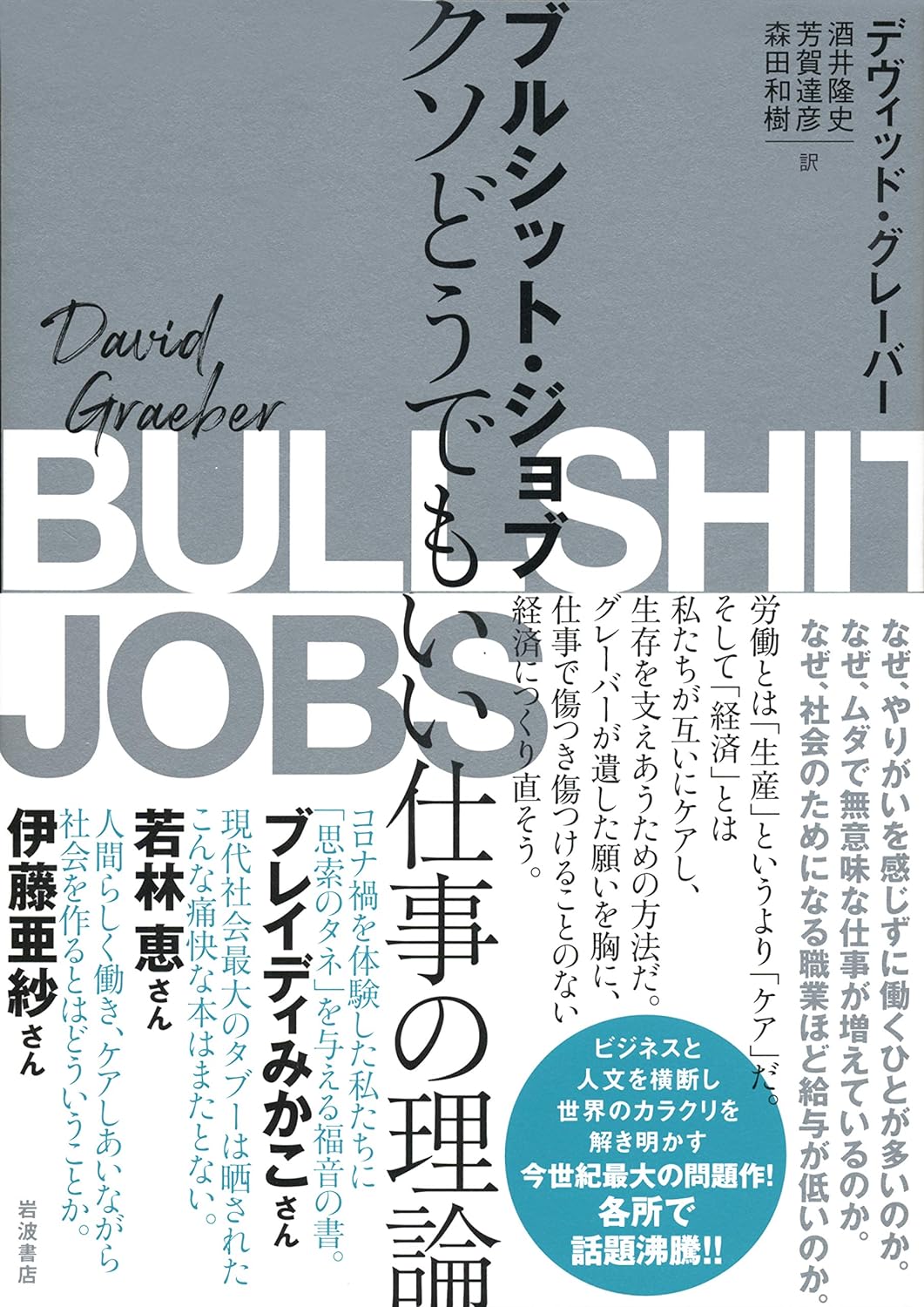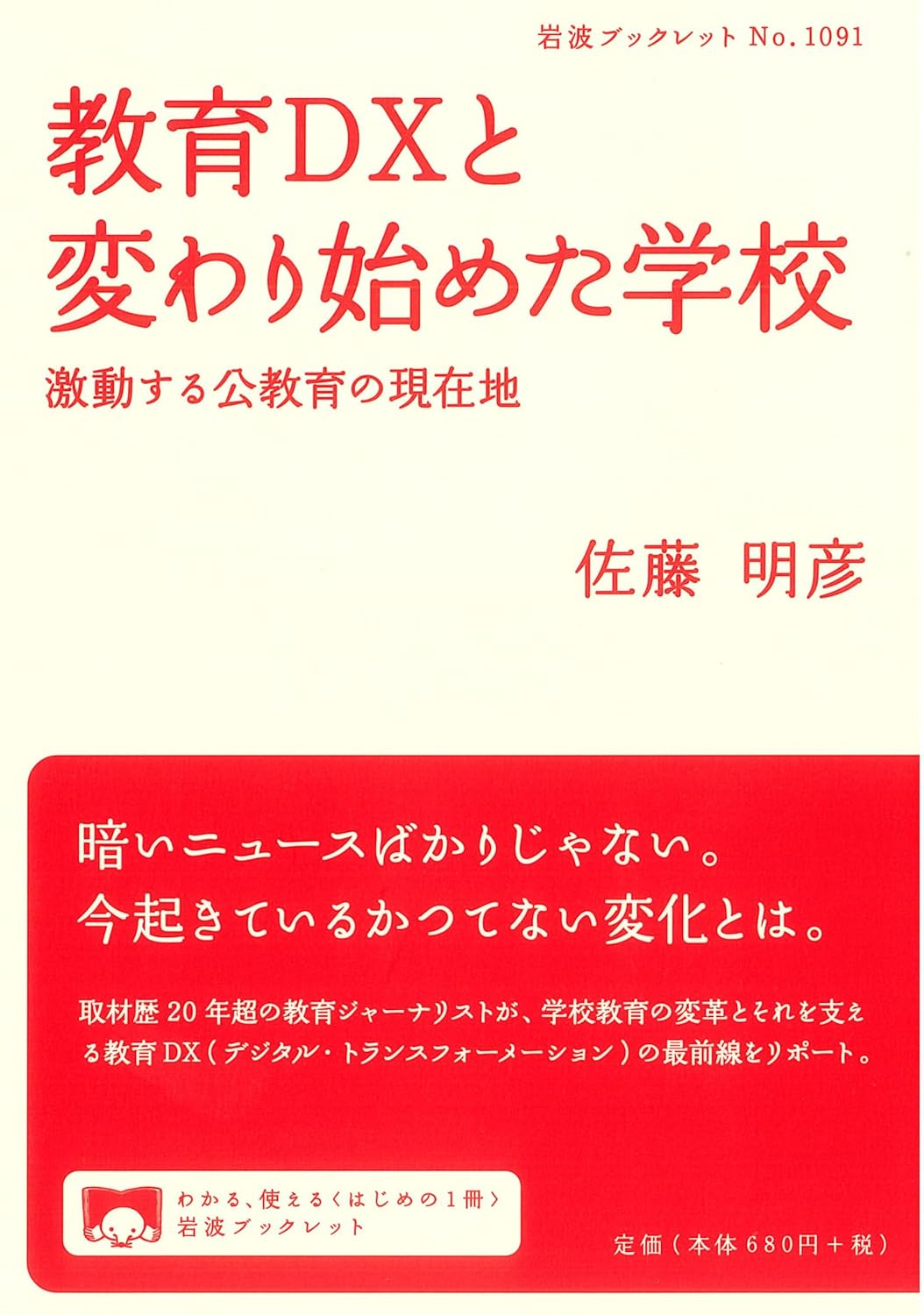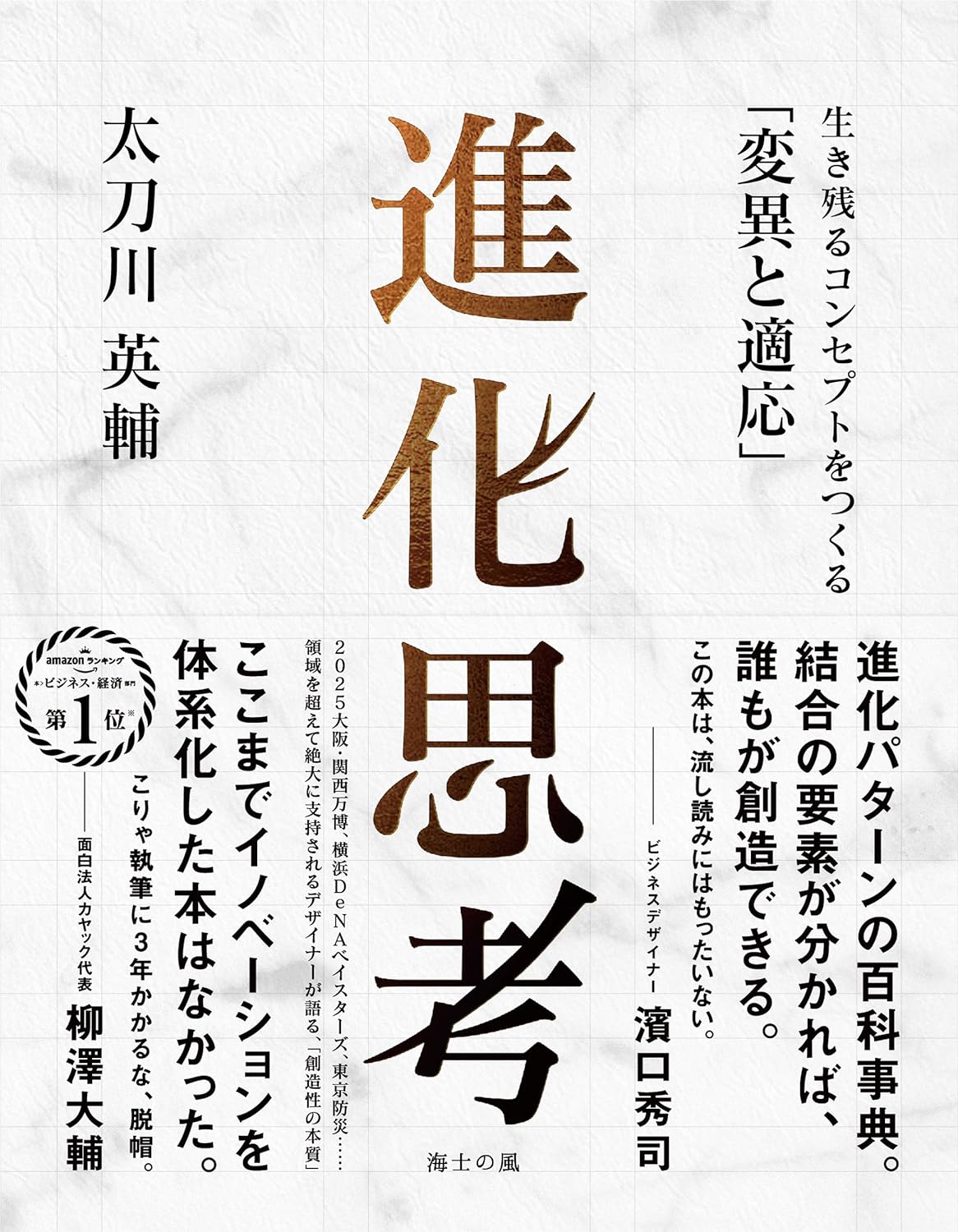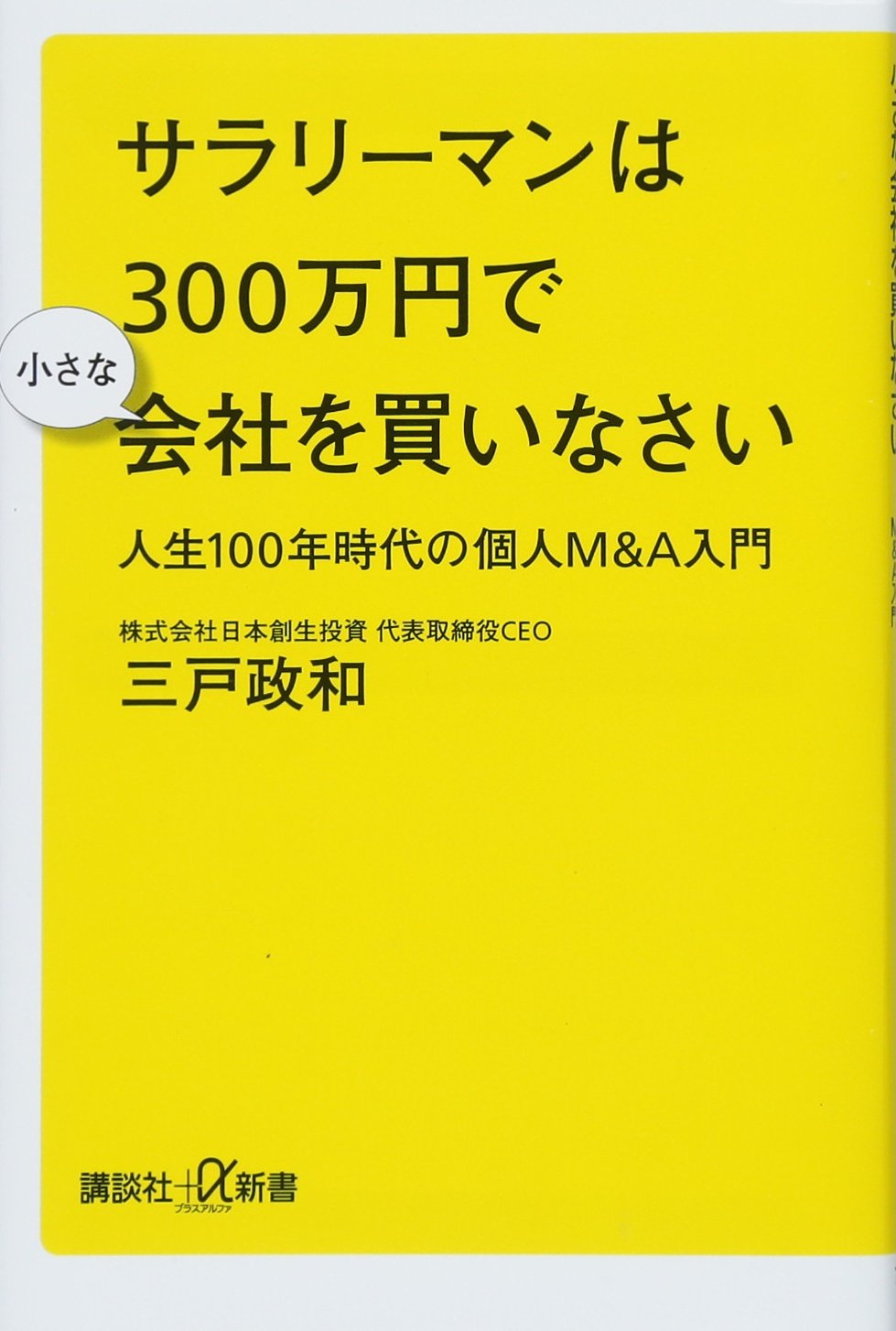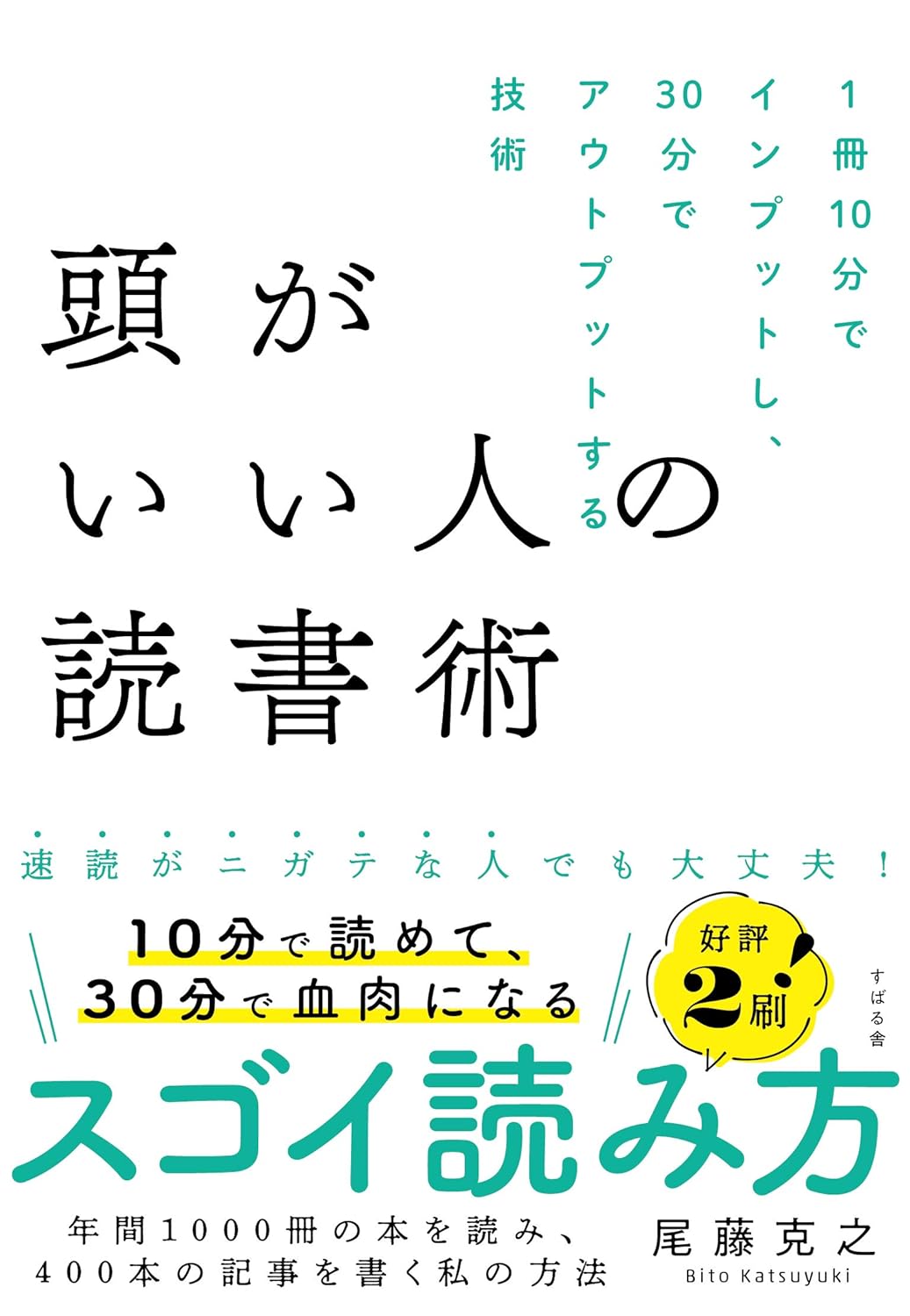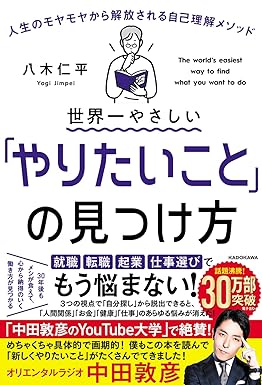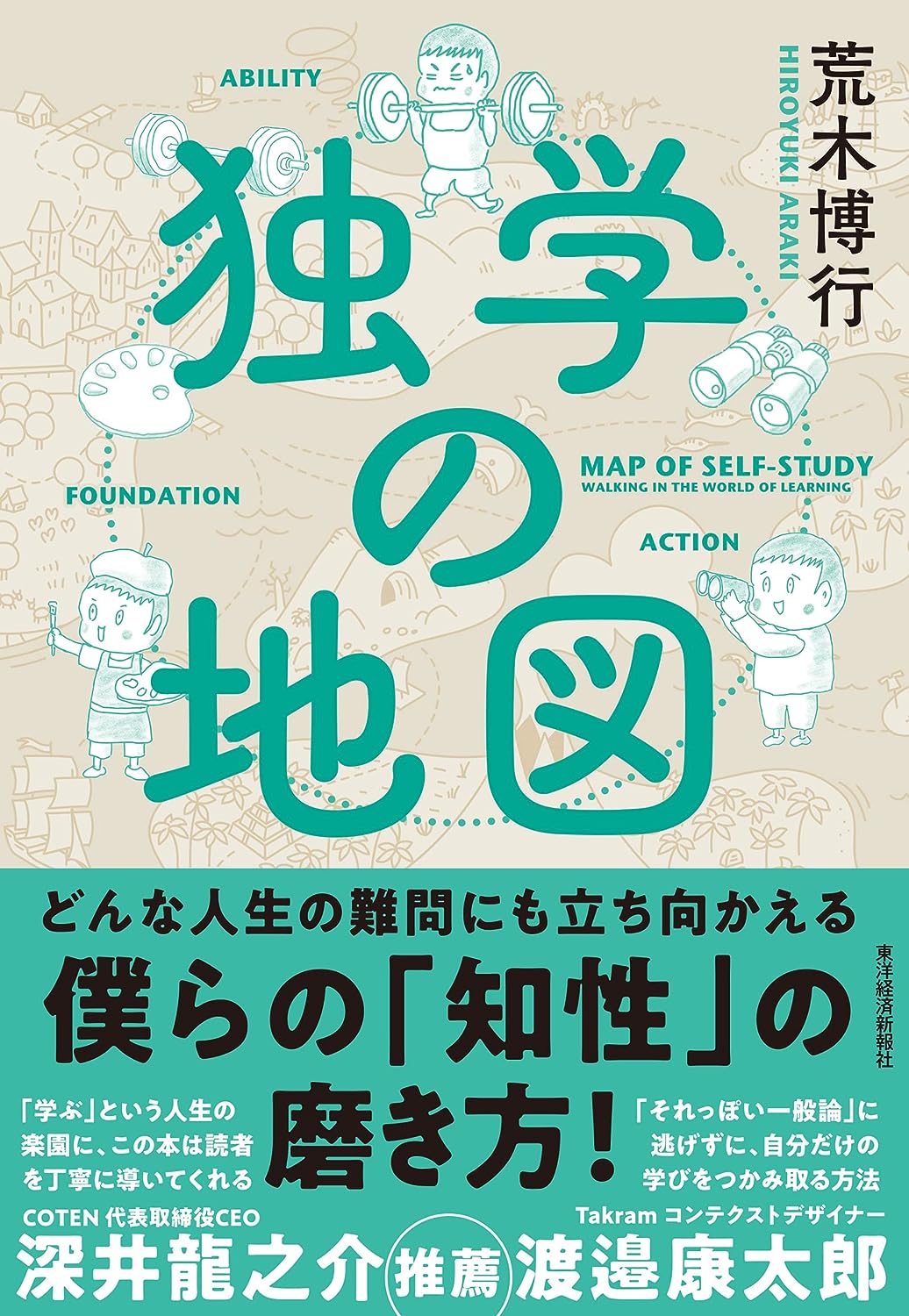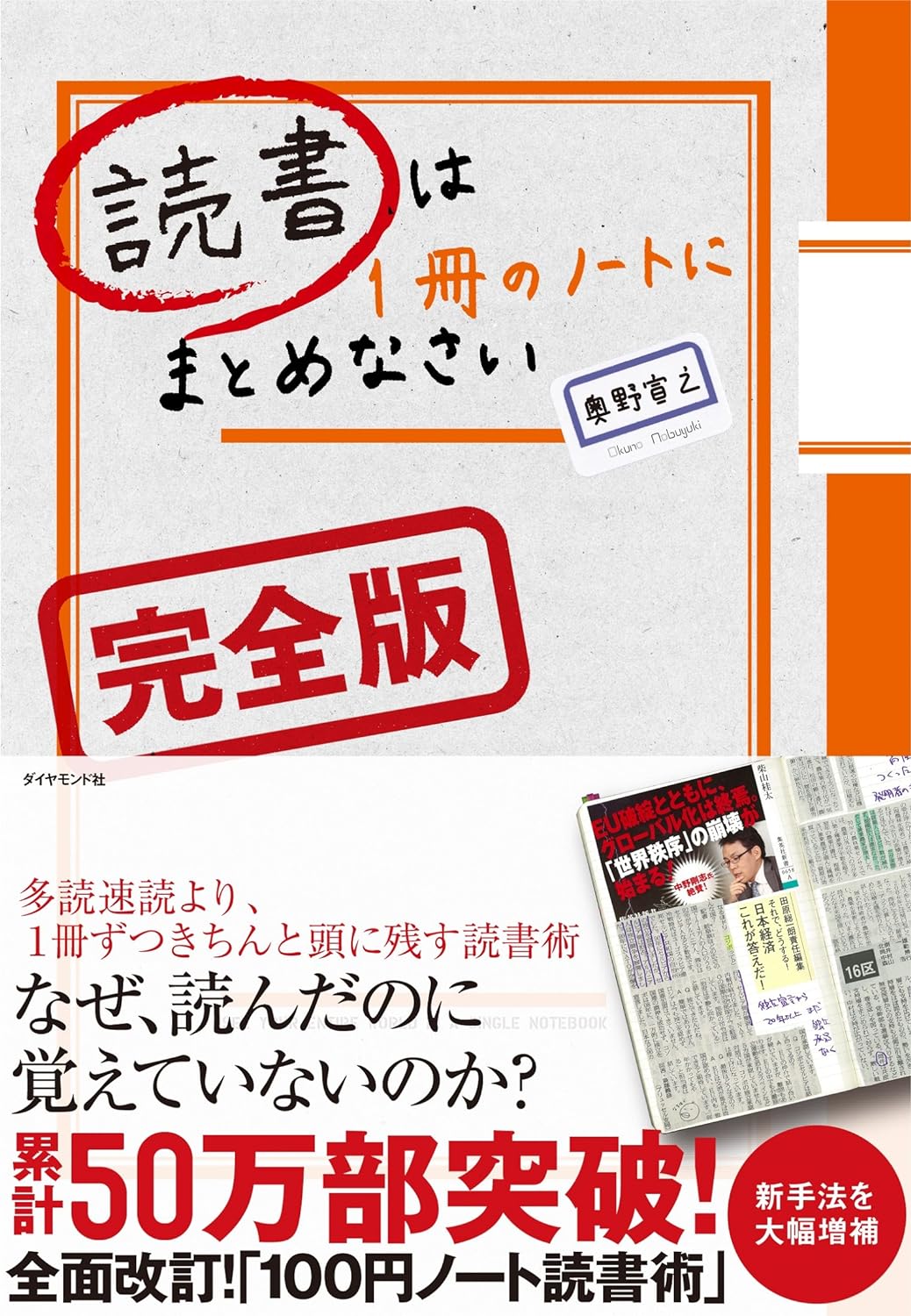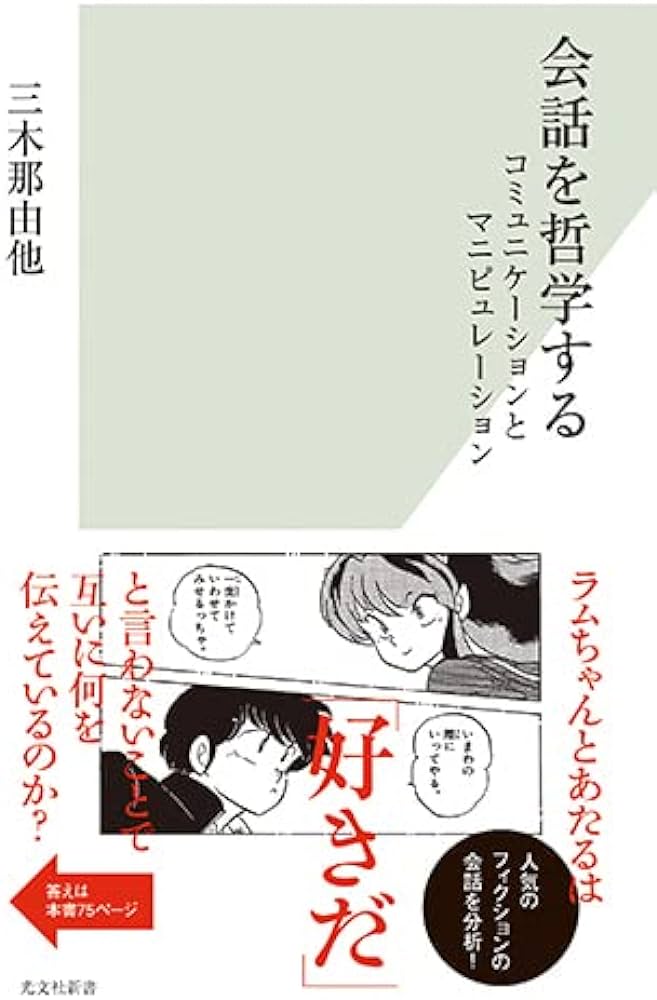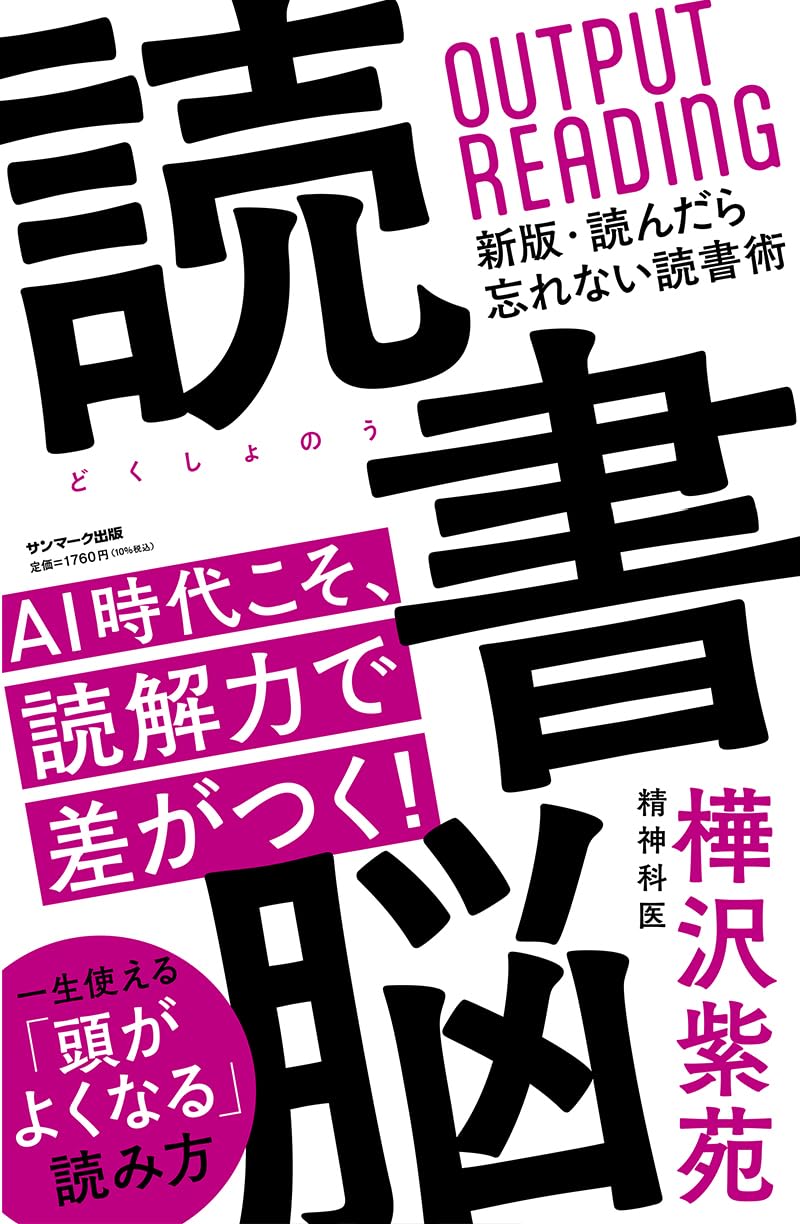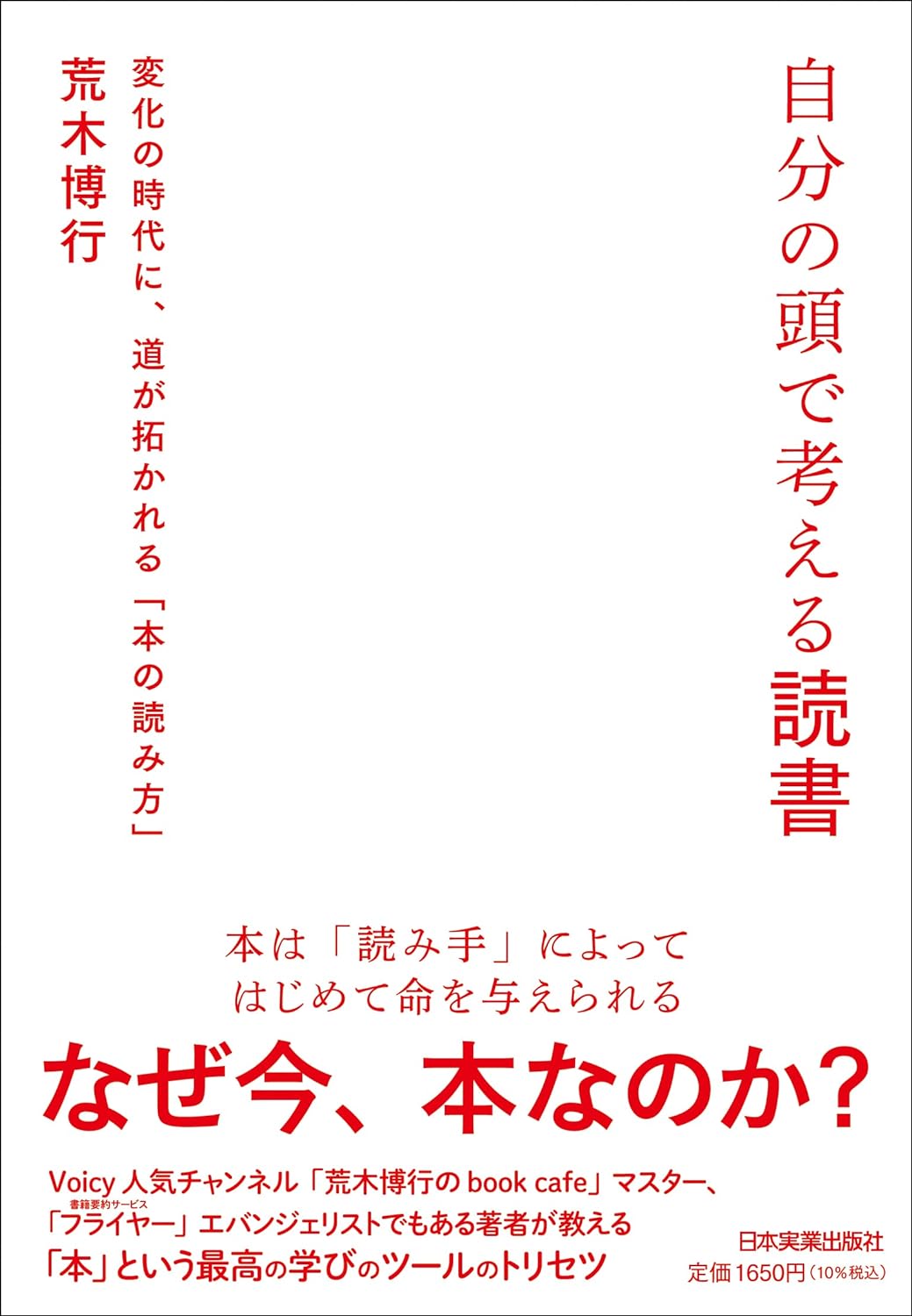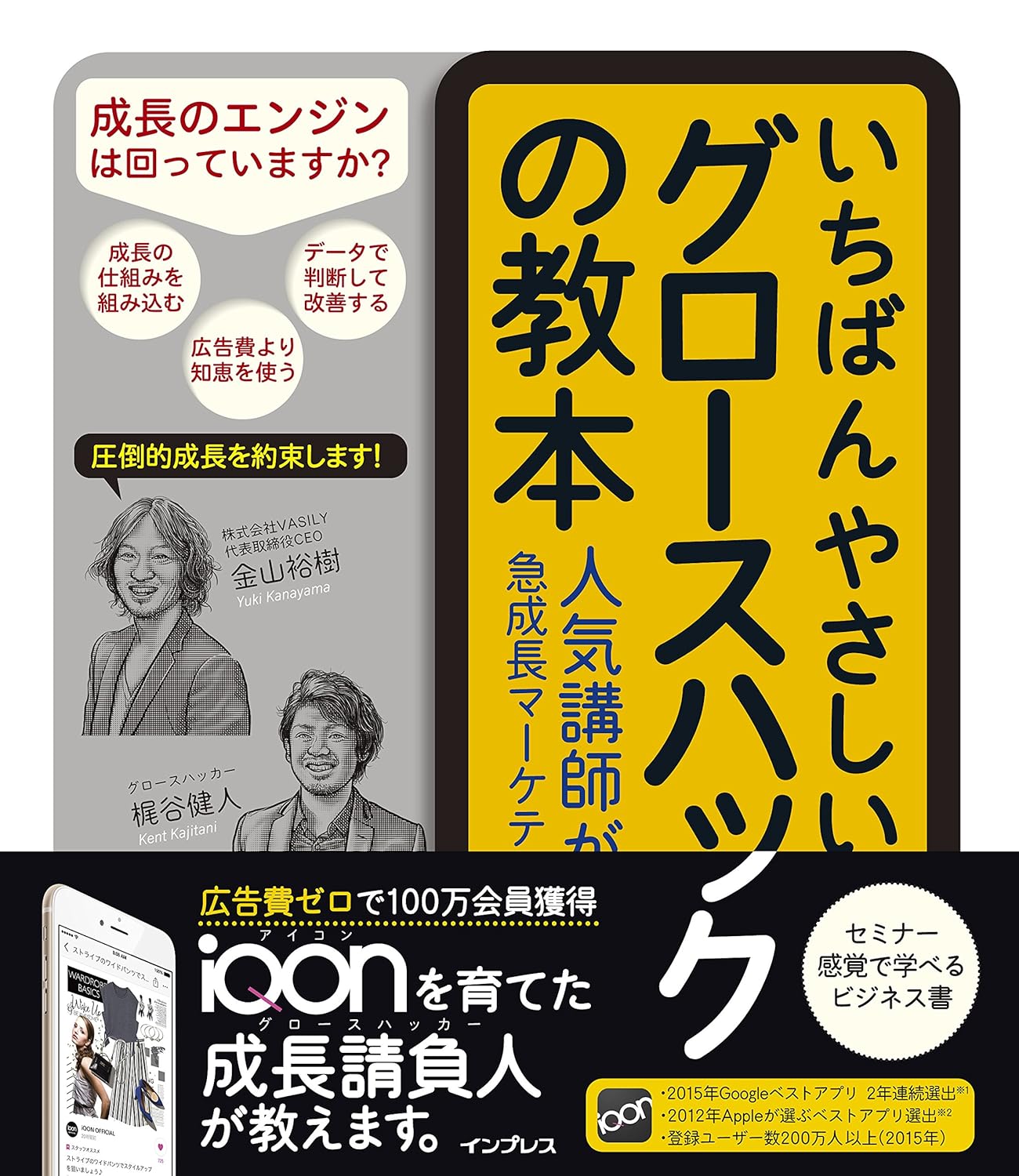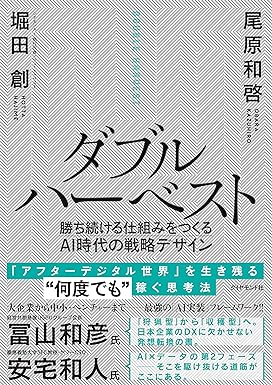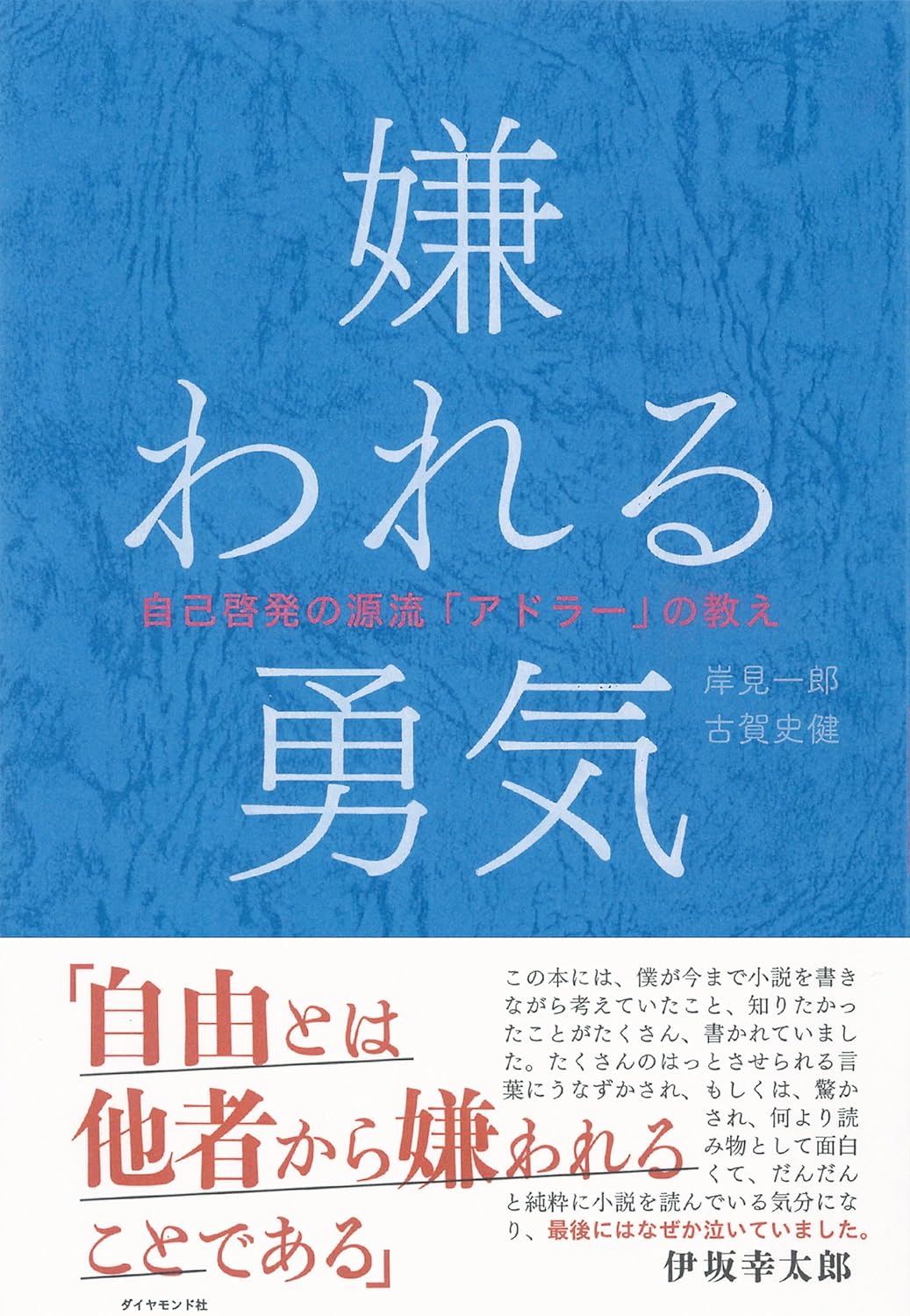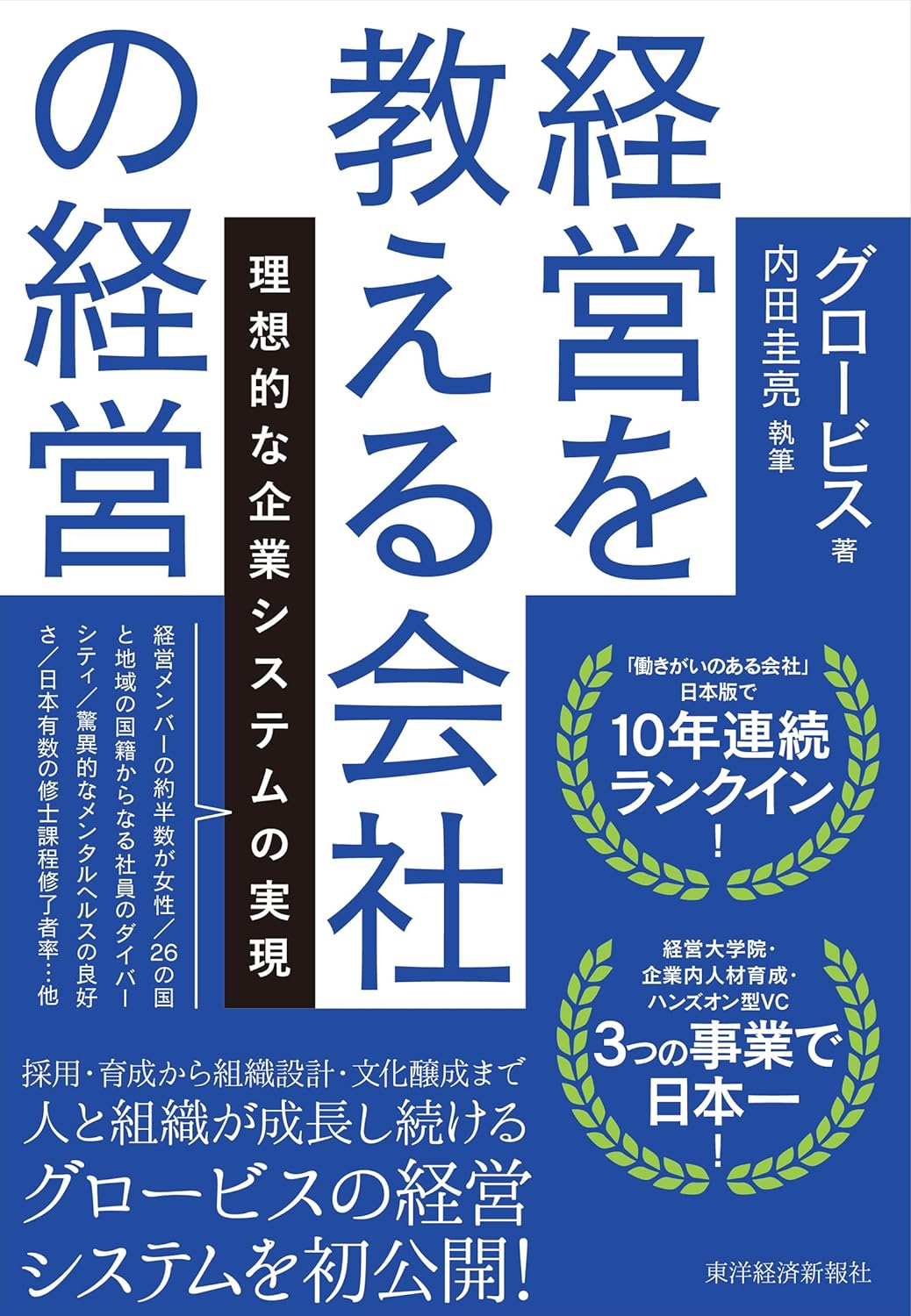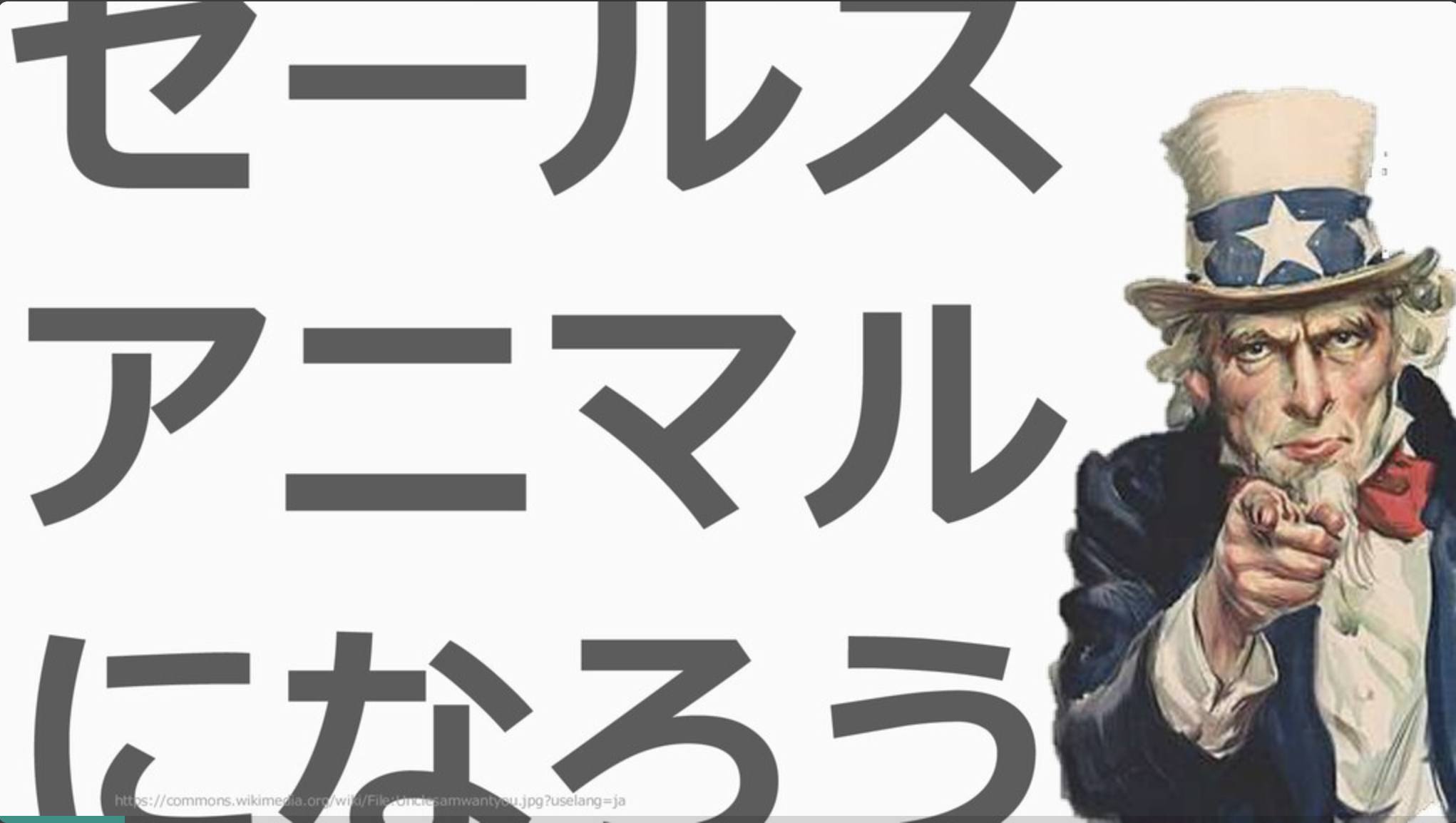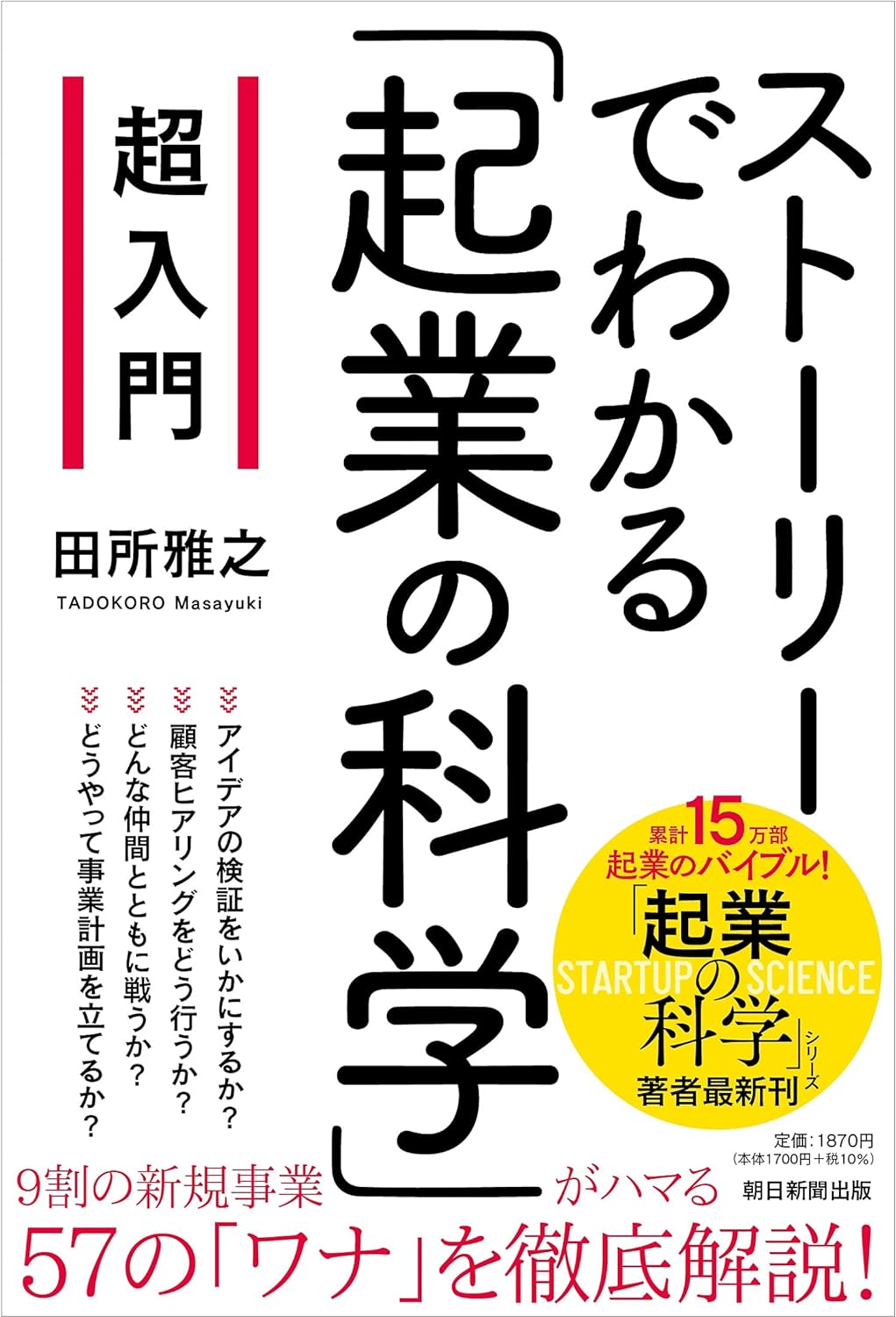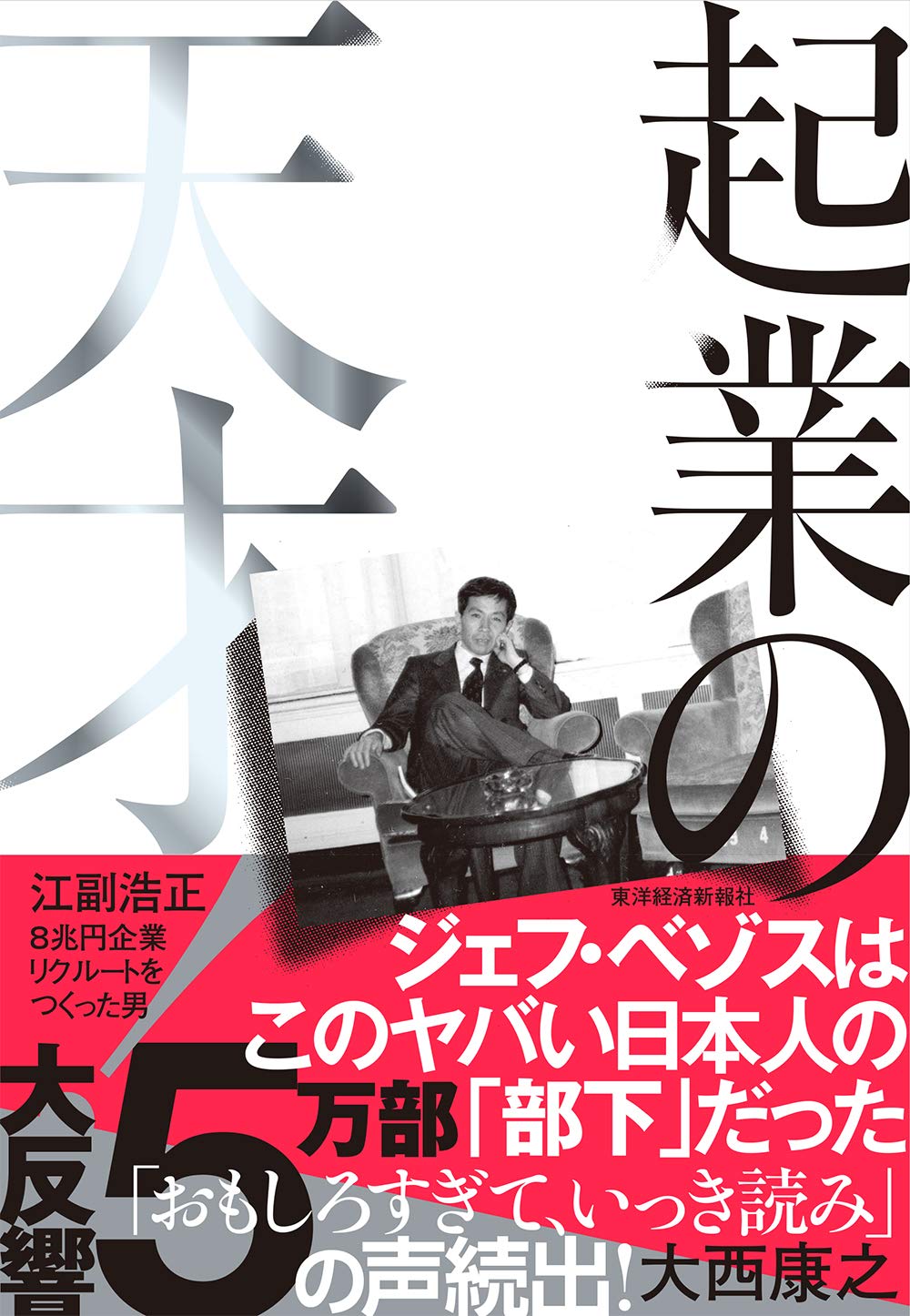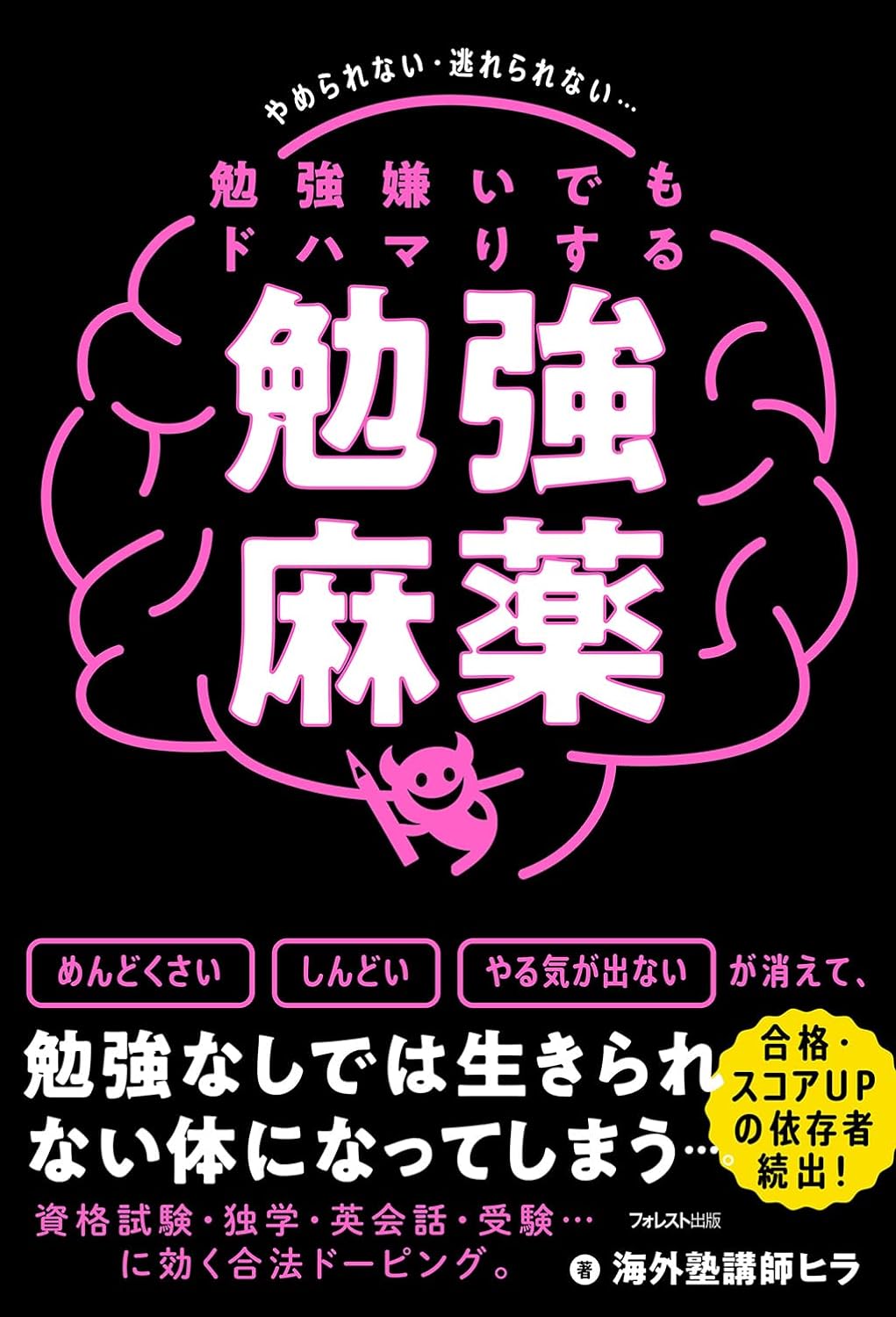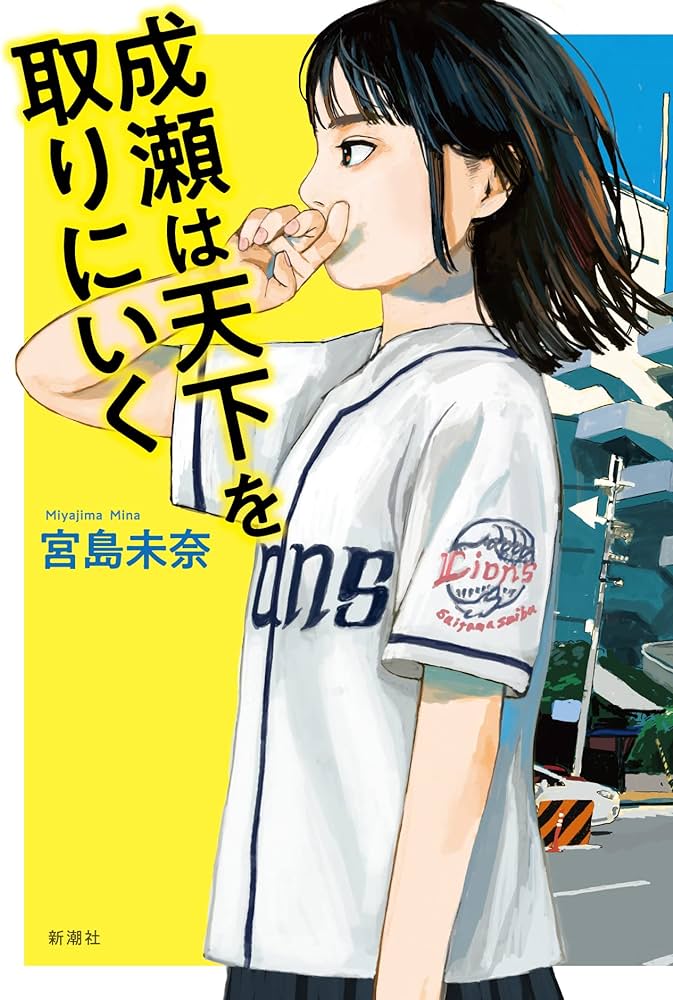■読む前に、この本に期待していたことは?
◎読もうと思ったきっかけ
いまの会社のMTGが無駄な部分が多く、それを変えたいと考えておりちょうど目に止まったので読もうと思った。具体的にはアジェンダなどがなく、オーナーが不明確なママはじまることが多く、とりあえず参加者にいっぱい入れる。みたいなことが多いです。
◎本から得たいこと
会社でMTGを行う際に、いくつかの要素を盛り込めるものを探したい。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「具体的な手法まで書かれており、一部だけでも真似できそうなエッセンスがある書籍」
◎感想・得たこと
・会議は「情報伝達会議」「意思決定会議」「アイデア出し会議」「進捗管理会議」の4つに大別される
・「情報伝達会議」は、基本的になくし、「意思決定会議」「アイデア出し会議」を経て決まったものについて、「進捗管理会議」を日々行っていく
・「意思決定会議」では、1枚or6枚のワードにまとめるという2種類に絞ることにより、情報を見やすくする。またパワポではなく、ワードにすることにより参加していない人も理解できるものとする。
→自社で急にこれは難しいと思うので、まずは文字サイズは変更しないなどの縛りくらいをいれていこうと思いました。
・Amazonのリーダーシップ理念(OLP)は12個あり、Amazon社に属していなくても一般的な企業の中で働くにあたっても学びになることが多い
・有名なプレスリリース駆動によって顧客目線で書くことができる
時間に対する意識と、工数に対する成果の意識がとても強い企業だということがよくわかった。
当社もかなり近いやり方をしているなと思いましたが、企業規模が全く違うので、
これをこの規模で全社でやっていると思ったら本当に素晴らし仕組み、、
それが浸透するためにOLPがあり、常にOLPに立ち返るカルチャーが存在していることが他社がマネできない強みだと感じた。
ルールというよりは意識、というのが自社でも活かせるポイントなのではと思いました。
Amazonの会議にもともと興味があったわけではありませんでしたが、日々のビジネスシーンでの会議には山程課題を感じております。印象的だったのは、1on1の件、ナラティブな文章で伝えること、いわゆる資料ではない、あとは会議の空気づくりですがこれはなかなか簡単ではないな、とも。会議の時間をカウントすると朝から毎日どっと疲れがでます(笑)
少し前に読んでいましたが、今回の読書会をきっかけにもう一度読み直しました。
最初一番印象的というか衝撃だったのは「ジョブ」という考え方で、それ以外自分の仕事(B2B)でもこの考え方を意識するようにしております。他にも「埋め合わせの行動」や「KPI(能動的なデータと受動的なデータ)」など自分のこれまでの会社に当てはまるケースがあり、またこの著者の「イノベーションのジレンマ」に通づるところがありそうだなと今回改めて感じました。 自分がB2Bの仕事をしているので例のミルクシェーキのような顧客のジョブを片付ける購買行動とは当てはまらないなとおもっていましたが、今回改めて読んで、本質的には近いものがあるなと感じました。
・ある特定の状況で人が成し遂げたい進歩を“ジョブ”と呼ぶ
・消費とは“ジョブ”を片づけようとして、特定の製品やサービスを“雇う”ことである
・人は置かれた状況によって何を“雇う”か左右される
・“ジョブ”には機能的な側面だけでなく、感情的、社会的側面がある
ニーズとジョブは圧倒的に違うというのが、実務で行かせる最大のポイントでした。
ニーズは、要求であり、何かを解決するような要素は含まれていれどすべてではないということを知ると、
真に解決しないといけないイシューは、ジョブであると置き換えられることができ、それを置き換えることができれば
それがまさに真の課題解決(=価値のある仕事)なのであると知った。
読むのは2回目半ぐらいでした。当時はカスタマージャニーなどの知識もない状態で読んでいたのでミルクシェーキの本!との認識でした。今回はみなさんがどうよんだのか?お伺いができれば嬉しいです!
ビジョナリーカンパニー1を○年ぶりに読んだことをきっかけに、2も読みました。GoodからGreatなカンパニーになった共通点の本ともいえるが、そもそもGreat(実績から厳選された11社)なカンパニーの共通点、はずみ車の法則、ハリネズミの概念、第5水準、何をするかよりも誰とするか、などなど個人的にはピンとくるものとこないものが混じっていたと感じる。1との共通点という意味では、これらの共通点が会社の仕組み・システムとして浸透・文化となることかとおもうため、そんな簡単な話では無いものの、改めて会社組織とは?を考えさせられた。
前回のビジョナリーカンパニー(無印)の会には聞き専での参加となってしまいましたが、その日の議論があまりに熱かったこと、及び一般的にはサラリーマンには②の方が評価が高いという話を伺い、今回手に取りました。
読後感としては自分にとっては②よりも無印の方がワクワクさせられたという印象でした。このあたりの要因について、内容にも触れながらコミュニケーションできればと考えております。
小さいながら企業経営をしています。コロナで自粛休業を余儀なくされた不安しかない2020/5月にビジョナリーカンパニーに本屋で出会い、一気読みしました。
バスがどこに行くのか(戦略論やビジョン以上に)バスに誰を乗せるかが大事、という総括の部分にとても感じ入る思いだったのを強く覚えていますし、その後の自社の人材判断にも参考にしています。
ニュースをみてボケっとしている間に私たちの生活は外部環境によって激変にさらされている。なんとなくを明瞭に、そう考えて読書会に参加しました。
そもそも島国の日本が島の中で完結できていたといった立ち位置からスタートして、興味のなかった世界史にまで興味を持つきっかけになりそうな内容だと思います。
いつか学びたいと思いつつもなかなか踏み込めなかった地政学について、簡単なインプットに適した書籍だと思い、手に取りました。普段報道される情報は表面的で一側面でしかなく、その裏には各国の打算等があることを再認識しました。
・ランドパワーとシーパワーの対比が非常にわかりやすかった。
・中東やイスラエル・パレスチナの事情が歴史を踏まえてわかりやすい説明があった。
・石油依存が高いゆえに起きている問題にも見えた。
業種別の導入事例集がまとまっているのが、参考になりました。
3章までの前提の生成AIの歴史や状況については、元々チェックしていたこともあり、全体として大きな発見はなかったと感じました。
導入事例から感じたことは、生成AIで何を解決したいかという解像度の高い業務課題があるかいうトップダウンから視点と、生成AIが出るまでシステムで実現が難しかった非構造データを扱えるというボトムアップの視点が、それぞれ大事なのではないかと思います。
産業がどう変化してきたのか、これからどう変化していくのか、そこにコンピューティングや情報処理、AIがどんな影響を及ぼすのかが書かれており、いまどんな位置にいるのかが理解できた気がする。
各業界ごとの影響度合いなども書かれており、自身の業務にどう活用しようかや、やりたいことをどんなふうに活用してアウトプットしようかといったことを考えるきっかけになった。
ただ脅威と感じるのみならず(正しくリスクを把握する)、どう付き合っていくのか、どう活用していけるのかを考えられる内容だった。
■読む前に、この本に期待していたことは?
◆読もうと思ったきっかけ
IT業界にいてて、あまり生成AI使ってこなかったので徐々に触っていこうとしていた中で、生成AI本はプロンプトエンジニアリングのことが書かれた本が多く、技術とか今後について書かれた本がないなーと感じていた中で本書を見つけたため読むことに。
◆本から得たいこと
関わっているサービスづくりに生成AIを活用するために、技術要素の理解・今後の活用についてのアイデア創出につながるための基礎知識を入れるため
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「生成AIについて、技術的理解とビジネス観点の両方を知れる本」
◎感想・得たこと
まず、シンプルな感想としては生成AI関連の本はプロンプト・エンジニアリングの本が多く仕組みをちゃんとしれないなかでこの本は基礎からしれてよかった。
・プログラミングや、Excelマクロなどはサクッと作れるので少しプログラミングが読める人には生成AIが使えそう
・ハルシネーションは気を付けてプロンプト・エンジニアリングしないといけないなと思いました。
・生成AIのカスタマイズは、RAGとファインチューニングがありRAGのほうが比較的取り組みやすい
・「壁打ち」という言葉が、この本でよく出てきており、生成AIは答えを求めようというときではなく、話を聞いてもらいながら答えを見つけていくというのがちょうどいいのかなと思いました。
・生成AIに興味があり歴史、得意・不得意が学べてよかったです。
・cahtGPT以外にも知らないアプリがありまずは触ってみようと思いました。
・もう少し詳しいHOW TOがあってもよかったと思いました。
■読む前に、この本に期待していたことは?
生成AIを基礎から理解することにより、深い部分での理解を通じてtomogakuと会社員側でのサービスに取り組み事を考え始められるきっかけづくりにしたい。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「生成AIの技術的基礎を学べつつ、主にはプロダクトマネジメントの考え方を学べる本」
◎感想・得たこと
・生成AIなどの手段は知っていく必要はあるが、結局のところ、どういう人が(だれが?)・どういうシチュエーションで(その人の状態は?)・人は何に困ってて(Pain)を知ることがプロダクトづくり/プロダクトマネジメントに必要であることが最も重要である。
・人と技術の交差点をつなぐことがプロダクトマネジメントに重要である。
・これまでのプロダクトマネジメントとの違いでいうと、倫理観というのが重要な要素であることは気づきだった。
PMに遠い私の立場では多少難解に感じた本でした。半分読み終えた部分からプロダクトマネジメント中心の話になり、すこしづつ引き寄せができるようになった程度の読み取り。 最終的な結論としてはAIは人には成り代わらず、必ず人の手を介するという方向になったのは、AI関係の書籍ではよくある形だとも感じる。。。
せっかく読書会の機会を設けて頂いたのに、お恥ずかしながら読書会までに1章しか読めずディスカッションの機会を活かせない自分を深く反省しています。
ただ、冒頭に書かれている賛辞を見るだけでも、この本が素晴らしいのだろうことが伝わりましたので、今日からしっかり読み進めて行きます。時代のゲームチェンジャーである生成AIについてはしっかり理解を遅れずについていきたいと思っています!
・タイトルは難しそうで手を出しづらい印象だったが、chatgptを始め生成AIの重要性がわかりやすく書いてありためになった。
・いいプロダクトから作るべきと先入観があったが顧客ニースを抑える、ニッチなところでも顧客を満足させるプロダクトを作るべきと
感銘を受けた。
ビジョナリーカンパニーを読むのは10年以上ぶりです。 ビジョンが大事というぐらいでぼんやりとした理解だったのですが、今回改めて読み直してみると、昔読んだ時に気づけなかった話がとても身近に解像度高く感じたことと、これらの会社に共通する話「時計をつくる」とか「BHAG」について著者がいわんとしていることが別の角度で理解できたのがとても驚きでもありました!また社長が変わっても代々受け継がれる会社文化・理念の大切さと難しさ、私のこれまで所属した会社の例にもあてはまることもありました。読み直しの価値がスゴかった!
■読む前に、この本に期待していたことは?
自身で作っているサービス(ひいては会社)を成長させていくにあたり偉大な企業の成功法則を知りたかったから。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「(個人的には)会社を作ろう/作っている人が読むと自分がどうすべきか?どう目指すべきか?を考えさせられる本」
◎感想・得たこと
・Goodな会社から偉大な会社に進化した会社の共通点を学べる本
・「or」ではなく「And」思考。どちらも取りに行く
・失敗→学びを高速で回すことが重要<回復力> →ダーウィンの進化論が繋がってる。
・偶然をうまく見つけて、それを成長させる力が必要
5年くらい前に読みました。
起業してからコロナに突入して壁にぶつかって五里霧中で悶々としているときに読んで感動しました。
崩れた12の神話では、偉大なるリーダーやアイデアがなくてもGreatになっているというデータ事例が僕のような凡人起業家にはとても救いになりました。
なによりも、この手の過去の成功事例分析本では珍しいと思うのですが、
GreatとBadやOrdinaryを比較するのではなく、GreatとGoodを比較するというところがとても感じ入りました。
実際の事例に溢れ、かつ、単にデータを並べているだけではなく分析の深堀りがストーリーになっていて読みやすく分かりやすく実践にしやすく感じました。
繰り返し読んでいます。
■読む前に、この本に期待していたことは?
前回「ユニクロ」という本で読書会をし、おもしろかったので引き続きでこの本を読んでみようと思いました。
https://amzn.to/3ySkPbk
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「(前回の本と違い)柳井さん本人の視点で描かれており経営者の本音が垣間見える本」
◎感想・得たこと
企業名が徐々に形作られていったりなど、割と初期の頃の話が起業・スタートアップという感じで個人的に面白かった。
決算書は経営者の成績表とおっしゃっており、初期はそれを毎月月末に自分で作っていたとのことであり、サービスを作っている自分としては反省しました。
また、柳井さんはたくさんの事業や組織の失敗をしており、そこから学びや次に活かしているあたりに凄みを感じました。
■読む前に、この本に期待していたことは?
Mobility業界に転職したので、MaaSの基礎を知りたく 平たく広範囲に書書かれている本からを探しておりました。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「MaaSの基礎を学べ、今後のインプット効率アップに繋げられる一冊」
◎感想・得たこと
基礎から書かれており、かつ海外の事例の列挙だけにとどまらず日本の交通事業や政策の話まで丁寧に書かれておりわかりやすかった。
・MaaSの思想は、「環境に優しく自分でクルマを運転できなくても、困らない暮らしと社会」
・MaaS先進国フィンランドでは、Whimというサービスが月額6万円で全てを乗り放題としている。
・移動サービスを利用している人の多くは、「移動が目的ではなく【何かを用を足すために移動手段を使っている】」
・フィンランドのMaaSレベルを日本にそのまま当てはめるのではなく、日本には日本の交通事情があるので、国交省が出している日本版MaaS(複数の地方MaaSをそれぞれつなぐ)を理解するのがおすすめ
・スポーツを小さい頃から見たりやったりして疑問に思ってきたことがクリアになって良かった。
・損失回避バイアス、フレーミング効果、概数効果、同調効果、サンクコストはビジネス、私生活にも有益そう。自分の癖を見直すいいきっかけになりそう。
・人を巻き込む時にサクラを作る、ちょうどいい目標設定などテクニックとして使えそう。
・一流の審判でもその場の雰囲気に影響を受けることがあるのは驚きだった。
・マラソンの記録については、自分自身も走るので理解できた。(思った通りに走れるかどうかは別)
・スポーツの戦略が時代によって変わることがあるのは面白い。
今後の生きていく上でAIを上手く活用できる人とそうでない人で大きく差が出来てしまう。「旧人類と新人類」という具合にだ。しかしAIはあくまで手段であって、課題解決においてAIをいれる意義と意味があって初めて活用するものである。またAIが得意なのは、「確率論的に確からしい答えを生成すること」と「バリエーションを大量に生成すること」であり最終的な判断はやはり人間がする必要がある事を自覚する必要です。
また、AIについてはプロンプトが大事でであり、立場や条件、再度の練り直し等が必要でそういいたスキルは必要である
一言で生成AIといっても数多くのサービスがあることに驚かされました。生成AIの概要や各サービスの理解促進のため、今まで以上にまずは触ってみることを意識したいと思います。併せて本書でも触れられていましたが、その人のプロンプト力がAI活用の鍵となる一方で、自身の力不足を痛感しましたので、どういう目的で利用するのか、どんなアウトプットが必要なのかを言語化する能力も伸ばしたいと思います。
まだ読めていないのですが、生成AIに遅れずについていかないとここ1-2年で勝ち組負け組が決まってしまうのではないかとの危機感のもとこの本を手に取っています。その感覚と、実際的な使い方などを社員や組織にうまく浸透していきたいと思っていましたので、この本のタイトルにとても惹かれています。
モチベーション
* 外部環境として生成AIがある前提で、プロダクトの何をコントロールしないといけないかが知れればと思っていた。
* AIを使って少人数でプロダクト開発できる世の中になるのかなと思ったので、事例などを知りたいと思った
結果
* AIをプロダクト開発に組み込むという内容が多く記載されていた。
* 外部環境としてのAIに関する言及はあまりないように感じた
- 「儲け方が根本から変わる」という部分に関する言及はあまりなかったようにも感じた。
ディスカッションしてみたい
* 生成AIでどのような世界になり、プロダクトの競争優位を築くにはどのようにするべきだと思うか
AIに限らないプロダクトマネジメントのノウハウに、生成AIならではのノウハウを乗せているため、1度読むだけでは咀嚼しきれないくらい充実した内容でした。
グローバルプロダクトの実例も参考にしながら、プロダクトに生成AIをどのように組み込んでいくかを様々な切り口で記載されているだけでなく、AIを活用してプロダクト開発プロセスをどう高度化していくか、まで紹介されていました。
特に印象深かったことが、生成AIならではの、倫理感についても、プロダクト開発時には意識しないといけないことでした。
生成AI時代における人材像も最後に記載されているので、是非、自分のキャリアの糧にしていきたいと思いました。
「しなやかに生きる」というのが、「環境に適応する」「自分が変わる」など、さまざまな要素があって大切なことに立ち返ることができたという感覚になりました。
「そもそも、環境に適応しないといけないのか?」「そもそも、環境変化を受け入れないといけないのか?」「やらねばサイクル」→「やりたいサイクル」にするにはどうすればよいのか、といったあたりまえのことをじっくりと考えることができました。
創発的な時代においての組織システム、目標設定のやり方が今までとは大きく異なってくることがわかりました。特に各論(U理論、OODA、シナリオプランニングなど)は少し学んだことがありましたが、久しぶりに触れたこと、そして著者の流れの中で使い方を学べたことは良かったです。一方、実際にアウトプットしないとわかりにくい、情報量が多くて消化できていないとも思いました。
📍感想
よくある理想を語るだけの本ではなく、それを現実に落とし込むための思考のフレームワークやワークショップの具体的なイメージが書かれていることで、リアルな現場で使いやすく素敵な本だと思った
📍気付き
・Visionはあくまでも"現在のための未来"であるという考え方へのシフト
・チーミングとタスクアセスメントやビジョンクローバーモデルなどの相互の繋がり
📍これから考えていくこと
これらを実行していくためのKEY PERSONの巻き込み。仲間をどう作るか。
外部環境の説明から始まり、ゴールセッティング手法の限界に触れたうえでビジョンプロセシングの紹介に入る流れが分かりやすかったです。所々に調査結果や理論の説明を入れつつ、具体的な実践方法も詳しく記載されており読みごたえがあります。
ゴールを設定しその到達を目指す手法ではなく、不確実な中で未来の捉え方を変え、今この時の行動・プロセスに注力する、という著者の考えに個人的に共感できました
全体的には、難しいこと言ってないと思いますが、実務におとしこむとき、どうするのか見えませんでした。
一人で読むより、みんなで読んだほうが気づきが多そうな書籍です。
ビジョンの概念を著者が再解釈して、解説してくれている
深く解説してくれているためか、難解だし高尚であると感じた
実践に繋げるためのは相当難しいのではと思う
著者のような優れたコンサルタントがいないと普通の組織では理解、浸透が厳しいのでは?
久々にボリュームのある本だった。本気で読みました!
時代が変わっていることに気づく必要があり、PDCAでは通用しないステージになっていることを認識。
難しい時代だからこそ人と組織の内面を考えたり、本当に大事なことを心から願う声として共有したりやってみることはとっても大事と思った。
本を読む前にSOUNDメソッドを通じたチームビルディングを自社で実践していたため、腹落ちしやすかった!
VUCA時代とよく言われるものの、本書が示しているようにVUCAワールドと呼ばれる現代はいったいどういう時代なのかをクネヴィンフレームワークを用いて解説されており、その整理と考え方だけでも学びになった。その状況の中で本当に大切なこととして「心の羅針盤」「本質的な課題」が挙げられており、パラダイムシフトへと繋がる流れは非常に参考になった。
何が起こるかわからないこの世の中において、いかにしなやかに自分や組織を変えていくか、ということのヒントをもらえたような気がします。
この本に記載されている事象が、今まさに自社で直面している問題がたくさんあったので、非常に”当事者意識”をもって読むことができました。
■読む前に、この本に期待していたことは?
新しい業界に転職し、PdM(プロダクトマネージャー)をする中で、業界知識がなくかつPdMは様々な職種の方々の知見を伺いプロダクトとして最適解を見つけて行くことが役割となるため、ぴったりな本だと思いつつも、「でも聞いてばっかりできるのかな?時間の制約もある中で」という疑問がありこの本からヒントを得ようと思いました。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「聴くスキルに加え、心持ちも重要でありそこが最も習得が難しいことを理解させてくれる本」
◎感想・得たこと
・聴くと伝えるはセットである
・「肯定的意図で全てをまずは受け止める」ことにより相手の考えを理解することができ、その上で建設的な会話をその後できるようになる。
ここは、ある意味プーチンにはプーチンの正義があるみたいな捉え方を自分ですることによってしっくり来ました。
肯定的意図という考え方が新しく学びになった点。
その発言・その行動の背後にあるものを判断せずにくみ取る姿勢がまずは大事。
どうしても判断しながら途中から聞かなくなってしまう。
相手の良いところ。特にたまにやる良いところに気づけるか。
人の粗は気づくけど良いところは気づきにくい。
Tipsも役に立ちそう。
肯定で伝える。なぜではなく何ができく。
質問の引き出しも会話が苦手な私にはありがたかった。
とても読みやすく勉強になりました。
コミュニケーションはサイエンスだ、きちんとした手順に則れば誰でも上手くやれる
という部分には勇気をもらいました。
抽象的な表現だけでなく、2軸でのフレームワークを使っての説明がわかりやすく、実践しやすいと感動しました。
■読む前に、この本に期待していたことは?
ZARAを抜いてアパレルで時価総額世界1位になったのは前から知っており、日本人として嬉しいなと思っていたのもありたまたま目に止まり読んでみようと思いました。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「全然うまくいってない(ことが多い)中で、ピンチをチャンスに変えたり紆余曲折を生々しく知れる本」
◎感想・得たこと
・人たらしだなーと感じました。(食品部門の立ち上げで20何億円の赤字を出した部下をやめさせずに、こんなけ勉強したんだからGUの副社長として頑張ってよといったところとかとか)
・ピンチをチャンスに変えるのがうまいと感じました。
・ある意味ほぼベンチャー起業家から、世界的大企業の社長として1代で成長できたのはなぜなんだろう?と感じた中で、やはり本を読むことの重要性があるのかなと書籍の中から感じました。
・現地現物、現場感がやはり重要なんだろうと感じました。一方でTRYする打ち上げるというのもどちらも兼ね備えておくことも重要だなとも思いました。
◎気になったこと
・父親(柳井等)が、経営者じゃなかったとしたら柳井さんはユニクロを創業できていたのか?ここまでの大きさにできていたのか?を考えてみたいなと思いました。
■読む前に、この本に期待していたことは?
会社員・副業・起業に現在取り組んでおり、全てを自分だけの力でガリガリは時間的にできないですし、会社員は特に自分だけよりもチームの力を借りるほうがむしろ良いと考え、でもこれまで割と数人や自分一人で突き進む傾向にだったため、会社員・副業において、他者の力をいかに借りれるのか?を具体的な手法を知りたく読もうと思いました。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「短期思考の成果ではなく長期思考のマインドを持って、任せる相手が"成長すること"を前提に遠回りしてでも長期的な果実を取りに行く」
◎感想・得たこと
・「丸投げ」でいいんだというのがまずいちばんの驚きでした。その中で丸投げにもコツがあることを学べたのが大きかったです。
・タスクを依頼するタイミングでなく、日頃からメンバーのタイプや好み、モチベーションが上がるものを把握しておくことが重要。(事前に把握しておくことによってタスク発生時に素早く、適切に渡せる)
・ピラミッドの話ではないが、なんのためにそのレンガを積んでいるか?を意識して上位の目標を理解してもらうことが大切。
・断る余白を残しておくことも重要。
◎気になったこと
・成長というのが大前提にあるように書かれているように見えたので、成長を見込まない場合どう捉えたらいいのか?(同じようにスピードを優先したい場合も)がきになる。
聴くことだけでなく、フィードバックの返し方や着目点などを関係性に応じて柔軟に変えていくことを説いた点は面白かった。
聴くにあたって、在り方の重要性を改めて実感しました。
肯定的意図、非言語の視覚・聴覚情報からまず始めたいと思いました。
また、PIマトリクスからどういうときに聴くべきなのかも印象的でした。
このような読書会を開催いただけたおがけで、楽しく読むことができました。
ありがとうございました。
普段から他人の話を聴くよりも自分の意見を話すことが自然と前に来てしまっていて、コミュニケーション上の課題意識はありました。
特に会社でのメンバーとのキャリア面談のようなシーンで悩んでいる真っ最中だったので、「聴く」や「伝える」などのコミュニケーションを分解品しながら自分の言動をふりかえることのきっかけが出来ました。結局のところ、どうすればよいのかのこたえが見つかったわけではないものの、相手との会話・話題の状態を客観視(過去・未来とか、ポジネガとか)するフレームワークは今後意識してみたいとおもいました。
相手の言動の背景には肯定的意図があると信じて聴く。聴くの姿勢としてこれが全てだよなーと納得しかありませんでした。同時に話をきくときに無意識的にその話について自分がジャッジメントをしているから、相手の話を肯定、否定などを考えてしまう自分の思考の癖にも気づけました。とはいえ、何度も何度も見直さないとすぐに戻ってしまうのですぐに手に取れる範囲に置いておく本になっております。激推しです
■読む前に、この本に期待していたことは?
生成AIをもともと触ったりはしていたのですが、最近少し遠ざかっていたのですが、先日僕の大好きApple社がAI(Apple Intelligence)を発表しその流れから生成AIをビジネスで使われている方と話すことがあり熱が再燃し本を改めて読みました。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「生成AIをどういう時に使えるか?というTipsがたくさん書かれた本」かなと思いました。
◎感想・得たこと
ペルソナ、ユーザインタビューあたりが自身のプロダクトマネージャーという職種的に最も使えそうで、実際のユーザへの壁打ち前に使えるなと思いました。
とても実践的なChatGPTの活用法をまとめた一冊。ChatGPTを使いこなせれば、活用できない同僚と比べて、圧倒的な仕事のスピードと質を手に入れられる。メール作成や文書添削といった初歩的な使い方から始まり、企画・提案や、情報整理、マーケティング・PR、プレゼンなどビジネス全般にわたって活用できない仕事がないぐらい利用範囲が広い。キャリアの相談にのってもらったり、褒めてもらったり、励ましてもらったり、愚痴を聞いてもらったりとまるで上司や友達のような存在になってきているのが驚き。
「AI仕事革命」は、AI(人工知能)が働き方や組織の在り方に与える影響をテーマにした書籍です。この本では、AIがどのようにして従来の仕事のあり方を変え、新たな価値を生み出すのかが議論されています。
AIの導入により、ルーチンで反復的な仕事は自動化され、人間は創造性や戦略的な思考に集中できるようになるという考え方があります。また、AIはデータを活用し、意思決定の質を向上させることができます。
一方で、AIの導入によって生じる倫理的な問題や社会的な影響、さらには職業の多様性や雇用の変化にも警鐘を鳴らしています。AIの活用は労働市場全体に大きな影響を及ぼす可能性があり、教育や政策の再考が必要とされています。
要するに、「AI仕事革命」は、AIが人間の仕事に及ぼす多面的な影響を探り、その中でどのように個人や組織が適応していくべきかを考察しています。
これまで何冊か行動経済学の書籍を読みましたが、初めて見るお題や専門性の高い(詳しい)紹介がされていました。
ただ、説明が不足しており読みにくいと感じる部分もありました。
後半は身近な事例が多く、自身に引き寄せやすい内容でした。自身へのナッジに関するページでは、自身の行動変革に言及しており生活に落とし込みやすい構成になって良かったです。
行動経済学の本は、ビジネスで使える系が書かれた本と、自分の生活に応用できる身近なことが書かれた本の2種類があると思っていて、この本はビジネスで使える系のことが多く書かれた書籍だと思いました。
一番学びだったものは、システム1,2は動機(関与)と能力(知識)の変数が影響しているというのが学びでした。
とはいえ、行動経済学の本にありがち?な理論がたくさん羅列されている形だったので、覚えていく?みたいな形になりこれをどう活用するか?に少し悩みそうだなと感じたので辞書的に使うのがいいのかなと思いました。
伝統的経済学では単純化された個人や法人の行動について、現実的には非合理的な行動が多いという見地からの学問が行動経済学とのこと、とても実際的で分かりやすく勉強になりました。
マリッジブルーなどの現象について、数式での解明を試みる点などにはとても学びがありました。単に、人間ってこういう不合理な行動しますよね、という心理学的な研究に留まらず、数式に落とし込もうとするあたりに経済学としての価値があり、それが多数のノーベル賞受賞者につながっているゆえんと理解しました。
以前読んだ行動経済学が最強の学問...とアプローチが違ったので興味深かった。
一個一個の効果に対し図解がついているのでわかりやすい。
プロスペクト理論にて損得と確率の考え方が理解できたのでコミュニケーション(駆け引き)でも活用できそうと思った。
またナッジの作戦立ての部分も体系立てて書いてあり、今後の取り組みにも生かしたい。
数年前に実践行動経済学という本の読書会をしてから興味を持っていましたが何も実践できていなかったことに焦りました。
ケースが細かく分かれており興味がある理論だけでも読めるので読みやすかったです。
本自体がロジカルツリーに出来上がっているようで、だんだんと深度を取っていくスタイルであったと考えている。
結論では(深さが大事ってこともあるが)”課題を抽出”して”手足を動かせ”って問うている本だとも感じた。
+付録:解像度を上げる型一覧 があるので、、、、、いつでも読書会に参加できそうではある。見直すことができる本。
内容としては、ロジカル・クリティカルシンキングが4つの軸で再整理され、課題・解決策それぞれに対する取組についてわかりやすく解説されたものと認識。過去に取り組んだ某大学院での講義が思い出されたものの、久々に振り返ると忘れているものも多く、実践し続けることの大切さを再認識しました。
・タイムマネジメントではなく、セルフマネジメント(自己管理)をする。
・時間効率も大事だが、成果にフォーカスし優先順位をつける。
・何かにYesをいうと、なにかにNoと言っている。
このあたりが最も響いた部分でした。
これまで効率よくさばくという意識でやっていましたが、そもそもの優先順位を意識しているようで足りていなかったなという気付きがあり、この本を通して5つのポイントでやっていけばよいというのが明文化されていたのが良かったです。
ただ、石・砂利・砂・水を順番に入れていく話は理解できるし知っていた一方でどうしても、水や砂利を先にさばきたくなる性分はどうしたらいいのかという悩みもまだ抱えています。。
■5つのポイント
削る
自動化する
任せる
先延ばしにする
集中する
この本は、時間管理の重要性を深く理解させてくれる一冊でした。特に、日常生活にすぐに取り入れられる内容が多かったです。人生は短く、限られた時間を最大限に活用するために、自分にしかできない仕事に集中して取り組む姿勢を教えてくれました。この本を通じて、自己管理の大切さと効率的な時間の使い方について再認識し、今後の生活や仕事に役立てたいと思いました。
「明日やろうはばかろうではなかった」本当に今日やることは正しい事なのか?
今日出来るからやっているのであれば、一度考え直そう。
実はやった事より優先事項が高いことがある可能性がある。
また、やったことにより「予期せぬ変化コストを背負い込む」というリスクが発生する。
その場合、やり直すという事で余計に時間を消費してしまう
印象に残った学び。
・最も成功している人々は、忙しいとこぼすどころか、忙しいという言葉を口にすることすら「決して」ない。これは自分もちょくちょく口にしている言葉で、何も生み出さないことにエネルギーをロスしていたなと反省しました。
・自分の時間を使って何を行い、何を行わないかを決めれれるだけの力があなたにはある。このフレーズもすごく力がもらえるので、肝に銘じて決断して行きます。意志が弱いから仕組みかですね。
開発Prj.が大きすぎるが故に人がうまく動くにはどうすればよいかヒントが欲しくなり選択。
人はある条件下ではカチ、サーで動きやすくなる。
→行動経済学の合理性とも近いが一方で居ても立っても居られない感じで行動してしまう。
一個目の返報性は特に身近でよく起こっていることだと思うし、お返ししないと気持ちが落ち着かないのはシンプルで分かりやすいなと思った。
あと怖いのはコミットメント、上位と面談するとつい見栄を張って?丸め込まれて?発言してしまい縛られているように思う。
人を動かして成果を出すためにしたたかに行動する上の基本的な原理をしっておくべきだと思いました。
・実践的な内容で部分的にでも活用できそう。
・世の中のセールスなどで自分が使われていることも意識するといいかも。
・自分は好意や権威を使おうすることが多いがTPOに合わせられていなかったかもと後悔。
自分自身が普段からよく考えて行動している内容が体系的にまとめられていてすごく納得できる良書と感じています。どんな良い戦略があっても動くのは所詮「ヒト」であるため、何らかの力(駆け引き)が発生して成立しているものと思います。これからAIが発達してくる世の中になったとしても、ここに書かれているような影響力はずっと残り続けるのだろうな、とも思いますね!
小売りの事業経営をしている立場なので、お客様の購買意欲や意思決定を自然と促せる技術に感動しました。
また、お客様に限らず、社内外の関係者に対しても、影響力を意識していくことで強いチーム力が作れると感じました。
この本に書かれている技術は、強引にさせるというものではなく、自然と自らしたくなるようになる技術ですので、顧客や関係者のコミットメントも高まり、皆がハッピーになれる魔法のノウハウだと感じます。しっかりと学んで行きたいと思います。
最近、導入コンサル部門側として、営業側や製品開発側との連携が多く、なかなかうまくいかないことが多かったので、ヒントおよび気づきがあった。 特に、正論だけでは人が動かない(逆に裏のネゴだけでも人は動かないことがある)ため、どうすればよいのか、と言う八並があったので、社内で企画を通すためのノウハウ(ロジックもさることながら、人を動かしたり、組織を動かしたりする)がとても参考になった。 人間心理、組織力学という言葉があるが、なかなかスキルとして定義し難い部分が、本当は大事。
役職なし、業務知識弱い、性格が不器用だからしょうがいないとあきらめていた部分がありましたが
仕事を進める上で逆に自分の弱点を知って関係者を適切に巻き込んでいく必要がある再認識することができました。
会社の不を減らすために弱者なりの撤退を含めた戦い方を明日から実践したいと思いました。
やることをやってダメなら環境を変えるのもありかなと。
現状を正確に把握して無謀な勝負をせずにしたたかに行動したくなりました。
最近のマーケティングの観点としてもモノ売りから事売りなっている事から人の欲求はモノより事(経験)に変わっている事がこの本を読んで腹落ちした。
経験に減価償却は無い。
経験にも福利が利く。若い時の経験はそれだけ福利が高くなる。したあがって能力が高い時に経験にたくさんのお金を使うのは理にかなっている。
また、自分は何をすれば幸せになるかを事前に棚卸しすると上記の経験がより豊かになる
今の自分にとって大事だと感じた部分は以下。
感想で終わらせずに実践していく。
・人生を最大限に生きることを重視し、資産をただ貯め込むのではなく、経験を最大化することが重要。
・金銭的価値を最大化するだけでなく、時間と健康を賢く使って一生を通じて充実感を得るべきである。
・人生の各ステージでの最適な支出パターンについて議論し、若い段階での体験投資に重きをおく。
自分の会社のビジネスである生命保険の存在意義と人生の意味など考えさせられる内容でした。
万が一の時のためにかける保険に入らず、今しかできない経験を優先した方が有意義だと思う一方
最悪のケースも考えないと困ることもあるので難しそうで、個人の価値観とライフイベントによる取捨選択が大事だと
思いました。
人生において、後ろに延ばせることと、実は思っているより延ばせない事があるよと具体例を踏まえて諭してくれるのがとても良い気づきになりました。人生において漠然としたお金の不安を抱え、何となく貯めていたモノを、ある程度具体的に年齢を定めてその時点でお金などの資産をZEROにする人生を考えたことがなかったので、それを考えるだけでもこの本に出会えた価値かなと思います
私としては、激推しな本になりますっ
以前読んだことがありこれをやりたいと思ったのですが結局実行できませんでした。自分のこれまでの経験や価値観が影響しているのかなと思います。私の祖父母は戦前生まれということもあり特に慎ましく生きてお金をためておくことは大切だという価値観の持ち主で自分の親も祖父母に比べれば使っていますが、そういうところがあったように思います。特に失われた30年の間はデフレということもありお金をためておいたことがいい方向に働いたと思いますが、インフレに転換している今、若いうちに経験しそしてそれを活かして生きていくことが結果的に収入を増やすことにつながり、経験もお金もどちらも増やし、その増やしたお金でさらに新たない経験につなげることができるように思いました。バケットプランを作り本当にやりたいことを人生で実現できるように考え行動していきたいと思います。
正直、5つの例えの表現が分かりづらく、内容が入ってきずらかった。
学術的な方がまとめられた著書ということもあり、ビジネスのリアリティに欠ける印象。
風呂敷を広げて無謀な計画を立てて疲弊して他責する傾向があったの5つの原則はとても参考になりました。
手中の鳥、許容可能な損出、レモネード、クレイジーキルト、飛行機のパイロットは仕事、趣味の麻雀にも活かして
押し引き、勝ち負け、周りとの協働など気を楽に持てそうです。
まず、創業云々でもなく比較的簡潔にわかりやすく読み切れる書物でした。
ゴール起点ではなく、わかりやすく言えば柔軟性を問われる本、頭が固くなってきた年頃で読むのは良いかもしれない。
■読む前に、この本に期待していたことは?
「なぜ、みんな本を読めないのか?」
「読書に関する歴史的な背景を知る」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「読書はあるい意味ノイズ。でもそのノイズをいれることによって成長や深みが出る。なので、もっと気楽に仕事も人生も、読書も半身で気楽にやろうよ!」
◎感想・得たこと
・なぜ本を読めないのか?ではなく、なぜ読まなくなったのか?がすごく理解できる本でした。
理由としては結局、昔の本の立ち位置(社会的に良い地位になりたい(立身出世)→エリート階層に追いつきたい→出世したい)がノイズになり、より効率的に仕事で必要なもの自己実現するだけの道具として今は活用されているので、それ以外のノイズ(近接領域、または現時点では遠い領域)が多いので好まれなくなる傾向がある。でも、実はそれが重要であったりして、偶発性を生んだり、ジョブズのconnecting the dotsじゃないですがどこかでつながるというのが読者に考えてあるとのこと。
・また、SNSづかれ、そして家庭と長時間労働の影響で本が読めなくなっている人が多いので、みんな半身で気楽に何事も取り組もうよ。そして本も半身でとのこと。
・また、本のメインテーマではないですが、半身の反対として全身コミットメントする場合、実はそこに集中するだけでいいので楽であるとのことや、全身コミットメントすると周りが負の影響を受けている可能性が高いというのは自身の家族や周りの友人などの大切な人との関係性について考えさせられるメッセージでした。
体系だって書かれているので理解しやすかった。
埋没コストはよく聞くが機会コストの意識は薄かった。もう少し行動するほうに振っていきたいと思った。
時間の認知はよくあるなと思った。特に遠い時間軸はあいまいになるし、計画も上位含めてハッピーストーリーになりがちで計画立てる意味が怪しいことがよくあると思った。
ナッジは行動経済学では一番有名な単語だと思うが、実際どうしかけるのかがわからず仕舞いだったが、プライミング効果やプロスペクト理論など手法名も併せて知れたので理解しやすかった。
特に伝え方で変わる部分のプロスペクト理論の方は自分が持っていきたい方向に話せているか意識しておくべきと思った。
■読む前に、この本に期待していたことは?
もともと行動経済学は興味がありマンガのような簡単なものは読んだことがありました。(ナッジ理論とかは知っている)ただ、一つ一つの手法がバラバラで知っているだけだなーとふんわりと思っていました。そんな中で、本書の目次を読んでいく中で、
「行動経済学を体系的に知り、今後の行動経済学の地図を学ぶときの地図になるようにする」
ということの必要性を感じ読むことにしました。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「行動経済学の全体像を知るための本」
◎感想・得たこと
・ビジネスでの活用以外に、自身の行動をうまくコントロールするためのものであったりと自身のためのものも多く書かれていた。
・「認知のクセ」が基本的に最もつよくあり、そのあと「状況」、「感情」とくる。
・ビジネス(対お客様)に活かせそうだなと感じたことはもちろん、日々の自身の仕事の進め方、仕事のモチベーションコントロールにも役立てられそうだなと感じました。あと家族に対しても..笑
・課題としては一旦頭にはなんとなく入ったけど、これをすんなり引き出せるようにするための訓練が必要だなとも感じました。
[行動経済学のフレームワーク]
・認知のクセ
・状況
・感情
普段から如何に非合理的に意思決定しているかがよく理解できる内容でした。
私自身が人と接するとき、「なぜ人がそのように行動するのか」と考える癖があったので、この本で書かれている内容は理解しやすかったです。また逆にうまくこの心理をうまく利用されて生かされているということも改めて実感した次第です。マーケティングは「人のこころをつかむこと」と学んだことがありますが、まさに人の深層心理を理解する(本当は理解できないのですが)ということが言語化されている良い本だなと感じました。
普段なんとなく感じている自分・人の行動が言語化されて整理されているので、それぞれの話が非常に馴染みがありました。
一方で網羅的であるため一つ一つの事例は淡泊だと感じました(読みやすいというメリットもあります)。自分自身の行動に落とし込むにあたっては、きちんと解釈が必要だと思います。
これまで様々な書籍を通して人・組織を動かす技術を学んできましたが、改めてその抜け漏れの確認のために本書を手に取ってみました。作者自身の経験を踏まえながら各項目の説明がなされており、具体感を伴って内容を理解することができたと感じています。
どこから読んでも、組織というモノに所属をしている人にとっては、新しい視点や組織構造のとらえ方ができるようになる具体例が本当にたくさん載っているので、学びが深いです。
そして、読みやすい。たぶん、「スキルセット」ごとにカテゴライズされている事で読み始める前に、読者に内容を受け取る前準備を促している事。
そして、読みやすい要因は具体例が今まで見た事ない切り口なのに、あるあるだから。と自分は読みやすさの要因を分析してみました。
この本の全体的なイメージとしては、影響力の武器をより身近なビジネスの日常に引き寄せつつ、なぜ、組織に所属する人はそのような動きをしてしまうのか?組織における原理原則が示されており、どう自分の想いを実現させるかにフォーカスされている感じです。
■読む前に、この本に期待していたことは?
①:「今の仕事が楽しく感じられていないので、この本から何かヒントを得たい。」
2:「今後取り組む別の仕事でも、ブルシット・ジョブにならないためにどうすればよいか?知りたい」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「ブルシット・ジョブが生まれる背景、その対策について社会全体としてのアクションが書かれている」本だと感じました。
個人的には、「自分の仕事を棚卸しせよ。その中でブルシット・ジョブはないか?」を考えさせられる書籍でした。
◎感想・得たこと
・19世紀のからの資本主義がブルシット・ジョブを生み出す要因を作っているという背景が理解できおもしろかった。(結局、こうなっている物事には過去からの歴史的背景によって、環境がそうさせてしまっていて、個人が悪いわけでなく社会全体がその方向に向かってしまっている。ということ。)
・以下のブルシット・ジョブの5種類をベースに自身の仕事を棚卸しするいいきっかけになりそうだと感じた。
[ブルシット・ジョブの種類]
・取り巻き:誰かに偉そうな気分を味わわせる仕事(ドアアテンダント、秘書など)
・脅し屋:雇用主のために相手を攻撃する仕事(企業弁護士、ロビイストなど)
・尻拭い:組織の中の「あってはならいないミス」を取り繕う仕事(不良コードを修正するエンジニアなど)
・書類穴埋め:組織が実際にやってないことを、やっていると主張する仕事(社内報、広報など)
・タスクマスター:他人に仕事を割り当てるだけの、ブルシット・ジョブを作り出す仕事(中間管理職)
■読む前に、この本に期待していたことは?
①:「今と自分の頃の教育の違いとは?」
②:「自分の経験からだけでなく、娘のためにどういった学習環境が良いか?を考える機会にする」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「教育がどう変わっていっているか?そして時代の風潮として遅い間違っているなどの批判ばかりせずに、変わっていることに期待を持つことを訴えかけている」ように感じました。
◎感想・得たこと
過去は教育の質が均一であることが完全正義であったものから、今は均一を意識しつつも先進的なものは支援していくとく体制になっているらしくよい傾向であると感じた。もう少し細かく言うと、均一のために出る杭を打ってたものを打たなくなったとのこと。
個人的には今後、出た杭にほかが追従できるような仕組みを企業側/親側としてなにか僕も貢献できたらいいなと思った。
これまでの「知識・技量」の習得でなく、今後は「考える力」「表現する力」、周囲との「協働(共同)する力」「問題を解決する能力」など、実社会において使える力にシフトしているとのことでありこの傾向は個人的にもいいと思う。
また本の中でもとはいえ、「知識・技量」の習得はベースとして重要とも書かれており、いかにこれをサクッとAI・DXのちからを使って効率よく習得しそのさきの学習につなげていくか?重要であるとも感じた。
一方で上記を許すということは、学校によりばらつきがどうしても起きるというも感じた。
自分の子供に対しては、やはり過去の自分の経験をそのままではなく、今の外部環境を理解し、
・学校の選択は重要であること
・効率的な学びと、非効率でもいいからじっくりとやるべきものを見極めて提供したいし、本人がそれを見極められるようにもなってほしい
と感じました。
■読む前に、この本に期待していたことは?
①:「思考のフレームワークを増やしたい」
②:「創造性に再現性をもたせられるのではないか?」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「自然・生命とリンクさせることにより、思考のフレームワークを定着化させられる」
◎感想・得たこと
何か一つのものについて分析、取り組みをするにあたりそれぞれの角度から考える際に役立てられそうに感じました。
一方で植物や動物の話が合間に多く、その分野について知識がないので正直その部分は読み進めるのに苦労しました。
あと、この本を批判している本がありおもしろそうだったので、そちらも読んでみたいと思います。
https://amzn.to/4azlWK6
日々の生活で事実を捉える視点がとても勉強になった。逆にこの視点を使うことで0→1ができるのかというと、現実ではそう簡単ではなさそうだ、ということにも気づくことができた。では創造のための源泉って何なんだろうか、と考えさせられた。
失敗や異端などネガティブだと思っていたことも見方を変えると進化の材料になりえるとポジティブな気持ちになれました。
忙しい、仲間が協力してくれない、リソースがないなどを言い訳にして変革をする作業を何一つしていないことに気づきました。
9つの変化の発想を使えばいつでもスタートできると思いました。
時空観学習についての学びの切り口に対する丁寧な説明がこれでもかというほど続くので学びの量がすごいです。飽きません。というか消化しきれません笑一生ものになると確信しております
自分にとっての哲学の本の様に、何度も噛み締めないと理解できないというような複雑さや難しさはなく、一つ一つの考え方が精緻に作りこまれているので繋がりが見える。それがこの本の特徴なのかなと思います。
だから、丁寧に丁寧に読み込んでいきたくなる。そんな魅力的な本なので、読むのにも時間が必要でした。また読み返します
・会社を安く買い、自分が価値を高め、高く売る。キモは、自分がいかにその会社の価値を高められるか? そのような企業を見つけられるか?
・実際にはPMIが重要。美味しい話はなく、結構泥臭く、人間臭いことも重要そう。
・購入した会社の倒産時に、個人への責任を及ばないことが可能という点が、リスクヘッジとなりうる。
・特にユニークな中小企業は、日本にとっても存続が重要と感じた。
2週間前に読んだので多少のイメージ論になります。
・第一印象として、”転職、副業”のチャレンジでよくぶち当たる壁を感じたのが正直なところです。その壁とは、、、、”有名企業に勤める”という定冠詞がついていたことです。
・こういったことを馬鹿正直に信じ、邁進する強い気持ちが必要である!ということに帰結すればよいのだろうと思いました。
■読む前に、この本に期待していたことは?
①:「頭のいい人のインプット手法(とくに新聞)を知る。」
②:「数ある読書法の一つのhowを知り、取り入れる箇所を探す(全てマネはしない)」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「読書をタイパ(得られるもの / 時間)よく得るための手法が書かれた本」
◎感想・得たこと
①:「頭のいい人のインプット手法(とくに新聞)を知る。」
ネット、新聞、ニュースサイト等多くの情報に振り回されるぐらいであれば「日経新聞を読むことを始めることがおすすめ。新聞は全体を俯瞰できる」とのことでした。
個人的には、新聞ざっと眺める程度で全体俯瞰で良いのかなと感じました。また書籍にかかれていた「ビジネス誌(ダイヤモンドや東洋経済など)は、特集について深堀りされていて初心者におすすめ」とのことであり、どちらかというまずはここから読んでみるのが良いのでは?と感じました。
②:「数ある読書法の一つのhowを知り、取り入れる箇所を探す(全てマネはしない)」
書籍に書かれていたこととしては、
・1ページ目から、全て読まなくて良い
・目次をみて全体を俯瞰する
・ビジネス書や実用書は、第1章とはじめに、終わりにを見れば、書籍の7割は理解できる
・ビジネス書や実用書は同じようなことをが複数の書籍にかかれているので、さらっとみる
・ビジネス書には「共通ポイント」があり、排除できない要素が存在することがほとんどなので
・書き込んだりしながら、一気に読む。そしてマーカーを引いた部分のみ再読することにより、定着率が上がる。
このあたりから、全体俯瞰をすることは守りつつも後は自信の気の向くままに楽しく読書を取り組むことを目指そうと思います。また、同系統の本を固め読みするほうが、一気に幅とと深さをしかも(読み飛ばせるので)効率よく手に入れられそうなので、同系統を固め読み(そのタイミングで興味も出ているし)をしていくのがおすすめではないかと思います。
その他:
・本の上部1/3のみを読むだけで書いてる内容が理解できるという研究結果(タイポグリセミア現象)がありこれをすることにより、読書ペースを速めることができる。(一言一句読む必要はない。)
というのが、ありこれは実際に書籍に練習できるページがしっかり割かれており、これがこの書籍で最も大きな収穫なのではないかと感じました。しばらく、タイポグリセミアを意識して読みたいと思います。
やりたいことを項目を埋めるだけで大枠の方向性を理解できるわかりやすさが本書の売りと感じた。
構造化と言語化が得意な作者だけあって、迷いそうなポイントを先回りして記載してくれているので、時間をかければ誰でも一定のやりたいことを見つけられる。
ただ、読み手の構造化力や言語能力にも依存するので、うまく対話の機会を設けられるとさらに深く学べそう。
呼んでとても気持ちが楽になりました。
・ねばならないの呪縛が減りました。
会社で出世しなくてはいけない、一生の仕事を見つけなくてはいけない、専門知識を身に着けなくてはいけない
↓
できなかった時の自己否定で病む
↓
繰り返し
「好きなこと×得意なこと×大事なこと=やりたいこと」から仕事を考えれば、今ある仕事からでも見つけることができて
気が楽になる。
また、異動・転職・スキルアップの意思決定にとても前向きに考えやすいと思いました!
好きな事・得意な事・大事な事をそれぞれどうやって言語化するのか?それぞれをどのようにして掛け合わ、自分のやりたいことを見つけたら良いのかプロセスを理解できました。
時間をとってそれぞれの言語化をやりたいと思っています。
「やりたいこと」を分解して、分かりやすく論理的に説明された本。やりたいことは好きなことから考えるべきではいない。まずは自分の「得意な事」、「大事な事」を考え最後に「好きな事」の順に考えるという順序だてがいかに大切かを学んだ。
■読む前に、この本に期待していたことは?
①:「どのようにして、普段の生活からぽんぽん問いをたてられるか?」
②:「書籍を読む際、鋭い問を立てるためにはどうすればよいか?」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「読書以外も含めた日常生活でも、問いを持つことによって独学していくための方法が書かれた本」
◎感想・得たこと
①:「どのようにして、普段の生活からぽんぽん問いをたてられるか?」
「実用的知的欲求(要はやらねばみたいなもの)」ではなく、「純粋知的欲求」を求めることを意識し、ビジネスのような鋭い問いを常に意識はせず気楽にとらえ楽しむことを優先することが大事であるとのこと。
現時点での私自身がそうであり、まずは純粋知的欲求を育みそれによって読書や日々の独学を加速/継続させることが重要であると感じています。
②:「書籍を読む際、鋭い問を立てるためにはどうすればよいか?」
基本的には、後述の独学の3階層フレームワークを利用し、徐々に問いをするどくさせる訓練をそれぞれ行っていくことが大事であると書かれていました。
その中でも、私自身が重要そうだと感じたことは、"差分"です。"差分"は経験前後(学習なども含む)の違いとしてほんの少しの2ミリでもいいのでそれを大事に学びとして消化することが重要であるとのこと。また、「◯◯だと再認識した」のような一般解は思考を止めてしまうため、できる限り自身の経験に落とし込んだものとして具体的な事例で差分を感じることが重要であるそうです。
こういったように、それぞれの筋力を鍛えることにより独学のちからがついていくと書籍では書かれていました。
◎独学の3階層
第1階層:独学のための「行為」
疑問
差分
他者
第2階層:独学のための「能力」
自己批判筋
保留筋
抽象化筋
具体化筋
表現筋
第3階層:独学のための「土台」
ラーニングパレット
■読む前に、この本に期待していたことは?
「本の選び方をしりたい」
「アウトプット手法のパターンを知りたい」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「気楽に継続してアウトプットしよう。でも、慣れてきたら/時間があるときはしっかりと自分の言葉でアウトプットすることによって血肉化する。」
◎感想・得たこと
アウトプットは質にこだわらず、「2008年8月5日 ◯◯◯◯◯読了。面白かった」まずは継続を目指してアウトプットすることが大事であると書かれていたが、実際私自身の学習/読書でも、日々福利を感じているので小さくでも継続しようと思う。
そして、かけるときは「ねぎま式」(書籍の内容の抜き書き + 感想・意見)で記述することによりアウトプットの質を目指そうと思いました。一方でほんの要約は時間がかかり継続性を失うのでおすすめしないと書かれており、これも要約はできるときだけぐらいに止めようと感じました。
また、「本の読み方はメリハリをつけ、自転車が傾斜によってギアをこまめにかえるように、よく引っかかるところでは低いギアでしっかりと、抵抗がないところは高いギアすべるようにイメージして読む」あったように、全てまんべんなくはたしかに疲れるため最近は目次で当たりをつけた箇所をじっくりと読み興味がわかないなーと感じたら流す気持ちで読み進めることにより結局気楽に全て読めたりすることが多いので、気の持ちようによって読書体験がよりよい状態に変わることを体感しています。
そして、コロコロと読みたい本が変わることを許容し、そのときの気持ちのまま読むほうがよいというところも、学生時代と違いMustで読まないといけないわけではないので気楽に読みたいものを読むを意識したいと感じました。
最後に最も納得感があったのは、「基本的には、帯や広告に触発されたり、一時的な気分で買うのではなく、落ち着いているときの自分からわいた考えで、主体的に本を選ぶことが重要」ということが大きな気付きでした。というのも、これまでポップやネットのnote記事に触発されて勢いで読み始めていましたが、結局続かないことも多かったので、買うまではいいが、読み始めるかどうか?は慎重になろうとも思いました。
まずこの本に出会えて良かったと素直にそう思った。良かったと感じた点は3つある。
1つ目は、過去に他人とのコミュニケーションで感じたモヤモヤの正体を知ることができたこと。
2つ目は、独り言などの一見無意味に見える行動にもロジックが存在すること。
3つ目は、この本の知識を頭に入れた状態で小説・漫画や映画などのフィクションの世界に触れることで見える景色が変わると思えたこと。
■モヤモヤの正体が知れてよかったことについて
SNS上で発生するいわゆる炎上という現象や、差別的な発言を見たときに「一見発言者は真っ当なことを言ってるように見えるが、攻撃的で確実な悪意を持っていることを感じる。しかしそれを指摘することができない」という心理状態になることが多々あった。ようは「この人絶対に攻撃する目的で発言してるけど、それを批判されないような言い方でごまかしてる」といった感覚を覚える場面が多かった。
この本を読んだあとに、それは何故か?ということとそういう場面に出くわしたときに次回からどうしたら良いか?という解を自分の中で見出すことができた。これは非常に大きい発見だった。
詳しくは本の魅力を削いでしまうため書けないが、端的に言うと「人のコミュニケーションで起こってる理不尽の正体」が何かをこれを読むことで理解することができるようになる。
・・・と書くと物騒に聞こえるが、この本は別にそういったコミュニケーションの指南書ではない。フィクションの世界でかわされる会話に置いて、どういったコミュニケーションが起こっているかを解説してくれている。
表紙の帯に書かれている「好きだ」と言わないことで何を伝えているのか?
といった紹介文はまさにそのことで、この本は「人は会話においてどういった認識を形成しているか」を丁寧に解説してくれている。その内容に触れることで、応用して様々な会話場面においての意味合いを自分に置き換えて推し量れるような知識が身につく。
さらに読み進めることで、
■独り言を言うことで自分は何をしようとしているのか
も段階的に理解が進むようになる。
人間が避けては通れない会話という行為にどういった側面が潜んでいて、私達が知らず知らずのうちに何を行おうとしているか。それがわかってくると、今度は
■フィクションの世界における会話の側面で何が行われているか
を知りたいという欲が生まれ、小説や漫画を読み進めるのが楽しくなってくるのを感じた。
長くなったが、総じて「会話とは何か?何をしようとしているか?」を体系的に学ぶことができ、また題材となっているものがフィクションの作品なので、楽しみながら読み進めることができる。気づくとどんどんページを捲っていて、あっという間に読み終えることができた。
この本に出会えて良かった。
■読む前に、この本に期待していたことは?
以下のような問いを立てて読み進めました。
「1冊から学びを多く吸収するにはどうすればいいか?」
「Kindle、紙の本などばらけているが、良い管理方法やKindleだからこその読み方などを、知りたい」
■読んでみてどうだったか?
◎この本を一言でいうと
"アウトプット" と "スキマ時間"この2つを意識すれば、記憶に残る読書ができる。
◎感想・得たこと
「読書自体の大事さ、アウトプットの大事さと、そのアウトプット手法を伝えてくれている本」であると考えました。
※さすが、この本のあとアウトプット大全を書かれた著者というふうに思いました。
「インプット量UP」▶「アウトプット量UP」▶「自己成長のスピードUP」のサイクルを作るために、まずはインプットの大切さがあり、インプット量として、「一人で経験し学べることには限界がある中で、本ではたくさんの人をの経験と学びをたくさん吸収できるという意味で重要である」というのがしっくり来て、読書の価値を再認識。
また、本を読まない人は、"悩み事"を抱えたときに視野狭窄に陥るケースが著者としては多いそうで、そのときに読書習慣がある人は本を読むことにより問題解決を試みるとのこと。
また、様々なアウトプット手法や、アウトプットのペースが書かれており参考になりました。
・本を読みながらメモをとる/マーカーを引く
・本の内容を人に話す。本を人に進める
・本の感想や気付きを投稿する。Twitterやブログに書評やレビューを書く(まさにこれ)
など。
そして、読書時間の確保に関しては、以下のようなことを意識することで改善ができるとのことであり、学びとして大きかったです。
・心を動かすように読む(今/今日読みたい本を朝に選ぶ、モチベーションが上がったときにその瞬間に読む等)
・スキマ時間を活用する
・決めた時間に読む(今日読み切る!電車を降りるまでに3章を読み終える!など)▶これにより脳内物質が分泌されされ記憶にも残りやすくなるとのこと
・すべて読まなくてもいいと考え、気になるところを読む
最後に本を読むに当たり問いを立てた「Kindle(電子書籍)での活用法」はガジェット好きの僕としてはあまり学びがなかったですが、これまでKindleに触れていない方は納得感があると思います。
■読む前に、この本に期待していたことは?
以下のような問いを立てて読み進めました。
・「スモールビジネスのよさを理解」
・「スモールビジネスは、どうやってはじめられるか?割に合うのか?どのくらいやる必要があるのか?」
・「スモールビジネスの見つけ方は?」
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「自己のスキルの正当な認識・資産家になる手段はたくさんある」
◎感想・得たこと
「サラリーマンから資産家にいかになるか?(特に)大企業の管理職であれば培ってきたノウハウ・コネクションを活用し、個人でもM&Aを行うための手法を説明した書籍」である。
本書に書かれているようにベンチャー企業の上場確率は0.3%(別のソースで調べるとさらに低い0.094%)とかなり低くリスクも伴うことが書かれており、だからこそM&A等で中小企業を買収することが良いとのことで、一定は理解できたと思います。
ただ、前提として
・「大企業の管理職(部長級以上)である」
・「50歳前後」
が隠れているように感じました。
もちろん、上記がなくてもできるとは思いますが、そこが割と前提であるように見えます。
あと、ポイントとして雇われ経営者ではなく、オーナーになっておく必要があり、キャピタルゲインや、バイアウト時のリターンを意識したものとなっていました。
また、飲食店経営は経営学のすべてを詰め込んだものであり手を出すなと書かれていましたが、個人的にはMBAを取得したのでTRYしてみたい気持ちが芽生えたりもしました。
はじめ方としても、LBO・第二会社方式・無利子での金融機関からの借り入れ等手段が多くあり、自身が取り組みたいと考えた事業・企業があればニアに頭手段を構築できそうであると感じることができました。
買後時/後のポイントとしては、隠し不正・会計などがないように、「まずは2年で役員として入る」が理想的だと感じました。
明確な防衛法はない。場に流されない、思考停止しない、冷静に考えることがもっとも効果的な防衛法であることが改めて学びになりました。
また自身の成果を得るためのポイントも学べた一方で、相手に損をさせるような誘導は長期的にお互いに損をすることになるように感じます。テクニックを利用する際には、相手に不快にならない、一方的に損にならないような形を意識したいと思います。
人は意識して気合を入れて考えるようにしないと、無意識のうちに影響力によって承諾させられたりしていることを改めて認識できました。
好意を持ってもらい、Yesと言ってもらいやすくする
恩を売る。恩を返してもらえない人にはあまり近づかない
一貫性を持って行動しようと意識している。行き過ぎた一貫性によって手戻るのを嫌がる。
逆に最初に決めた場合、そのまま押し通しやすくなっている
権威の力を利用することはときどきやります。社長を説得して、社長の会社だからやりましょうとなる
限定品は、周りに人にはわかっていても購入しようとする傾向がある
自分の心としっかり向き合い、影響力を受けていないか、できるかどうかは別として、
本当にメリットがあるかを考える大切さを認識しました
--------------------
人が好意を持つ5つの要素の1つ 類似性 を見つけました
青木仁志さん
出身
選択理論で人生が変わった
クリスチャン
に弱い
https://www.youtube.com/watch?v=x-CTfvBQ38Y 4:24
これだけ人と会って、いろんな人をみて、失敗もしてきていても、わかっていても好意を持ってしまう事例
好意を持ってしまう前提で進めるしかないですね
とはいえ、まず、自分はどんな人に好意を持ってしまうかを把握するところから
影響力というのは強力と実感します
自分が持つ「希少性」は何だろうか?というのを考える機会になりました。本書ではモノ、情報に関する希少性について書かれていましたが、スキルもその一つかなと思います。希少性は社内外ともに行使できる影響力であり、競合、競争相手と比較した上での希少性の行使を行動したいと思います。
この本の構成が好きです。理由は、章の終わりに設問があり答えようとするとかなり中身を精読しないと答えられなくて、この本らしく動かされていると感じるからです笑
章末にある設問のタイプは2つ。
1、内容の理解を問う問題
2、クリティカルシンキングとして、基礎的な理解を踏まえてあなただったらこのケースについてどう対応しますか?というもの。
中身は多岐にわたるので個別の学びではなく、この本を読むメリットの一つを残しておきます。
この世の中には、影響力の武器を使って人を動かそうとする、悪い人がいるのでその様な人と対峙した時に、正しく状況を認識して防御できるという事があげられる!が大きいと思います。
良き大志を抱き世界を動かすのもいいですけど。
■読む前に、この本に期待していたことは?
「読書を通してアウトプットの質を上げる」「読書で楽しむ方法をしる」この2つをテーマに読み進ようと思いました。
■読んでみてどうだったか?
◎一言でこの本からの学びを書くとするなら
「戦略的に読書を捉えつつも日々読むときは気楽に」かなと感じました。
◎感想・得たこと
一番得たものとしては、「新たな問い」「既存の問い」「新たな答え」「既存の答え」この4つでポートフォリオを組んで書籍を分類し、自信のその日/期間の状態や、読書体力によって読むものを変えるていくというのが大きな発見でした。
あとは、べき論(「こういうふうに本は読むべき」)みたいなものを持たずに、自由に読むことが推奨されていることによって気が楽になりました。
一方で「問い」を持ち「答え」を探しながら読むことが重要であるという観点は日々読書をする中でアウトプットの質に繋がりそうで良さそうです。ただ、自由に読むが前提なので必ずしもここにこだわらなくて良いとは感じます。
その他にはアウトプットの機会を作ることにより、吸収も読むことにも前のめりになること。"具体的"な自身の問いから、"抽象的な問い"に変換し、本に書かれている答えから、"具体的な自身の答え"につなげていくあたりを読み、やはり具体と抽象の大事さを再認識しました。
また、本と動画の違い(余白のあり/なし)についても書かれており、本を読む価値を体感できました。
あとは、6つの読書の病を知ることにより、この本のコンセプトでもある「楽しく読書する」を達成するための心構えを身につけられました。
◎読書の病
・完読の病
・コミットメントの病
・積読の病
・実践の病
・読書時間不足の病
結果を出せる営業のノウハウ(BtoB)が分かり易く言語化されていると感じています。
これまでこういう事を意識していたなと思う事がうまくまとまっていると感じており、また意外にBtoB用の営業ノウハウはまとまっていないというイメージがあります。
営業の進め方とやり方がまとまってるのかなと。このやり方の部分まで掘り下げているのもよい部分と感じます。
商談の状況を把握し、接戦状況に強くなる事。2-6-2の6をどれだけとれるか?ここの営業筋力をあげる。
結局は金額で決まるという固定概念をとり、いかに営業次第で決まるのだという事を理解させる事が大切と感じてます。
現在の部署は営業を受ける機会が多いのですが、思い返してみるとこの本のメソッドに沿って提案をしてきている会社(主にIT関連)が結構あるなと感じました。とはいえ、こういった営業方法の表面だけを真似ているような人に対して発注しようとはならないので、「4つの力」を血肉にするというか違和感なく発揮できるようにならないと好成績を残せる営業マンにはなれないのだろうないう気がします。
個人的には最後の方に書かれていたルート型、アカウント型の営業の切り分けが面白かったので、この辺の話をもっと詳しく知りたいと思いました。
本の冒頭で書かれている「情報のズレ」を合わせることが大事ということが一番印象に残りました。
自身の性格を考えると、楽勝案件を探したくなったり、負け戦に近いものをなんとか頑張ろうとする習性がある中で、「接戦が最も注力すべき」という気付きも面白かったです。
また、"深堀り質問"のやりかたなどは、ユーザインタビューなどにも使えそうであり営業以外の場面でも使えそうなことがたくさん書かれており学びが大きかったです。
自分が営業という職種を経験したことがないという前提なのですが、コンペがどこで決まるのか?など考えたことがない問いがたくさんあり、新鮮でした!!
それと、具体的に今日から使える抽象化された汎用的なノウハウがたくさんあり(自分としてはこれを具体的な洞察の引き出しと命名)試したくなります。インタビューの時など少しいじってさっそく明日試しますw
今の自分にとっては、1~4章の概論の所が刺さる所が多く、5章以降の4つの力の解説(質問力以外の、価値訴求力、提案ロジック構築力、提案行動力)については、具体例や図解などが多くわかりやすいのですが、抽象化して自分への引き寄せが結構難しかった。
読書会を使っていろいろ深掘りをする為にこのままの状態で残しておきます。それに合わせて、noteもアップデートを掛けていきます。
■読む前に、この本に期待していたことは?
サービスづくりを行うにあたって、AARRR指標を思い出し、そこからサービス立ち上げのタイミングだとARRRAのほうがよいというのをネットでみて本書にたどり着きました。
ARRRAの基礎と、事例を知ることができるといいと思います。
■読んでみてどうだったか?
webサービスを作っていくにあたり、AARRRモデルではなく、ARRRAモデルで見たほうが良いことがすごく理解できました。「つまりはSaaSでいうバケツの穴を防ごう」ことであり、一つ一つ手前から順に解消していくことが重要であると感じました。
また、超優秀なグロースハッカーでも、「10回トライして1回成功」すればいいというのが通常であるというのは、すぐく勇気づけられました。裏をかえすと、10回に1回も施策がうまくいかないということであり、きちんと仮説検証と計測をすべきなんだろうとも感じました。
とはいえ失敗に対する理解として、
「Fail fast(早く失敗しよう)、Fail often(たくさん失敗しよう)、Fail smart(賢く失敗しよう)」
と、あるように早さも大事だということなので、小さな施策を繰り返すのが良さそうです。
●重要な指標
・Activation: 活性化 (利用してくれる)
・Retention: 継続 (使い続けてくれる)
・Referral: 推奨 (他者にすすめてくれる)
・Revenue: 収益 (お金を払って使ってくれる)
・Acquisition: 顧客獲得 (顧客になってくれる)
■読む前に、この本に期待していたことは?
グロービスで問い(イシュー)というワードを使用することは多かったですが、ケースも問いが設定されているパターンも多く、問いからまっさらな状態で考えることは割りと多くはなかったと感じています。
そんな中で実際の仕事では、役割上”「問い」の設定”から考えることも多く感じており、この書籍を読んでみたいと思い読みました。
■読んでみてどうだったか?
問の設計の仕方をかなり丁寧に書かれていて、学びが多かったです。
一方で、項目や注意ポイントが多かったので一気には覚えられないなという印象でした。
■読む前に、この本に期待していたことは?
チームやプロジェクトの仲間をうまく鼓舞できるときもあれば、関係部署などの方々などはなかなかうまくできないことが多く、そこの違いを知りたくて読みました。
■読んでみてどうだったか?
重要な要素それぞれ、これまでの経験と振り返って使っていた使えていなかったがはっきりとわかり面白かったです。また、「コミットメントと一貫性」は、サービス作りで利用者になにか宣言してもらうなどができそうに感じて(書籍には書かれてなく僕自身の気づき)おもしろかったです。
●重要な7要素
以下、7要素を活用することにより、「カチッ・サー(固定的動作パターン)」となってもらうことを目標とする。
1 影響力の武器「コントラストの原理」
2 影響力の武器「返報性(へんぽうせい)」
3 影響力の武器「コミットメントと一貫性」
4 影響力の武器「社会的証明」
5 影響力の武器「好意」
6 影響力の武器「権威」
7 影響力の武器「希少性」
■読む前に、この本に期待していたことは?
AIというよりは、「ハーベストループ」もっというと、Amazonの"フライホイール"を今考えているサービスでどう描くか?を考えるヒントとして読みました。
なので、AIの活用ではなく、フライホイール(=ハーベストループ)の事例を通して、「いかに構築していくのか?」の解像度を上げたいと考えていました。
■読んでみてどうだったか?
フライホイールの解像度は具体的な事例で上がったのはもちろん、
AIをどのように活用するか?業界・業種でのハーベストループへの組み込み方、そのパターンを知ることができAIを組み込むための考えを深めることができました。
本来こっちが書籍で伝えたいことだったと思うのでそれも含めた良かったです。
■読む前に、この本に期待していたことは?
結構ずけずけと発言する割に嫌われることに抵抗があり、万人受けしたいと思う面がたまに出てきます。
どっちが自分に取っていいのかわからないですが、この本からなにか方向性なりを得られるといいなと思いタイトルで選びました。
■読んでみてどうだったか?
「課題の分離」は相手の問題にまで首を突っ込まないようにできそうと気づけたのと、その反面書籍にも書かれていた「個別化?」のような状態にならないか?と感じましたが、読み進めていくと課題の分離のタイミングで、自分の課題だと捉える部分・その人が仲間かどうか?(共同体)で捉え方がかわるという意味でスッキリしました。
ただ、最終章の部分の、「人生は線ではなく、刹那で捉える」の部分は正直まだ落とし込めていないです。
■読む前に、この本に期待していたことは?
自身が通っていた大学院で書かれた書籍だったので、興味本位で買いました。
マーケティングであったりとかユーザ価値みたいなところが書かれているといいなという期待で購入。
■読んでみてどうだったか?
マーケティング、ユーザ価値の部分に関しては書かれていなかったですが、主に「ヒト系」について書かれた本でした。「優秀な人を集めているグロービスだからこそ、できるな」と感じる部分もありましたが、ほんとにお手本通りにキレイに「採用・配置・育成・評価・報酬」が回っており感心しました。
自社にこれを当てはめるにはどうすればいいか?という落とし込みどころが他の本よりも正直難しく感じていたので、読書会に期待です。
■読む前に、この本に期待していたことは?
起業を考えており、別のエフェクチュエーションという分厚い本があり、それを読もうか迷っていたときにこの本が発売されることを知り予約したのがきっかけです。
これまで会社員として10年以上働いているので、起業していくにあたりマインドを少しでも変えていきたく、「起業家マインドをどう得ていけばいいか?行動様式を知りたい」ということで読みました。
■読んでみてどうだったか?
5つの原則を知ることにより少し自分でも初めて行けそうな気がしました。
とくに「許容可能な損失」についてが印象的で、どこまでであれば損失を許容できるか?を考えるとやれることの幅を徐々に増やしていけそうな気がしました。また、書籍の中で、損失が許容可能でなくなったタイミングも事例として書かれておりリアルさがより自身が進めていくに当たり、この5つを意識した活動ができそうだなと感じた書籍でした。
●5つの原則
「手中の鳥」(Bird in Hand)
「許容可能な損失」(Affordable Loss)
「クレイジーキルト」(Crazy-Quilt)
「レモネード」(Lemonade)
「飛行機の中のパイロット」(Pilot-in-the-plane)
■読む前に、この本に期待していたことは?
ChatGPTをなんだかんだ使っていなかったので、そういった意味でまずは初歩的なところから理解しようと思い選びました。なので、基礎とどのように使うのが良いのか?深さよりも幅をとれればいいというイメージで読んでいました。
■読んでみてどうだったか?
読んでいるだけだと理解が進まなく感じたので、写経のように実際にプロンプトに打ち込んでみたりすることによってできることの理解が深まりました。
また想定通りどんなことができるか?幅をしれたので良かったです。
■次回読みたい本
本書とは関係ないが最近のトレンドに触れられていないので、AI・web3あたりも基礎的なことは読み進めていきたい
■読む前に、このスライドに期待していたことは?
toC領域のサービス経験がないなかで、どのようにしてサービス立ち上げ期にサービスを売るか?というのを知りたくてこのスライドにたどり着きました。
■読んでみてどうだったか?
toBよりのサービス立ち上げのほうが色が強い気もしますが、マーケティングに頼らずに自ら手売りしろというのがすごくしっくりきた。(ユーザフィードバックをファウンダーがもらう必要性、そのためにもセールスをするなどなど)。
■次回読みたい本
逆にセールスでいかずにPLG(プロダクトレッドグロース)で売るにはどうするのか?に関して読みたい。
https://app.tomogaku.com/interests/d/116/
■読もうと思った背景
田所さんの書籍関連の「流れ」をざっくりと理解するために、読んだ。
■読んでみてどうだったか?
ストーリーとして読むので記憶に定着しやすい。
一方で網羅的には書かれていないので、起業の科学
→起業大全を読みながら実際は読み進める必要あり。
■読もうと思った背景
サービス作りの際に、より深く考えられるように
①:ユーザーインタビューから顧客インサイトを知るために、ユーザーの状態をより知るスタンスになれるように
②: プロトタイプ、MVPなどの、仮説検証からより深い解像度で考えられるように
■読んでみてどうだったか?
・使いこなせると素晴らしいが、覚えることがたくさん。改めてもっかい読んでみると良いかも。
・最も気づきとしてあったのは、「時間」の概念を理解したことかと思います。他の論理思考などの本やフレームワークではそれ以外の広さや深さなどはみますが、時間の概念が薄い理解だったので、このあたりが大きな学びでした。
◯解像度を上げる方法7つ
<課題の解像度を上げる>
「広さ」
「構造」
「時間」
<解決策の改造を上げる>
「深さ」
「広さ」
「構造」
「時間」
■考えていきたいポイント
どうやってこの思考訓練を日々していくのがよいのか?考えたい
■読もうと思った背景
起業家の精神性、メンタル、価値観を知るため
■読んでみてどうだったか?
江副さんは孤独であり、家庭とバランスを取るのはやはり難しかったことがうかがい知れる。
また、ホリエモンの本を読んだ時にも似た感覚があったなと。 (古い体質を受け入れない一部が潰しにかかっているというかなんというか、、、 )
江副さんの実体験から来るところが多くのサービスにあるなーとも感じた。
自分ごとの事業であること大事。
■読む前に、この本に期待していたことは?
直接勉強ではないですが、読書量を増やしたくこの本を読もうと思いました。
また、自身の子供がもう少し大きくなったときに、いい意味で勉強に中毒化(はまるという意味で)してくれるといいなとも思い読みました。
■読んでみてどうだったか?
本書に書かれている「情熱・密着・達成・環境」の4項目を満たすことによって勉強に夢中になれることが書かれており、更にそのそれぞれをどう満たしていくか?それぞれを組み合わせると?と、具体的な事例が書かれておりまた真似しやすいものが多くおもしろかったです。
また、自身の学生時代に勉強を取り組んでいたときに工夫していたことと一部重なる部分があり、編み出したもの(オンライン自習室や、スマホの1画面目に勉強系を増やすなど)が、要は「密着
や環境を満たす行動だったんだ!」という気付きがあり面白かったです。
■次回読みたい本
この本を通して、どうやったら人はハマるのか?を知りたくなりました。
仕事でプロダクトマネージャーを志向しているので、ゲーミフィケーション関連の本を読んでみようかと思います。
■読む前に、この本に期待していたことは?
知り合いのイベントに参加するため読む必要があり、たまたまこの本を知り購入。
起業予定だが、会社員としてしばらくは働くだろうし読んでおくかーという感じ。
■読んでみてどうだったか?
想像よりも中身が濃く楽しんで読むことができました。
これまで会社員として自身がやってきて正解だったんだ、だからうまく行かなかったんだ(本書に書かれているセオリーと逆のことを実施)という気付きが多かったです。
その中でも「仕事は所詮RPG」「上司とははしごを外すもの」という2つが自信の経験からぶっ刺さりました。
この物語の主人公「成瀬」と比べると、自分はまだまだ色んなことに挑戦する心、野心的なものが足りていないということに気づいた。そして同時に、読了後に「もっと頑張ろう!」というモチベーションが湧いてくる本でもあった。
この本はいわゆる小説であり、読んでいて普通に面白い。青春を謳歌するいち中高生の挑戦を追体験するような内容になっている。ただその追体験により、ビジネスマンとしての情熱を呼び戻されるような感覚になる。
近所の百貨店が潰れるから、それまでの1ヶ月間毎日通ってテレビに映るという挑戦。
お笑いをするために、M-1グランプリに出場するという挑戦。
そのどれもが読んでいて熱くなり、キャラクターにも引き込まれていく。
小説の感想としては、「キャラが立っていてストーリも面白く、一気に読める内容でした」となるが、自身の明日への活力を貰えたようなこの感覚が一番読んで価値を感じた部分。ぜひ、ビジネスマンにも読んでほしい。
Youtubeでおすすめしてる動画をきっかけに購入しました。
他人との付き合い方や自分自身で行動をするときの意思決定を考える時に、影響を与えるような本でした。
この本を読んで一番大きく自覚したのは、過去に自分の意志で決定してきたと思っていた内容は実は他人からの影響を大きく受けていたと言う事でした。本当は他人の都合なのに、それを自分の都合のように思って行動していたことがたくさんあったなと思いました。
それによって過去の自分は不安をいだいたり、後悔するようなことがあったのですが、この本を読んだあとはそういったことは減るのではないかと。
作中でも触れられていますが、自分が今まで生きてきたスタイルを変えるのは確かに大変だし、変えないほうが楽だと思います。でも、ちょっと頑張って一歩を踏み出してみようかな・・・そんな思いにさせてくれるような本です。ただ、一度読んだだけではまだ理解しきれてないような気もするので、何度か反芻してみようと思います。
一人で読むのもいいですが、読書会でディスカッションを交わすと他の人の解釈やスタイルの考え方をしれて、とてもいい刺激になりました。